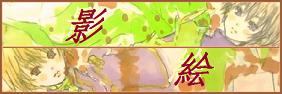自作小説「水の車輪」の原稿置き場です。 ※未熟ではありますが著作権を放棄しておりません。著作権に関わる行為は固くお断り致します。どうぞよろしくお願い致します。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
五、
城下に広がる町には、新鮮な空気があふれている。
焼けた甘いパンの匂い、水で無造作に洗われた野菜の匂い、少しだけ血の味を連想させる、生臭い魚の匂い。
男の匂い、女の匂い。母親の匂い、子供の匂い、年寄りの匂い。
綺麗に磨かれた清潔な香り。垂れ流したままの汚物の匂い。
それら全てがキオの鼻をつき、生きていると知らせてくれる。
大げさかもしれない。そんなことは分かっている。
けれど、閉ざされた窓の奥で、人工的に灯された明かりの下で、既製品として作られたペンを握って文字を書く日常よりもずっと、日のあたる場所で餓鬼のように土に木の棒で絵ともいえない代物を描いたり、他にないからと果汁の余りや魚の血でとりあえず文字を書く、そういう街の庶民の動作が好きだった。綺麗なようで汚い。汚いようで磨かれている。
こういう暮らしがあるのだと、見せてくれたのはレミオだった。正しく言うなら、ふらふらと庶民の街に迷い込んだ彼女の捜索隊にちゃっかり自分も紛れ込んだだけだったが。
けれど、新しい発見だった。あの造られた邸から抜け出すこと、自分の足で歩くこと、思いもつかなかった。言われるままに背中を押され、差し出された手をとり、ただ馬車に乗るだけ。特に景色にも興味はなかった。どうせ自分とは無縁の世界だ。キオの関心を引いたのはただ、馬車の天井の角、つなぎ目部分にあるちょっとした錆だった。どうせここからは出ていいと言われなければ出られない。出たいとも思わない。なぜなら、いきなり一人で外に放り出されても何処へ行けばいいのか分からないのだし。
レミオを探しに行ったのは単なる気まぐれだった。レミオは正真正銘の阿呆だと思う。どうせぼけっとしていて邸から出て戻ってこれなくなったんだろう、と思った。途方に暮れてべそをかいているなら、その面を思い切り小馬鹿にした目で笑いくだしてやりたいと思った。もし泣きもせずぼけっとしているならそれはそれで面白い。退屈しのぎにはなる。なんだかんだでキオは別にレミオを嫌っているわけじゃなかった。だから別に、怒るのも本気なわけではない。けれど、レミオのへまやぼけに少しずつ怒鳴っていくうちに、気づいた。自分にはこんなにも揺らぐ気持ちがあったのだと。本当は苛々したかったのだということ。けれどただの怒りは自分の内に溜まるだけだ。やがて自分を蝕むだけだ。だから怒らなかった。いつも静かに、ただ静かな気持ちで生きていれば苦しいことも悲しいこともない。抑えろ。抑えるんだ。動じることなどみっともない。ほら見てみろ、僕の父親は怒る時唾を飛ばす。なんて醜い。あんな風にはなりたくない。汚い。
けれど、本当はただ分からなくなっていただけなのかもしれない。今でも父親の癖は好きじゃない。不快感しか起こらない。それでも何か情はあって、たまに哀れになり、たまに可愛いなとも思う。不思議だと思う。気を使っていたことだけは確かだと思う。無意識にそれを覚えたのか、それとも言うことを聞けと以前怒られたことがあったのか、もう覚えていない。けれど不思議だった。どうしてレミオは笑うのだろう。泣くのだろう。あんなにぼんやりしているのだろう。危ないのに。ほら、また躓いた。危ない。危ない?
どうして危ないと思うのだろう。
不思議だった。いつの間にか、自分とはまるっきり違う奇妙な少女を目で追うようになっていた。そしていつしか、情までわくなんて。危ない、だなんて、心配にまでなるなんて。
怒鳴るのは体力が要る。苛つくのも体力を奪っていく。けれど、感情を爆発させ、ぶつけられるのはレミオだけだった。レミオになら何をしたっていい気がする。いいはけ口だ。そしてそういう自分が好きだ。いつの間にか好きになっていた。
たまに、やりすぎたかなとか、言い過ぎたかな、と思う時もある。けれどレミオは必ずふにゃりと笑った。どうでもいい。どうしたらいいのか分からないから、どうでもいい。
もう少し大人になったら、対処の仕方も、後始末の仕方もわかるんだろうか、とぼんやりと考えている。
ザゼリと会ったのも、レミオのおかげだったかもしれない。
馬鹿のレミオは港に散乱していた箱にもたれかかって、出っ張っていた釘で手を刺した。ものすごく泣いた。慌てて駆け寄って来たのがザゼリだ。鉄錆が体に入ったらどうするんだと思った。呆れてものもいえない。ザゼリはものすごくあたふたして、途中何度も荷物にけつまづいて、包帯の巻き方もがたがただった。自分のことじゃないのに、痛いよね、痛いよね、とぽろぽろ涙を流して消毒液をぼたぼた腕の方に垂れるくらい塗りたくった。
変な奴だな、と思った。どうしてレミオはいつも、僕に新鮮なものを運んでくるんだろう。こんななよなよした男、見たことがない。
興味が出たのは、ザゼリがレミオにどこか似ていて、しかも男だったからかもしれない。ザゼリは自分の知っていた男どものどれとも違っていた。ひょろひょろともやしのように頼りない。そばかすだらけのしまりのない顔と表情。どこどこのお嬢さんが可愛いだの、惚れた腫れただの、常に嬉しそうに話しては振られたと落ち込む。花束を渡そうとして、安い花を握り締めながら電柱の陰から相手を見つめているのを見た時にはさすがに引いた。酷い猫背だ。老婆のように腰が曲がった背中で、おどおどと相手を見つめている。そして嬉しそうに幸せそうにへらへらと笑っている。
「キオ、最近姿勢悪いよ?」
ザゼリは船から下ろした荷物をどさり、と床に置いて腰をそらした。
「あー、腰いてえ・・・」
「お前のが移ったんだよ。責任とれよこの野郎」
「は?え、でも、ええ?おれのせいぃ?」
ザゼリは頭を掻いた。キオと背中あわせに樽の上に座っていたエンデがこん、と後頭部をキオにぶつけてくる。背中に重みが加わった。
「疲れた」
「んだよ、もう根あげてんの?」
「編み方が難しい」
「絡ませたのはあんたらだろ。手伝ってやってんだからありがたく思えよ」
「わたしよりもキオの方が目数少ないじゃない。わたしはこれだけやったのよ?」
エンデは編み終わった綱を広げる。
「自業自得だろ」
キオが言うと、少し気分を害したらしいエンデは黙り込んで、また作業にとりかかった。ザゼリは目をこする。
「それにしても、レミオならわかるけど、エンデがへまをするって珍しいね?」
「半分はわたしのせいだもの、つまづいたから・・・」
床に座り込んでほつれた網目を直していたレミオが申し訳なさそうに言う。キオはつっこまずにはいられなかった。
「いや、お前、半分って。謙虚さ少しは学べ」
つっこんでしまってから、どうして自分は声を出すという面倒な動作をしてしまったのだろうとぼんやり考える。
ザゼリが思い出し笑いで噴き出した。肩が小刻みに揺れる。エンデが真っ赤になったのが首越しに伝わった。熱い。
「あんま笑ってやんなよ」
小さな声でキオは言う。
「だってさ、思わないじゃない、綱の網目の中にすっぽり、狙ったみたいに挟まるとかありえないだろ?いやああれは可愛かった。そして面白かった」
元々緩くなっていた網目の間に挟まったのはエンデだ。こけそうになったレミオの服を掴み、傍にあった綱をとっさに掴んだ。きちんと巻かれていた綱が一気にたるんで、二人してよろめいた。しかもレミオも綱を引っ張った。多分穴を広げたのはレミオの腕だったと思う。そこから慌てて手を抜こうとして、その手はエンデにしたたかにぶつかり、エンデはよろけて肩からその穴に突っ込んだ。そのあとたくさんの綱が落ちてきて、レミオの体に巻き付いた。もがくから余計に辺に結び目ができて、二人をそこから助け出すのも一苦労だった。周りは大爆笑だ。顔が火照りそうになって、キオは何とかこらえた。ここはきっと、呆れかえった方が二人のためだ。二人の皮膚が硬い綱に擦られてあちこち擦り向けていたのに少し胸が痛んだ気もしたが、ザゼリが自分の代わりに顔を真っ赤にして焦っていたので自分はもう気にしないことにした。
「しかもレミオはレミオでまるで蓑虫みたいな恰好なんだもんな。まったくほんとに。あんなのもう二度と見れない気がする」
ザゼリはまだ笑っている。そしてふと気がついた。
「エンデ、指の皮剥けてる。無理すんなよ」
「いいの。終わらないんだもの」
「血でてるじゃん。とりあえず消毒しろって。ここの物大して綺麗じゃないんだぜ」
「いいんだってば」
エンデの声は普段通りだ。淡々と静かで、抑揚すらない。けれど、言葉遣いがなんとなく違う気がした。どこがどう違うだなんて、キオには説明できない。ただ、声を出すことがためらわれる。不思議だ。
ザゼリは肩をすくめた。ただでさえ狭い樽の上に自分も腰かける。キオは意地でも場所を譲らなかった。なんとなく負けな気がしたからだ。結局少しずれたのはエンデだ。エンデが振り返って少し睨んできた気がした。ほんの少し心が跳ねた。びっくりしたのだ。エンデが感情を高ぶらせるなんて、めったにないことだ。いや、ほぼないことだ。
ザゼリはそのままただエンデの手元を眺めていた。何をするでもない。エンデも黙々と、先刻教えられた通りにほどけた五本の細い糸を固く編んでいく。
とても穏やかだ。肩に触れるザゼリの体温。背中に触れているエンデ。なんとなくキオの心は穏やかだった。こういう時間はなぜか嫌いじゃなかった。なんとなく、むずかゆくなってくる。けれど絶対に意地でもどいてなんかやらない。このままの風が好きだ。
ふと、キオは一人だけじべたにしゃがみこんで綱を編んでいるレミオを見やった。いつもならうんうん唸りながら作業をしているのに、先刻までそうだったのに、レミオは全く声を発しない。首が酷く曲がっている。流れた髪で顔は見えなかった。レミオにしては珍しく、空気を読んでいるんだろうかと思った。けれど、それにしても不自然に静かすぎる気がした。見なければ気づかないほどに空気に溶け込んでいる違和感。とはいえキオには関係ない。どうでもいいのだ。どうせレミオは何も考えちゃいないし、どうせすぐに忘れる。自分と違って、心に浮かんだことは染みだすように空気に溶けて消えていくのだ。構ってやろうとは思わない。構うと楽しいのはザゼリの方だからだ。それにエンデが付け加えられるとなお面白い。
顔にザゼリのおくれ毛がかぶさって来た。なんとなくキオはそれを指に巻き付けいじる。ザゼリがキオの方に顔を向けてきょとん、とした。とても可愛い表情だと思う。年上だけど。
「どうした?」
「別に?」
ザゼリはくすり、と笑った。今度はキオの手元を眺める。やがて目を閉じて顎を空に向けた。気持ち良さそうに風の匂いを嗅いでいる。
「お前さぁ、髪だけは綺麗だよな、いっちょ前に」
キオが言うと、ザゼリはのんびりした声で笑った。
「なんだよいっちょまえって。ひでえなあ」
綺麗だな、と思う。キオはエンデの背中にもたれかかった。エンデは何も言わない。そのまま支えてくれている。
キオはザゼリの金髪の束を空に向かってすかした。明るい。とても薄くて明るいそれは、心をなんとなく晴らしてくれる。キオは髪を手から離すと、ふう、と息をついて空を仰ぎ、自分も目を閉じた。
明るい。
自分を包む日の光も、この世の光も、自分を照らしてくれる。頬がぽかぽかと暖かくなる。いつか心臓が光の熱で焼かれればいいと思った。焼け焦げればいい。この日々が続くなら、きっと耐えられる。いつかもし、ヘラクレイトスの掟が自分達を阻みそうになるなら、この心臓ごと、あいつらを焼き焦がしてやる。
キオはとても満足していた。レミオに感謝してやってもいい。けれど絶対に、意地でも口には出してやらない。
城下に広がる町には、新鮮な空気があふれている。
焼けた甘いパンの匂い、水で無造作に洗われた野菜の匂い、少しだけ血の味を連想させる、生臭い魚の匂い。
男の匂い、女の匂い。母親の匂い、子供の匂い、年寄りの匂い。
綺麗に磨かれた清潔な香り。垂れ流したままの汚物の匂い。
それら全てがキオの鼻をつき、生きていると知らせてくれる。
大げさかもしれない。そんなことは分かっている。
けれど、閉ざされた窓の奥で、人工的に灯された明かりの下で、既製品として作られたペンを握って文字を書く日常よりもずっと、日のあたる場所で餓鬼のように土に木の棒で絵ともいえない代物を描いたり、他にないからと果汁の余りや魚の血でとりあえず文字を書く、そういう街の庶民の動作が好きだった。綺麗なようで汚い。汚いようで磨かれている。
こういう暮らしがあるのだと、見せてくれたのはレミオだった。正しく言うなら、ふらふらと庶民の街に迷い込んだ彼女の捜索隊にちゃっかり自分も紛れ込んだだけだったが。
けれど、新しい発見だった。あの造られた邸から抜け出すこと、自分の足で歩くこと、思いもつかなかった。言われるままに背中を押され、差し出された手をとり、ただ馬車に乗るだけ。特に景色にも興味はなかった。どうせ自分とは無縁の世界だ。キオの関心を引いたのはただ、馬車の天井の角、つなぎ目部分にあるちょっとした錆だった。どうせここからは出ていいと言われなければ出られない。出たいとも思わない。なぜなら、いきなり一人で外に放り出されても何処へ行けばいいのか分からないのだし。
レミオを探しに行ったのは単なる気まぐれだった。レミオは正真正銘の阿呆だと思う。どうせぼけっとしていて邸から出て戻ってこれなくなったんだろう、と思った。途方に暮れてべそをかいているなら、その面を思い切り小馬鹿にした目で笑いくだしてやりたいと思った。もし泣きもせずぼけっとしているならそれはそれで面白い。退屈しのぎにはなる。なんだかんだでキオは別にレミオを嫌っているわけじゃなかった。だから別に、怒るのも本気なわけではない。けれど、レミオのへまやぼけに少しずつ怒鳴っていくうちに、気づいた。自分にはこんなにも揺らぐ気持ちがあったのだと。本当は苛々したかったのだということ。けれどただの怒りは自分の内に溜まるだけだ。やがて自分を蝕むだけだ。だから怒らなかった。いつも静かに、ただ静かな気持ちで生きていれば苦しいことも悲しいこともない。抑えろ。抑えるんだ。動じることなどみっともない。ほら見てみろ、僕の父親は怒る時唾を飛ばす。なんて醜い。あんな風にはなりたくない。汚い。
けれど、本当はただ分からなくなっていただけなのかもしれない。今でも父親の癖は好きじゃない。不快感しか起こらない。それでも何か情はあって、たまに哀れになり、たまに可愛いなとも思う。不思議だと思う。気を使っていたことだけは確かだと思う。無意識にそれを覚えたのか、それとも言うことを聞けと以前怒られたことがあったのか、もう覚えていない。けれど不思議だった。どうしてレミオは笑うのだろう。泣くのだろう。あんなにぼんやりしているのだろう。危ないのに。ほら、また躓いた。危ない。危ない?
どうして危ないと思うのだろう。
不思議だった。いつの間にか、自分とはまるっきり違う奇妙な少女を目で追うようになっていた。そしていつしか、情までわくなんて。危ない、だなんて、心配にまでなるなんて。
怒鳴るのは体力が要る。苛つくのも体力を奪っていく。けれど、感情を爆発させ、ぶつけられるのはレミオだけだった。レミオになら何をしたっていい気がする。いいはけ口だ。そしてそういう自分が好きだ。いつの間にか好きになっていた。
たまに、やりすぎたかなとか、言い過ぎたかな、と思う時もある。けれどレミオは必ずふにゃりと笑った。どうでもいい。どうしたらいいのか分からないから、どうでもいい。
もう少し大人になったら、対処の仕方も、後始末の仕方もわかるんだろうか、とぼんやりと考えている。
ザゼリと会ったのも、レミオのおかげだったかもしれない。
馬鹿のレミオは港に散乱していた箱にもたれかかって、出っ張っていた釘で手を刺した。ものすごく泣いた。慌てて駆け寄って来たのがザゼリだ。鉄錆が体に入ったらどうするんだと思った。呆れてものもいえない。ザゼリはものすごくあたふたして、途中何度も荷物にけつまづいて、包帯の巻き方もがたがただった。自分のことじゃないのに、痛いよね、痛いよね、とぽろぽろ涙を流して消毒液をぼたぼた腕の方に垂れるくらい塗りたくった。
変な奴だな、と思った。どうしてレミオはいつも、僕に新鮮なものを運んでくるんだろう。こんななよなよした男、見たことがない。
興味が出たのは、ザゼリがレミオにどこか似ていて、しかも男だったからかもしれない。ザゼリは自分の知っていた男どものどれとも違っていた。ひょろひょろともやしのように頼りない。そばかすだらけのしまりのない顔と表情。どこどこのお嬢さんが可愛いだの、惚れた腫れただの、常に嬉しそうに話しては振られたと落ち込む。花束を渡そうとして、安い花を握り締めながら電柱の陰から相手を見つめているのを見た時にはさすがに引いた。酷い猫背だ。老婆のように腰が曲がった背中で、おどおどと相手を見つめている。そして嬉しそうに幸せそうにへらへらと笑っている。
「キオ、最近姿勢悪いよ?」
ザゼリは船から下ろした荷物をどさり、と床に置いて腰をそらした。
「あー、腰いてえ・・・」
「お前のが移ったんだよ。責任とれよこの野郎」
「は?え、でも、ええ?おれのせいぃ?」
ザゼリは頭を掻いた。キオと背中あわせに樽の上に座っていたエンデがこん、と後頭部をキオにぶつけてくる。背中に重みが加わった。
「疲れた」
「んだよ、もう根あげてんの?」
「編み方が難しい」
「絡ませたのはあんたらだろ。手伝ってやってんだからありがたく思えよ」
「わたしよりもキオの方が目数少ないじゃない。わたしはこれだけやったのよ?」
エンデは編み終わった綱を広げる。
「自業自得だろ」
キオが言うと、少し気分を害したらしいエンデは黙り込んで、また作業にとりかかった。ザゼリは目をこする。
「それにしても、レミオならわかるけど、エンデがへまをするって珍しいね?」
「半分はわたしのせいだもの、つまづいたから・・・」
床に座り込んでほつれた網目を直していたレミオが申し訳なさそうに言う。キオはつっこまずにはいられなかった。
「いや、お前、半分って。謙虚さ少しは学べ」
つっこんでしまってから、どうして自分は声を出すという面倒な動作をしてしまったのだろうとぼんやり考える。
ザゼリが思い出し笑いで噴き出した。肩が小刻みに揺れる。エンデが真っ赤になったのが首越しに伝わった。熱い。
「あんま笑ってやんなよ」
小さな声でキオは言う。
「だってさ、思わないじゃない、綱の網目の中にすっぽり、狙ったみたいに挟まるとかありえないだろ?いやああれは可愛かった。そして面白かった」
元々緩くなっていた網目の間に挟まったのはエンデだ。こけそうになったレミオの服を掴み、傍にあった綱をとっさに掴んだ。きちんと巻かれていた綱が一気にたるんで、二人してよろめいた。しかもレミオも綱を引っ張った。多分穴を広げたのはレミオの腕だったと思う。そこから慌てて手を抜こうとして、その手はエンデにしたたかにぶつかり、エンデはよろけて肩からその穴に突っ込んだ。そのあとたくさんの綱が落ちてきて、レミオの体に巻き付いた。もがくから余計に辺に結び目ができて、二人をそこから助け出すのも一苦労だった。周りは大爆笑だ。顔が火照りそうになって、キオは何とかこらえた。ここはきっと、呆れかえった方が二人のためだ。二人の皮膚が硬い綱に擦られてあちこち擦り向けていたのに少し胸が痛んだ気もしたが、ザゼリが自分の代わりに顔を真っ赤にして焦っていたので自分はもう気にしないことにした。
「しかもレミオはレミオでまるで蓑虫みたいな恰好なんだもんな。まったくほんとに。あんなのもう二度と見れない気がする」
ザゼリはまだ笑っている。そしてふと気がついた。
「エンデ、指の皮剥けてる。無理すんなよ」
「いいの。終わらないんだもの」
「血でてるじゃん。とりあえず消毒しろって。ここの物大して綺麗じゃないんだぜ」
「いいんだってば」
エンデの声は普段通りだ。淡々と静かで、抑揚すらない。けれど、言葉遣いがなんとなく違う気がした。どこがどう違うだなんて、キオには説明できない。ただ、声を出すことがためらわれる。不思議だ。
ザゼリは肩をすくめた。ただでさえ狭い樽の上に自分も腰かける。キオは意地でも場所を譲らなかった。なんとなく負けな気がしたからだ。結局少しずれたのはエンデだ。エンデが振り返って少し睨んできた気がした。ほんの少し心が跳ねた。びっくりしたのだ。エンデが感情を高ぶらせるなんて、めったにないことだ。いや、ほぼないことだ。
ザゼリはそのままただエンデの手元を眺めていた。何をするでもない。エンデも黙々と、先刻教えられた通りにほどけた五本の細い糸を固く編んでいく。
とても穏やかだ。肩に触れるザゼリの体温。背中に触れているエンデ。なんとなくキオの心は穏やかだった。こういう時間はなぜか嫌いじゃなかった。なんとなく、むずかゆくなってくる。けれど絶対に意地でもどいてなんかやらない。このままの風が好きだ。
ふと、キオは一人だけじべたにしゃがみこんで綱を編んでいるレミオを見やった。いつもならうんうん唸りながら作業をしているのに、先刻までそうだったのに、レミオは全く声を発しない。首が酷く曲がっている。流れた髪で顔は見えなかった。レミオにしては珍しく、空気を読んでいるんだろうかと思った。けれど、それにしても不自然に静かすぎる気がした。見なければ気づかないほどに空気に溶け込んでいる違和感。とはいえキオには関係ない。どうでもいいのだ。どうせレミオは何も考えちゃいないし、どうせすぐに忘れる。自分と違って、心に浮かんだことは染みだすように空気に溶けて消えていくのだ。構ってやろうとは思わない。構うと楽しいのはザゼリの方だからだ。それにエンデが付け加えられるとなお面白い。
顔にザゼリのおくれ毛がかぶさって来た。なんとなくキオはそれを指に巻き付けいじる。ザゼリがキオの方に顔を向けてきょとん、とした。とても可愛い表情だと思う。年上だけど。
「どうした?」
「別に?」
ザゼリはくすり、と笑った。今度はキオの手元を眺める。やがて目を閉じて顎を空に向けた。気持ち良さそうに風の匂いを嗅いでいる。
「お前さぁ、髪だけは綺麗だよな、いっちょ前に」
キオが言うと、ザゼリはのんびりした声で笑った。
「なんだよいっちょまえって。ひでえなあ」
綺麗だな、と思う。キオはエンデの背中にもたれかかった。エンデは何も言わない。そのまま支えてくれている。
キオはザゼリの金髪の束を空に向かってすかした。明るい。とても薄くて明るいそれは、心をなんとなく晴らしてくれる。キオは髪を手から離すと、ふう、と息をついて空を仰ぎ、自分も目を閉じた。
明るい。
自分を包む日の光も、この世の光も、自分を照らしてくれる。頬がぽかぽかと暖かくなる。いつか心臓が光の熱で焼かれればいいと思った。焼け焦げればいい。この日々が続くなら、きっと耐えられる。いつかもし、ヘラクレイトスの掟が自分達を阻みそうになるなら、この心臓ごと、あいつらを焼き焦がしてやる。
キオはとても満足していた。レミオに感謝してやってもいい。けれど絶対に、意地でも口には出してやらない。
PR
この記事にコメントする
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(10/08)
(10/07)
(09/24)
(09/24)
(09/10)
(08/11)
(08/11)
(08/11)
(08/10)
(07/27)
最新トラックバック
ブログ内検索
最古記事
(07/19)
(07/20)
(07/20)
(07/27)
(08/10)
(08/11)
(08/11)
(08/11)
(09/10)
(09/24)
P R