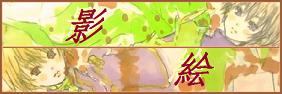自作小説「水の車輪」の原稿置き場です。 ※未熟ではありますが著作権を放棄しておりません。著作権に関わる行為は固くお断り致します。どうぞよろしくお願い致します。
[1]
[2]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
『その赤子は生まれた瞬間より其れと分かるであろう』
それは、何世紀を経て伝えられた予言であった。
人々の間で語り継がれる双子の星を統べる者・・・【双神伝説】によりその運命を約束された王の到来。
権力拡大を狙うヘラクレイトス家に生まれたその赤子は、生まれたばかりだというのに左目の目尻に二つの黒子を有していた。
彼らはこの赤子こそ王であると考えるも、同日エリュイトス家でもまた同様の黒子を有した赤子が誕生してしまう。
それだけに終わらず翌日には更にもう一人、マジュ家に同様の赤子が生まれた。
人々の混乱と三家の争いが激化していく中で、運命の子供たちは大人たちの思惑の外、少しずつ絆を深めていく。
“もう一人”の存在を知ることもなく・・・
同じ二つの黒子を有したもう一人の少年、ドュマとの出会いが、彼らの関係を、未来を、少しずつ侵食していく・・・
『人の忘れ去りし幻の都 オケアノスに幸あれ
人の住まいし熱の地ガイアよ 永久に不滅であれ』
『この世の全ての事象は 彼らにとればただの夢の一時でしかない』
こちらはオリジナル小説「水の車輪」の本文を保管するためのブログになります。
現在「Ourselves」という小説を連載しているので、こちらの更新は亀ペースになるかもしれませんが頑張ります。詳しくは横のバナーよりサイトでご確認ください。
ブログタイトルは「水の双子座」という感じの英語になるようにしました。
サラ=ブライトマンさんのアルバム「エデン」に収録された「ネッラ・ファンタジア」を聴いているときに、この物語で言うオケアノスの映像がふわっと浮かんできて、そこから思いついた物語です。
物語は一見ドュマたちの生きる世界の話に思えますが実はこれは「ガイア」と呼ばれる『地上』でしかなく、本来は「オケアノス」と呼ばれるひとつの大きな世界の住人の短き夢のひとときの物語でしかありません。これ以上言うともうネタバレがひどいのでやめておきますが。
それからこのお話は、「主人公が一番最後に出てくる物語にするんだ!!」という欲望を満たした作品です(笑)たまにはそういうものも書きたくなるといいますか・・・ははは。
続きに主要人物についての簡単な説明です。
ちなみにこちらの動画がこの物語のイメージソングです。
それから以下の動画の一曲目もこの物語のイメージです。二曲目は別の「影絵」のイメージです。
PR
・・・つづきはこちら
前奏曲
茶という色はとても美しい。
土の色、木の色、鳥の色、
肌の色。髪の色。
愛しい人の、瞳の色。
白い大輪の花が咲き誇っている。ところどころに赤い実、紫の小さな粒。
木々の間を潜って湧き、小川に注ぐ冷たい水は、胸が空くように青い。
彼が通ると、鳥も、虫も、植物も、皆静かに彼に道を広げ、そして優しく彼のそばに絡みつく。
彼はとても愛されていた。この青い楽園の全ては彼のためにある。
彼を慈しみそっと守るためにある。
少しがさつく蔓の茎が、彼の耳に触れる。彼は穏やかに微笑んでそれを撫でた。
鼻歌でさえも、神というものが本当に存在するのならば、かくありきやと思わせるほどに、美しく安らかだ。
彼が肩に止まった白い鳥の尾を撫でていると、彼の目の前にそっと灰色の影が被さる。
彼はとても幸せそうに微笑んだ。
とても愛おしい人がそこにいる。困ったような顔で彼を見つめている。ダジエルダの茶色の瞳に、自分の葉っぱまみれの顔が映っているのを見て、彼はくすりと笑った。
この世界に住む彼らは人と呼ばれたが、つがいをもたなかった。
ここは肉体のない尊き物が、水の国では水の、風の国では風の力を借りて、形をなす。
彼らに営みは不要だった。ただ愛おしいものがそこにあるだけで幸せだったのだ。
「ダジエルダ。やっぱり来てくれたね」
彼はにっこりと微笑む。ダジエルダは少しだけムッとした。
「お願いですから、俺を呼ぶのはやめてくださいと何度も頼んでいるでしょう」
「それでも君は来てくれるじゃない。知っているよ。君はとても優しい人だから。だって、僕が愛している者なのだもの」
「オストロン」
水のようにつややかに流れる髪をなびかせながら虫や鳥達と戯れる人に、ダジエルダは困惑気味に呼びかけた。オストロンは首をかしげる。微笑んだまま。
「なあに?」
「やめてください。あなたは水の中でも最高位のお方だ。何故あなたのようなお方が俺のような卑しい身分のものにまで気を遣うことがあるだろう」
「君たちはみんなみんなそればかりだね」
オストロンは冷笑した。
「僕は僕のしたいようにしかしないつもりだ」
オストロンは白い兎をそっと腕に抱えてその背を優しく撫でる。
「それでも全ては僕に言う。お前が水の王となれと。これだけ勝手にしていても誰もが皆僕にそれを望む。ならば何も問題はない。僕はこれからも僕の幸せのために生きていくんだ。僕は今でも諦めてはいないんだよ、君を」
「だから、」
ダジエルダは心底疲れたように額に手を当てる。
「あなたの愛情が重たいのだと何度言えばあなたはわかってくださるのか」
「そんなこと言って」
オストロンは少しだけ気分を害したかのように右腕をさっと振り上げた。手の先で水の粒が渦をなし、見事な大角の牡鹿が震えたように現れる。牡鹿はオストロンの機嫌に恐れをなしたかのように森の奥へ逃げ出した。
「つまらないな」
オストロンは嘆息した。
「どんなに怒っても、嘆いても、ここで僕が作り出せるのは全て美しすぎる。誰のそれにも増して、美しすぎるんだ、何もかもが。つまらない」
「だからあなたが最高位なのでしょう?」
ダジエルダはようやくやわらかく笑う。
「そんなお方から目をかけていただけるなんて、俺は幸せ者です。土なのに」
オストロンは嫌そうに深くわざとらしく嘆息する。そうして兎を土に下ろした。兎はオストロンの爪先に鼻をすり寄せたあと、森の穴蔵へと駆けていく。
「君はいつだって僕が呼べば来てくれる。僕が呼ばなくても来てくれる。僕が君を求めている時はいつだって現れてくれる。それなのに、君は一言だって、僕に言葉を伝えてくれないんだね。こんなにも僕は君を愛しているのに。ここは僕の国なのに。そうだ、僕の国なのに!!」
オストロンは声を上げた。その勢いに、花に群がっていた白い蝶たちが一瞬高く空にふわりと舞い上がり、またふわふわと花のもとへ降りていく。
ダジエルダはふわりと微笑むと、オストロンの側へ歩み寄り、その頭をそっと撫でた。ダジエルダはオストロンよりも頭一つ背が高い。オストロンはムッとした。
「またそうやって子供扱いを」
「違うんですか?」
ダジエルダの優しく静かな声に、オストロンはそのまま何も言えなくなって、俯いた。ダジエルダはそっとオストロンの手を取って、本当に柔らかく笑いかける。オストロンが泣きたくなるくらい好きな笑顔だ。
「分かってください。俺は土だから、あなたに何も伝えてはいけないんです。だから、分かってください。俺はいつだって、正直ですよ」
ダジエルダはそのままその手を引いた。そっと風に背中を押されるように、オストロンも歩き出す。
白と青で彩られた石の噴水には、真っ白な月下美人が眠るように浮いていた。
「あなたはまるで、この花のような人だ」
ふと、ダジエルダがそんなことを言い出す。オストロンは顔をしかめた。
「ええ!?もっと他に例えようがあるでしょ、どうしてこの花なんだよ」
ダジエルダはきょとんとする。
「俺は、この花が一番美しいと思っているんですよ。あなたみたいだから。ほら、見てご覧。水に浮くこの花ほど綺麗なものを俺は知らない。あなたはこうやって、水の中で静かに息づいているのが一番美しいんだ」
ダジエルダは、きゅっとオストロンの手を握りしめる。
「あなたは先だって、土になりたいと言ったそうですね」
「それが?」
オストロンは刺のある声で答える。
「案の定しばらくこの廃墟に幽閉されるほどにはご立腹されたけれど?見てのとおりだよ」
「見てご覧なさい、この、水の中を、ほら、覗いてみて」
ダジエルダはオストロンの背をそっと押した。
「知ってるよ、今更言われなくてもここから何が見えるかくらい嫌というほど承知・・・」
「いいから見ろ!」
ダジエルダの声は悲痛だった。オストロンは渋々水面に目を移す。
世界の最果てにあるこの器に宿る水には、世界が臨める。水の国はこの世で最高位にある世界だった。この国の器からは、すべての下位の世界が見える。そう、物質界と呼ばれる最下の卑しい土地まで。
それでも、その『汚れ』にもまれなければ美しくなり得ない者たちは、下位世界に降り立ちその魂を磨かなければならない。戻ってくる頃には、受けた試練の分、彼らは一段と輝きを増し、身分を高める。
けれどたまに、実力以上の試練を受けようとして身を滅ぼし貶めるものも数多くいた。オストロンの目の端に、今やオケアノスでは有名どころになった人の苦しむ姿が引っ掛かる。
彼は火に包まれ、煤けて、もがいていた。またかよ、とオストロンは毒づきたくなる。
飽きるほどにも見慣れた顔だ。フォレスネッサ。火の国の寵児とまで歌われた美しい存在だったにもかかわらず、水の国の景色に心奪われ、『水になりたい』という無謀な、哀れな望みを未だ捨てきれないでいる。
もはやガイア、『物質界』に下りすぎた彼の魂は、とても水どころか火の国にも戻れないほどに落ちぶれてしまっていた。
ダジエルダは、フォレスネッサが嗚咽を漏らしながら髪をかきむしるさまを静かな目で見つめていた。ほんの少しだけ、オストロンの手を握る力が強くなる。
「彼だけでない。水になりたいと願い身を焦がす者がどれだけいるだろうか。これだけの者たちが、高位に憧れ危険を冒してまで物質界に下る。だというのに、どうしてあなたはわざわざ俺のような卑しい土の身分になりたいなどと本気で思うのか」
ダジエルダは、耐えるように目を固くつむった。オストロンは何かむしゃくしゃして、その手を振り払い、素知らぬ顔で噴水の淵に片足を立てて座り込んでもう一度水底を眺めた。
どうしようもなく毒々しい思いが体を駆け巡っていく。愛する者への欲望のためなら、どれだけでも汚くなれる。それなのに人は皆自分を誰よりも何よりも、素晴らしいと、美しいと、顔すら上げることもかなわず震えて頭を垂れる。
オストロンはぽつり、と呟いた。
「かわいそうに」
その瞬間、声が届いたかのように虚ろなフォレスネッサの淡紅色の瞳がオストロンの青い眼を捉える。オストロンはありったけの蔑みを浮かべて微笑み返した。けれどフォレスネッサは惚けたようにオストロンをあどけない顔で見つめている。
「ふーん・・・」
オストロンは片眉を少しだけ釣り上げた。
ダジエルダはオストロンの瞳をまっすぐに見据える。そうして、ふっと、気が抜けたように悲しげに笑った。
「長居しすぎました。また・・・来ないこともないかもしれません」
「お前は来るよ。僕が生きている限り、きっとお前は来続けるんだ。・・・僕のもとに」
ダジエルダは答えなかった。土埃が舞って、ダジエルダの影だけがそこに取り残される。やがてそれも、空気に溶けて消えてしまった。
オストロンは冷めた静かな表情で虚ろに自分の胸元の服を握りしめる。
「ああ・・・本当に・・・やってられない。何も変わらない」
オストロンはもう一度水面を頬杖を付いてのぞき込んだ。フォレスネッサは疲れきったようにぺたん、と座り込んで、船をこいでいた。思わずオストロンは吹き出さずに入られなかった。こういう馬鹿な辺りが、彼をなかなか浄化させてやれていないのかもしれない。
「やあ、フォレスネッサ。ガイアはどうだい?堕ちるところまで堕ちた気分は?」
フォレスネッサは虚ろな眼をそっと上向かせただけだった。
『水を・・・ください』
ほろほろと、その目からなみだがこぼれおちる。
「あーあ、馬鹿だねえ。こんなことしなければ、君は火の国の期待の星だったんだから、僕みたいに水の幻影を作り出すことなんて朝飯前だったろうにね。ほんっとに馬鹿だねえ」
『それじゃ意味がない』
ふっと、フォレスネッサの瞳に火が灯る。
『そんなまやかしでは意味がないんだ。僕は、どうしても水になりたかった。あなたを、あなたがたを、美しいと思った。火が好きだった。けれど水がもっと好きになった。一目惚れだったんだ。僕は苦しい。今でも苦しくて、何度助けてくれと醜く叫んだかわからない。何度後悔して何度己を哀れんだかも覚えていない。それでも僕は、僕は、後悔してしまうことはない!』
「あっそう」
オストロンは冷えた声で言った。そうしてにやりと口角を釣り上げる。
「それだけ気力が湧いてきたなら、また大丈夫そうだね、せいぜい頑張りなよ」
フォレスネッサはしばらく黙っていた。そうして、随分と時間が経った頃、ふわり、と笑った。
オストロンは軽い衝撃を受けて、手から顔を上げ、フォレスネッサのあどけない顔をまじまじと見つめた。
『頑張る』
フォレスネッサは穏やかに微笑んだ。そうしてようやく腰を上げる。
その穏やかさは、ダジエルダのそれとも全く違っていた。ダジエルダしかまともに見たことがなかったから、笑顔に違いがあるということも、オストロンは気づけていなかった。
(なんだか、惹かれるな、この子・・・)
オストロンは静かな気持ちでフォレスネッサの薄赤の頭を眺める。
(僕に似ているからなのか。それとも、本当は僕のなりたい姿だったのか・・・)
「君って本当に不細工だね」
オストロンがそういうと、フォレスネッサは心底傷ついたように顔を上げた。その表情にオストロンはぶっと吹き出す。
「あはは、僕のダジエルダとは大違いだ・・・!あはは!!すっごく不細工・・・はは」
可愛いな、と思った。憐れすぎて逆に愛おしい。
オストロンはにやりと笑った。本当にただの気まぐれだ。急な思いつきで、行きあたりばったりだった。けれど、もう、オストロンは限界だった。
「ねえ、フォレスネッサ」
僕の望みを、叶えてくれるかな?
「助けて、あげようか?」
水面に、林檎の花びらがふわりと舞って、落ちた。
茶という色はとても美しい。
土の色、木の色、鳥の色、
肌の色。髪の色。
愛しい人の、瞳の色。
白い大輪の花が咲き誇っている。ところどころに赤い実、紫の小さな粒。
木々の間を潜って湧き、小川に注ぐ冷たい水は、胸が空くように青い。
彼が通ると、鳥も、虫も、植物も、皆静かに彼に道を広げ、そして優しく彼のそばに絡みつく。
彼はとても愛されていた。この青い楽園の全ては彼のためにある。
彼を慈しみそっと守るためにある。
少しがさつく蔓の茎が、彼の耳に触れる。彼は穏やかに微笑んでそれを撫でた。
鼻歌でさえも、神というものが本当に存在するのならば、かくありきやと思わせるほどに、美しく安らかだ。
彼が肩に止まった白い鳥の尾を撫でていると、彼の目の前にそっと灰色の影が被さる。
彼はとても幸せそうに微笑んだ。
とても愛おしい人がそこにいる。困ったような顔で彼を見つめている。ダジエルダの茶色の瞳に、自分の葉っぱまみれの顔が映っているのを見て、彼はくすりと笑った。
この世界に住む彼らは人と呼ばれたが、つがいをもたなかった。
ここは肉体のない尊き物が、水の国では水の、風の国では風の力を借りて、形をなす。
彼らに営みは不要だった。ただ愛おしいものがそこにあるだけで幸せだったのだ。
「ダジエルダ。やっぱり来てくれたね」
彼はにっこりと微笑む。ダジエルダは少しだけムッとした。
「お願いですから、俺を呼ぶのはやめてくださいと何度も頼んでいるでしょう」
「それでも君は来てくれるじゃない。知っているよ。君はとても優しい人だから。だって、僕が愛している者なのだもの」
「オストロン」
水のようにつややかに流れる髪をなびかせながら虫や鳥達と戯れる人に、ダジエルダは困惑気味に呼びかけた。オストロンは首をかしげる。微笑んだまま。
「なあに?」
「やめてください。あなたは水の中でも最高位のお方だ。何故あなたのようなお方が俺のような卑しい身分のものにまで気を遣うことがあるだろう」
「君たちはみんなみんなそればかりだね」
オストロンは冷笑した。
「僕は僕のしたいようにしかしないつもりだ」
オストロンは白い兎をそっと腕に抱えてその背を優しく撫でる。
「それでも全ては僕に言う。お前が水の王となれと。これだけ勝手にしていても誰もが皆僕にそれを望む。ならば何も問題はない。僕はこれからも僕の幸せのために生きていくんだ。僕は今でも諦めてはいないんだよ、君を」
「だから、」
ダジエルダは心底疲れたように額に手を当てる。
「あなたの愛情が重たいのだと何度言えばあなたはわかってくださるのか」
「そんなこと言って」
オストロンは少しだけ気分を害したかのように右腕をさっと振り上げた。手の先で水の粒が渦をなし、見事な大角の牡鹿が震えたように現れる。牡鹿はオストロンの機嫌に恐れをなしたかのように森の奥へ逃げ出した。
「つまらないな」
オストロンは嘆息した。
「どんなに怒っても、嘆いても、ここで僕が作り出せるのは全て美しすぎる。誰のそれにも増して、美しすぎるんだ、何もかもが。つまらない」
「だからあなたが最高位なのでしょう?」
ダジエルダはようやくやわらかく笑う。
「そんなお方から目をかけていただけるなんて、俺は幸せ者です。土なのに」
オストロンは嫌そうに深くわざとらしく嘆息する。そうして兎を土に下ろした。兎はオストロンの爪先に鼻をすり寄せたあと、森の穴蔵へと駆けていく。
「君はいつだって僕が呼べば来てくれる。僕が呼ばなくても来てくれる。僕が君を求めている時はいつだって現れてくれる。それなのに、君は一言だって、僕に言葉を伝えてくれないんだね。こんなにも僕は君を愛しているのに。ここは僕の国なのに。そうだ、僕の国なのに!!」
オストロンは声を上げた。その勢いに、花に群がっていた白い蝶たちが一瞬高く空にふわりと舞い上がり、またふわふわと花のもとへ降りていく。
ダジエルダはふわりと微笑むと、オストロンの側へ歩み寄り、その頭をそっと撫でた。ダジエルダはオストロンよりも頭一つ背が高い。オストロンはムッとした。
「またそうやって子供扱いを」
「違うんですか?」
ダジエルダの優しく静かな声に、オストロンはそのまま何も言えなくなって、俯いた。ダジエルダはそっとオストロンの手を取って、本当に柔らかく笑いかける。オストロンが泣きたくなるくらい好きな笑顔だ。
「分かってください。俺は土だから、あなたに何も伝えてはいけないんです。だから、分かってください。俺はいつだって、正直ですよ」
ダジエルダはそのままその手を引いた。そっと風に背中を押されるように、オストロンも歩き出す。
白と青で彩られた石の噴水には、真っ白な月下美人が眠るように浮いていた。
「あなたはまるで、この花のような人だ」
ふと、ダジエルダがそんなことを言い出す。オストロンは顔をしかめた。
「ええ!?もっと他に例えようがあるでしょ、どうしてこの花なんだよ」
ダジエルダはきょとんとする。
「俺は、この花が一番美しいと思っているんですよ。あなたみたいだから。ほら、見てご覧。水に浮くこの花ほど綺麗なものを俺は知らない。あなたはこうやって、水の中で静かに息づいているのが一番美しいんだ」
ダジエルダは、きゅっとオストロンの手を握りしめる。
「あなたは先だって、土になりたいと言ったそうですね」
「それが?」
オストロンは刺のある声で答える。
「案の定しばらくこの廃墟に幽閉されるほどにはご立腹されたけれど?見てのとおりだよ」
「見てご覧なさい、この、水の中を、ほら、覗いてみて」
ダジエルダはオストロンの背をそっと押した。
「知ってるよ、今更言われなくてもここから何が見えるかくらい嫌というほど承知・・・」
「いいから見ろ!」
ダジエルダの声は悲痛だった。オストロンは渋々水面に目を移す。
世界の最果てにあるこの器に宿る水には、世界が臨める。水の国はこの世で最高位にある世界だった。この国の器からは、すべての下位の世界が見える。そう、物質界と呼ばれる最下の卑しい土地まで。
それでも、その『汚れ』にもまれなければ美しくなり得ない者たちは、下位世界に降り立ちその魂を磨かなければならない。戻ってくる頃には、受けた試練の分、彼らは一段と輝きを増し、身分を高める。
けれどたまに、実力以上の試練を受けようとして身を滅ぼし貶めるものも数多くいた。オストロンの目の端に、今やオケアノスでは有名どころになった人の苦しむ姿が引っ掛かる。
彼は火に包まれ、煤けて、もがいていた。またかよ、とオストロンは毒づきたくなる。
飽きるほどにも見慣れた顔だ。フォレスネッサ。火の国の寵児とまで歌われた美しい存在だったにもかかわらず、水の国の景色に心奪われ、『水になりたい』という無謀な、哀れな望みを未だ捨てきれないでいる。
もはやガイア、『物質界』に下りすぎた彼の魂は、とても水どころか火の国にも戻れないほどに落ちぶれてしまっていた。
ダジエルダは、フォレスネッサが嗚咽を漏らしながら髪をかきむしるさまを静かな目で見つめていた。ほんの少しだけ、オストロンの手を握る力が強くなる。
「彼だけでない。水になりたいと願い身を焦がす者がどれだけいるだろうか。これだけの者たちが、高位に憧れ危険を冒してまで物質界に下る。だというのに、どうしてあなたはわざわざ俺のような卑しい土の身分になりたいなどと本気で思うのか」
ダジエルダは、耐えるように目を固くつむった。オストロンは何かむしゃくしゃして、その手を振り払い、素知らぬ顔で噴水の淵に片足を立てて座り込んでもう一度水底を眺めた。
どうしようもなく毒々しい思いが体を駆け巡っていく。愛する者への欲望のためなら、どれだけでも汚くなれる。それなのに人は皆自分を誰よりも何よりも、素晴らしいと、美しいと、顔すら上げることもかなわず震えて頭を垂れる。
オストロンはぽつり、と呟いた。
「かわいそうに」
その瞬間、声が届いたかのように虚ろなフォレスネッサの淡紅色の瞳がオストロンの青い眼を捉える。オストロンはありったけの蔑みを浮かべて微笑み返した。けれどフォレスネッサは惚けたようにオストロンをあどけない顔で見つめている。
「ふーん・・・」
オストロンは片眉を少しだけ釣り上げた。
ダジエルダはオストロンの瞳をまっすぐに見据える。そうして、ふっと、気が抜けたように悲しげに笑った。
「長居しすぎました。また・・・来ないこともないかもしれません」
「お前は来るよ。僕が生きている限り、きっとお前は来続けるんだ。・・・僕のもとに」
ダジエルダは答えなかった。土埃が舞って、ダジエルダの影だけがそこに取り残される。やがてそれも、空気に溶けて消えてしまった。
オストロンは冷めた静かな表情で虚ろに自分の胸元の服を握りしめる。
「ああ・・・本当に・・・やってられない。何も変わらない」
オストロンはもう一度水面を頬杖を付いてのぞき込んだ。フォレスネッサは疲れきったようにぺたん、と座り込んで、船をこいでいた。思わずオストロンは吹き出さずに入られなかった。こういう馬鹿な辺りが、彼をなかなか浄化させてやれていないのかもしれない。
「やあ、フォレスネッサ。ガイアはどうだい?堕ちるところまで堕ちた気分は?」
フォレスネッサは虚ろな眼をそっと上向かせただけだった。
『水を・・・ください』
ほろほろと、その目からなみだがこぼれおちる。
「あーあ、馬鹿だねえ。こんなことしなければ、君は火の国の期待の星だったんだから、僕みたいに水の幻影を作り出すことなんて朝飯前だったろうにね。ほんっとに馬鹿だねえ」
『それじゃ意味がない』
ふっと、フォレスネッサの瞳に火が灯る。
『そんなまやかしでは意味がないんだ。僕は、どうしても水になりたかった。あなたを、あなたがたを、美しいと思った。火が好きだった。けれど水がもっと好きになった。一目惚れだったんだ。僕は苦しい。今でも苦しくて、何度助けてくれと醜く叫んだかわからない。何度後悔して何度己を哀れんだかも覚えていない。それでも僕は、僕は、後悔してしまうことはない!』
「あっそう」
オストロンは冷えた声で言った。そうしてにやりと口角を釣り上げる。
「それだけ気力が湧いてきたなら、また大丈夫そうだね、せいぜい頑張りなよ」
フォレスネッサはしばらく黙っていた。そうして、随分と時間が経った頃、ふわり、と笑った。
オストロンは軽い衝撃を受けて、手から顔を上げ、フォレスネッサのあどけない顔をまじまじと見つめた。
『頑張る』
フォレスネッサは穏やかに微笑んだ。そうしてようやく腰を上げる。
その穏やかさは、ダジエルダのそれとも全く違っていた。ダジエルダしかまともに見たことがなかったから、笑顔に違いがあるということも、オストロンは気づけていなかった。
(なんだか、惹かれるな、この子・・・)
オストロンは静かな気持ちでフォレスネッサの薄赤の頭を眺める。
(僕に似ているからなのか。それとも、本当は僕のなりたい姿だったのか・・・)
「君って本当に不細工だね」
オストロンがそういうと、フォレスネッサは心底傷ついたように顔を上げた。その表情にオストロンはぶっと吹き出す。
「あはは、僕のダジエルダとは大違いだ・・・!あはは!!すっごく不細工・・・はは」
可愛いな、と思った。憐れすぎて逆に愛おしい。
オストロンはにやりと笑った。本当にただの気まぐれだ。急な思いつきで、行きあたりばったりだった。けれど、もう、オストロンは限界だった。
「ねえ、フォレスネッサ」
僕の望みを、叶えてくれるかな?
「助けて、あげようか?」
水面に、林檎の花びらがふわりと舞って、落ちた。
誰かの慟哭
おお、神よ!
どうか怒りを鎮めたまえ
我々は卑しい身分なれど
このままでは食ってはいけぬ
生きてはゆけぬ
どうか我らを救いたまえ
病を鎮めたまえ
どうか我らの王の御子が
願わくば我らの子らが
無事に生まれんことを
我らが飢えることのなきよう
どうぞお守りたまえ
妻が 我が子が
我が父母が
生きて行けるのであれば
我はどんな苦行にも耐えよう
どうか我の命と引換えに
どうか救いをもたらしたまえ
とある言い伝え
ほらお前
空をご覧
あそこに二つ並んだ金の星があるだろう
あれはその昔 この世界を平定なさった二人の勇者の魂なのだよ
どうしてお空にいるの?
それは神様から愛されてしまったからだよ
神様は お二人をそれはそれはお気に召して
老いて醜く死んでいくのを恐れたのだよ
だから空に閉じ込めなさった
彼らは今も我らを見守っているんだよ
ある記録
拾一月参日
山羊の刻 尋問開始
被告は神話の新解釈と称して、二人の英雄神ルフェラとサフィアの存在を否定
独自に改造したという望遠鏡での観察の結果、ルフェラとサフィアは我々が大御神ティタンと呼ぶところのものの周りを円形の起動に沿って回るただの球体だと称している。
被告はティタンをただの炭素と硫黄の塊だと述べている。
同日射手の刻 裁判長は被告の有罪判決を下した。被告の罪状は立法第百三十九条、反宗教説此れ死罪に相当すべし。
我、些かの不安を覚えるも、この考えは墓に持って逝く所存である。
我らが神々 ただの我々と同じ物質であるべからず。
望遠鏡の販売及び開発を禁ずる法律が制定さるる。レオラ大学天文学部某教授、上記被告に関わりがあったとして同様に処罰されたり。
とある若者の手記
今日、おれはとんでもないものを見つけてしまった。
大昔前の予言の書ってやつだ。
誰かにしゃべってしまいたいがあいにく下手な話をして処罰なんぞされたくないんで、おれは涙を偲んでここに落書きをする。
今でこそある程度の飯と学と金は確保できる贅沢な時代だが、大昔はそりゃあ混沌の時代で、まともにおまんま食えるだけでもありがたかったらしい。
それを今の統制された治世の土台を作った方々が神話で有名どころの英雄、大御神ティタンの隠し子、双子のルフェラ、サフィア様だ。それにしてもすげえな。今でこそそうでもないが、おれの餓鬼の頃は双子だなんて獣腹と呼ばれて忌み嫌われていたし、昔はもっと酷かったんじゃねえのか。
とにかく、この予言はおれは今まで知らなかった。ということはそれなりに隠されてきた伝説ってことだ。ばあちゃんに聞かされて馴染みのあるほら話がまさか実際に文書として残っているなんて思ってもみなかったぜ!だけどおれは絶対に口外しねえ。せっかく都に出てきたってのに田舎に送り返されたらたまったもんじゃねえ。それどころか牢屋行きもありうるな。
まさか双子英雄の再来話が実際の予言だったなんて思いもしなかったぜ。ああ、これは本当に本当のことなんだろうな?おれの目の黒いうちに現れてくれねえかなあその勇者さんとやら。せっかく見つけた真実なんだ。この目で見てみてえってもんだ。
ムーサの預言碑
我 大地の神ダジエルダより詔を受けたりし
遠き先の世 我らが英雄神の末裔より 彼らが転生現るるなり
彼らを神に献上すべし さすれば未来永劫人の世を守られたりし
双子神の伝説 末代まで語り継ぐべし
ダジエルダ 我に拾三の言葉を与うる
一に 未来永劫祈りを捧げるべし
二に 人は皆神の創りたもうたものである 親を敬え 妻を敬え 子を敬え
三に 血は全て尊き恵みである 此れ無駄な殺生は控えるべし
四に
・・・・・
『其の赤子
生まれ落つ時しより
彼の者である』
序章 終
おお、神よ!
どうか怒りを鎮めたまえ
我々は卑しい身分なれど
このままでは食ってはいけぬ
生きてはゆけぬ
どうか我らを救いたまえ
病を鎮めたまえ
どうか我らの王の御子が
願わくば我らの子らが
無事に生まれんことを
我らが飢えることのなきよう
どうぞお守りたまえ
妻が 我が子が
我が父母が
生きて行けるのであれば
我はどんな苦行にも耐えよう
どうか我の命と引換えに
どうか救いをもたらしたまえ
とある言い伝え
ほらお前
空をご覧
あそこに二つ並んだ金の星があるだろう
あれはその昔 この世界を平定なさった二人の勇者の魂なのだよ
どうしてお空にいるの?
それは神様から愛されてしまったからだよ
神様は お二人をそれはそれはお気に召して
老いて醜く死んでいくのを恐れたのだよ
だから空に閉じ込めなさった
彼らは今も我らを見守っているんだよ
ある記録
拾一月参日
山羊の刻 尋問開始
被告は神話の新解釈と称して、二人の英雄神ルフェラとサフィアの存在を否定
独自に改造したという望遠鏡での観察の結果、ルフェラとサフィアは我々が大御神ティタンと呼ぶところのものの周りを円形の起動に沿って回るただの球体だと称している。
被告はティタンをただの炭素と硫黄の塊だと述べている。
同日射手の刻 裁判長は被告の有罪判決を下した。被告の罪状は立法第百三十九条、反宗教説此れ死罪に相当すべし。
我、些かの不安を覚えるも、この考えは墓に持って逝く所存である。
我らが神々 ただの我々と同じ物質であるべからず。
望遠鏡の販売及び開発を禁ずる法律が制定さるる。レオラ大学天文学部某教授、上記被告に関わりがあったとして同様に処罰されたり。
とある若者の手記
今日、おれはとんでもないものを見つけてしまった。
大昔前の予言の書ってやつだ。
誰かにしゃべってしまいたいがあいにく下手な話をして処罰なんぞされたくないんで、おれは涙を偲んでここに落書きをする。
今でこそある程度の飯と学と金は確保できる贅沢な時代だが、大昔はそりゃあ混沌の時代で、まともにおまんま食えるだけでもありがたかったらしい。
それを今の統制された治世の土台を作った方々が神話で有名どころの英雄、大御神ティタンの隠し子、双子のルフェラ、サフィア様だ。それにしてもすげえな。今でこそそうでもないが、おれの餓鬼の頃は双子だなんて獣腹と呼ばれて忌み嫌われていたし、昔はもっと酷かったんじゃねえのか。
とにかく、この予言はおれは今まで知らなかった。ということはそれなりに隠されてきた伝説ってことだ。ばあちゃんに聞かされて馴染みのあるほら話がまさか実際に文書として残っているなんて思ってもみなかったぜ!だけどおれは絶対に口外しねえ。せっかく都に出てきたってのに田舎に送り返されたらたまったもんじゃねえ。それどころか牢屋行きもありうるな。
まさか双子英雄の再来話が実際の予言だったなんて思いもしなかったぜ。ああ、これは本当に本当のことなんだろうな?おれの目の黒いうちに現れてくれねえかなあその勇者さんとやら。せっかく見つけた真実なんだ。この目で見てみてえってもんだ。
ムーサの預言碑
我 大地の神ダジエルダより詔を受けたりし
遠き先の世 我らが英雄神の末裔より 彼らが転生現るるなり
彼らを神に献上すべし さすれば未来永劫人の世を守られたりし
双子神の伝説 末代まで語り継ぐべし
ダジエルダ 我に拾三の言葉を与うる
一に 未来永劫祈りを捧げるべし
二に 人は皆神の創りたもうたものである 親を敬え 妻を敬え 子を敬え
三に 血は全て尊き恵みである 此れ無駄な殺生は控えるべし
四に
・・・・・
『其の赤子
生まれ落つ時しより
彼の者である』
序章 終
第一章 轍
一、
ヘラクレイトス家には、宝がある。
それは【人】であったが、同時に【神の器】と同義であった。
その子供が生まれたことで、ヘラクレイトス家は新興貴族として名を馳せるようになる。
当主の愛人から生まれたその子のために、ヘラクレイトスという一介の中堅階級の一族は、大見得きって出歩けるようになった。
人々はその子供を出した、ヘラクレイトス家現当主、ベリエルザに頭を垂れる。
歯の浮くような世辞を言い、かしづく。
子供は愛人の子であったけれど、まるで元から身分の高貴なものであったかのように扱われた。
彼には長兄がいたが、長兄もまた、彼に恐れおののき、身を引いた。彼が時期ヘラクレイトス家長になることは、目に見えて明らかであった。
母親は、ヘラクレイトス家お抱えの、商家の娘であり、同様に国で有数の大企業となる。
彼が、予言の子である【かもしれない】こと、ほんの少し、残りの【予言の子】の中では頭脳も優れていたこと、ただそれだけの理由で、人は彼こそが予言の子だと言い切るようになった。
人当たりのいいその少年は、酷く心をくすませていく。
誰も、そのことに気づかない。
少年もまた、気づいて欲しいとも、思わない。
「決め手にかけるな」
ベリエルザは苛々しながら忙しなく室内を歩き回った。
その様子を、部屋の壁にもたれてにこにこと眺めている少年がいる。
少年は母親似でひどく愛らしく、桂皮色の髪からは匂い立つような美しさが際立つ。
父であるベリエルザは決して不細工ではなかったが、少年と並ぶとあまりにお粗末に見えた。
そして少年もまた、父親をひどく馬鹿にしている。
「お前、本当に、何も知らないのか?覚えはないのか?」
少年はしょんぼりとしたように俯く。
「僕が不甲斐ないばかりに・・・申し訳ありません」
「お前は先の王の行幸の際、王の目の前で風車台の羽を回してみせたではないか」
「あれは偶然です、父上。現に、ほら」
少年は【その時】と同じように片手を宙に伸ばす。そして真剣な顔つきになる。
ややあって、落胆したように嘆息しながら首を振って、少年は手を下ろした。
「僕は今、父上の机に乗っている紙束を動かそうとしてみたんです。けれど、父上、一寸たりとも動いていない・・・父上、僕だって、あの時は、僕にこんな素晴らしい力があったのかと、踊りだしたくなるような気持ちでした。もしそんな素晴らしい力があるなら、僕はもっともっと、父上のお役に立てます!けれど・・・」
少年はうなだれる。
「何度やっても、どんなに神経を集中させても、僕にはできないのです。どうしたって、風は僕の言うことを聞いてくれない。やはり、きっと、ただの偶然だったのですよ、父上。僕だって・・・僕だって・・・欲しかった。父上の役に・・・」
ベリエルザは舌打ちしながら息を吐くと、少年の桂皮色の髪をぐしゃり、と撫でた。
「もういい。お前を追い詰めるつもりなどないのだ。何もできないのなら仕方がない。だが・・・どうにも解せん。お前は確かに予言の子のはずなのに、これといって特出するものは何もないではないか」
その言葉に、少年が心の中で苛立ちを滾らせたことに、男は気付かなかった。
「あれはまるで奇跡のようであったから、もしや・・・お前にその能力はなくとも、他の二人にはあるのではないか?人を超越した神の力を、お前以外の者がよもや持ってはいまいな?」
「そんなことはないと思います、父上」
少年は、くしゃり、と笑った。
「ご存知のとおり、エリュイトス家のご子女はあのような馬鹿ですし、片やマジュ家の彼女は彼女でひどく気難しく、どちらも己の制御能力に欠けています。もしも力があるのなら、たとえ彼らの家の者が隠そうとしようとぼろが出るはずですよ。まあもし・・・僕に力があるのなら、僕は父上とこのヘラクレイトス家のために、決して余所にその力を見せるようなへまもしません」
「ふん」
ベリエルザは苦笑した。
「お前もよくよく口が悪いな。両家の御子女のことをそんなふうに言える強者はお前くらいのものだろう。あの二家はうちと違って古株の貴族なのだからな」
「じきにうちが勝ちますよ」
少年はにこり、と笑った。
ベリエルザは満足げに微笑する。
父の書斎を出て、自室に戻る。
身の回りの世話をするメイドを皆出払わせ、少年は窓の外を眺めた。不意に、苛立つように唇を噛み締め、視線の先をひどく睨みつける。そこに何かがあったわけではない。強いて言うならば、白い鳩が飛んでいた。けれど、ただそれだけのことだ。少年が苛立ったのは何も知らぬ鳩のせいなどではない。
少年は踵を返し、カフスのボタンを緩める。クローゼットを開け、堅苦しい上着を脱いで、奥の方から簡素な青染の服を引っ張り出した。ブーツを脱ぎ、靴下さえも放り投げる。
母方の祖母が編んでくれた麻糸の帽子を深く被り、少年は扉に鍵をかけた。もちろん扉の外に、【僕は疲れているのでゆっくり眠りたい。何があっても起こすな】という張り紙は抜かりなく貼り終えている。昨日夜更けまで勉強をしていたことは家人なら誰でも知っているはずだから、この言い訳もそうそう怪しまれないだろう。
少年は身軽に窓の淵へ飛び乗ると、そのまま窓の外から飛び降りた。
少年がいる部屋は屋敷の三階だ。
それでも少年が無事に着陸できたのは、異常成長した庭の草木が少年の体をそっと受け止め、再びゆっくりと枯れていったからに他ならない。
少年は右手をくるくると回した。異常繁殖した植物たちの残骸は、昼間の太陽の下では隠されてしまうほどの、しかし鋭い光の粒に包まれて、ただの灰になる。
少年はそのまま足音を立てないように、塀の隙間から外へと脱出した。
そうしてようやく少年が感情を爆発させたのは、かもめが呑気に飛び回る船着場だった。
「よう、坊主。なんだ?若いくせに眉間にしわが酔ってるじゃねえの」
「ザゼリ」
少年は無表情でその名を呼ぶと、不意ににやり、とした。
「一発殴ってもいい?」
「はぁ!?」
金髪に碧眼、容姿的には申し分ないはずなのにどこか阿呆面で残念なその青年は、汗まみれの白い上着を暑そうにはためかせながら、そばかすだらけの鼻の頭を掻いてムッとした。
「ちょい待て。おれが何をしたよ」
「何もしてないけど」
「よーしわかった。お前、その樽蹴っとけ。おれは謂れのない痛い思いなんぞさすがにしたかねえよ!」
「へー。いいんだ」
「あ?」
「これ、再起不能になっても知らないよ?」
「は」
「これ、多分まだ使う樽だよねえ。ていうかさ、なんか酒臭い。船員の飲む酒でも入れてた?」
「まあ、そうだけど」
「ほー」
少年はにっこりと笑った。ザゼリの顔が青ざめる。
「ちょ、まて、おい、ほんと待てって、キ―」
豪快な音が響く。
キオは、半ば狂ったようにその樽を殴り、蹴り続けた。やがて頑丈なはずの樽は、少しずつひび割れて、崩れていく。ザゼリは唖然とした。とても14歳の腕力とは思えない。そもそも、これだけの攻撃を自分がうけるかもしれなかったことにも呆然とする。そして、軽い気持ちで言ってしまった自分の言葉にも喚きたくなった。船長になんと言えばいいのか。
全てが粉々にただの板の破片と化した頃、ようやくキオは肩で息をしながら腰を上げる。片足で残骸を足蹴にしたまま。
まるで未来の暴君を見ているようで、ザゼリは苦笑するしかなかった。
「あーあーもう・・・何をそんなに怒ってんだか知んねえが・・・あーあもう・・・どうすっかな・・・怒られるのおれなんだけど」
「あー、ごめんね?」
「ちっとも悪いと思ってねえな」
「や、そんなことはないよ、4割程度には悪いとは思ってる。というか感謝っぽいものくらいはしてる」
「そうかそうか4割か。こないだより一割増しだな、ってそういうことじゃねえええええ」
ザゼリは頭を抱えた。
「あーあ・・・なんでおれこんな奴に懐かれちまってんだか」
「は?馬鹿言うなよ。懐いてないし。ただちょうどいい捌け口だよ」
「うわほんと、マジでひでえ・・・」
キオはふう、と息を整えて腰に手を当てる。空は薄く広がって、綺麗だ。
「ねえ、今日この辺をレミオとかが通らなかった?」
「あ?ああ・・・なんか下町に行くっつってたけど」
それを聞いた瞬間、キオが再び鬼のような顔になる。
「いや、おれに怒られてもさ・・・」
「別にお前に怒ってるんじゃないよ。僕が本気で苛つくとすればそれはレミオ以外にありえないからね。あのクソアマ・・・ッ」
それは憎々しげにキオは声を絞り出す。ザゼリは苦笑した。
「なーに怒ってんだぁ」
「あいつの不始末のせいでいつも不愉快な時間を過ごさせられるのは俺なんだよ・・・っ。あの脳味噌ふやけ女」
キオはそのままポケットに手を突っ込み、眉間に皺を寄せたまま大股で石段の道へと消えていく。そうはしながらも器用に人ごみをかき分けて一度もぶつからずに歩く辺はさすがとしか言いようがない。ザゼリはくすり、と笑って、しゃがんで板の残骸をつまみながら頬杖を付いた。
「だからあの皺・・・あいつ大丈夫かな、こんなガキの頃からあんなんで」
ザゼリはのんびりと呟いた。
それに同意するかのように、かもめが一声鳴く。
一、
ヘラクレイトス家には、宝がある。
それは【人】であったが、同時に【神の器】と同義であった。
その子供が生まれたことで、ヘラクレイトス家は新興貴族として名を馳せるようになる。
当主の愛人から生まれたその子のために、ヘラクレイトスという一介の中堅階級の一族は、大見得きって出歩けるようになった。
人々はその子供を出した、ヘラクレイトス家現当主、ベリエルザに頭を垂れる。
歯の浮くような世辞を言い、かしづく。
子供は愛人の子であったけれど、まるで元から身分の高貴なものであったかのように扱われた。
彼には長兄がいたが、長兄もまた、彼に恐れおののき、身を引いた。彼が時期ヘラクレイトス家長になることは、目に見えて明らかであった。
母親は、ヘラクレイトス家お抱えの、商家の娘であり、同様に国で有数の大企業となる。
彼が、予言の子である【かもしれない】こと、ほんの少し、残りの【予言の子】の中では頭脳も優れていたこと、ただそれだけの理由で、人は彼こそが予言の子だと言い切るようになった。
人当たりのいいその少年は、酷く心をくすませていく。
誰も、そのことに気づかない。
少年もまた、気づいて欲しいとも、思わない。
「決め手にかけるな」
ベリエルザは苛々しながら忙しなく室内を歩き回った。
その様子を、部屋の壁にもたれてにこにこと眺めている少年がいる。
少年は母親似でひどく愛らしく、桂皮色の髪からは匂い立つような美しさが際立つ。
父であるベリエルザは決して不細工ではなかったが、少年と並ぶとあまりにお粗末に見えた。
そして少年もまた、父親をひどく馬鹿にしている。
「お前、本当に、何も知らないのか?覚えはないのか?」
少年はしょんぼりとしたように俯く。
「僕が不甲斐ないばかりに・・・申し訳ありません」
「お前は先の王の行幸の際、王の目の前で風車台の羽を回してみせたではないか」
「あれは偶然です、父上。現に、ほら」
少年は【その時】と同じように片手を宙に伸ばす。そして真剣な顔つきになる。
ややあって、落胆したように嘆息しながら首を振って、少年は手を下ろした。
「僕は今、父上の机に乗っている紙束を動かそうとしてみたんです。けれど、父上、一寸たりとも動いていない・・・父上、僕だって、あの時は、僕にこんな素晴らしい力があったのかと、踊りだしたくなるような気持ちでした。もしそんな素晴らしい力があるなら、僕はもっともっと、父上のお役に立てます!けれど・・・」
少年はうなだれる。
「何度やっても、どんなに神経を集中させても、僕にはできないのです。どうしたって、風は僕の言うことを聞いてくれない。やはり、きっと、ただの偶然だったのですよ、父上。僕だって・・・僕だって・・・欲しかった。父上の役に・・・」
ベリエルザは舌打ちしながら息を吐くと、少年の桂皮色の髪をぐしゃり、と撫でた。
「もういい。お前を追い詰めるつもりなどないのだ。何もできないのなら仕方がない。だが・・・どうにも解せん。お前は確かに予言の子のはずなのに、これといって特出するものは何もないではないか」
その言葉に、少年が心の中で苛立ちを滾らせたことに、男は気付かなかった。
「あれはまるで奇跡のようであったから、もしや・・・お前にその能力はなくとも、他の二人にはあるのではないか?人を超越した神の力を、お前以外の者がよもや持ってはいまいな?」
「そんなことはないと思います、父上」
少年は、くしゃり、と笑った。
「ご存知のとおり、エリュイトス家のご子女はあのような馬鹿ですし、片やマジュ家の彼女は彼女でひどく気難しく、どちらも己の制御能力に欠けています。もしも力があるのなら、たとえ彼らの家の者が隠そうとしようとぼろが出るはずですよ。まあもし・・・僕に力があるのなら、僕は父上とこのヘラクレイトス家のために、決して余所にその力を見せるようなへまもしません」
「ふん」
ベリエルザは苦笑した。
「お前もよくよく口が悪いな。両家の御子女のことをそんなふうに言える強者はお前くらいのものだろう。あの二家はうちと違って古株の貴族なのだからな」
「じきにうちが勝ちますよ」
少年はにこり、と笑った。
ベリエルザは満足げに微笑する。
父の書斎を出て、自室に戻る。
身の回りの世話をするメイドを皆出払わせ、少年は窓の外を眺めた。不意に、苛立つように唇を噛み締め、視線の先をひどく睨みつける。そこに何かがあったわけではない。強いて言うならば、白い鳩が飛んでいた。けれど、ただそれだけのことだ。少年が苛立ったのは何も知らぬ鳩のせいなどではない。
少年は踵を返し、カフスのボタンを緩める。クローゼットを開け、堅苦しい上着を脱いで、奥の方から簡素な青染の服を引っ張り出した。ブーツを脱ぎ、靴下さえも放り投げる。
母方の祖母が編んでくれた麻糸の帽子を深く被り、少年は扉に鍵をかけた。もちろん扉の外に、【僕は疲れているのでゆっくり眠りたい。何があっても起こすな】という張り紙は抜かりなく貼り終えている。昨日夜更けまで勉強をしていたことは家人なら誰でも知っているはずだから、この言い訳もそうそう怪しまれないだろう。
少年は身軽に窓の淵へ飛び乗ると、そのまま窓の外から飛び降りた。
少年がいる部屋は屋敷の三階だ。
それでも少年が無事に着陸できたのは、異常成長した庭の草木が少年の体をそっと受け止め、再びゆっくりと枯れていったからに他ならない。
少年は右手をくるくると回した。異常繁殖した植物たちの残骸は、昼間の太陽の下では隠されてしまうほどの、しかし鋭い光の粒に包まれて、ただの灰になる。
少年はそのまま足音を立てないように、塀の隙間から外へと脱出した。
そうしてようやく少年が感情を爆発させたのは、かもめが呑気に飛び回る船着場だった。
「よう、坊主。なんだ?若いくせに眉間にしわが酔ってるじゃねえの」
「ザゼリ」
少年は無表情でその名を呼ぶと、不意ににやり、とした。
「一発殴ってもいい?」
「はぁ!?」
金髪に碧眼、容姿的には申し分ないはずなのにどこか阿呆面で残念なその青年は、汗まみれの白い上着を暑そうにはためかせながら、そばかすだらけの鼻の頭を掻いてムッとした。
「ちょい待て。おれが何をしたよ」
「何もしてないけど」
「よーしわかった。お前、その樽蹴っとけ。おれは謂れのない痛い思いなんぞさすがにしたかねえよ!」
「へー。いいんだ」
「あ?」
「これ、再起不能になっても知らないよ?」
「は」
「これ、多分まだ使う樽だよねえ。ていうかさ、なんか酒臭い。船員の飲む酒でも入れてた?」
「まあ、そうだけど」
「ほー」
少年はにっこりと笑った。ザゼリの顔が青ざめる。
「ちょ、まて、おい、ほんと待てって、キ―」
豪快な音が響く。
キオは、半ば狂ったようにその樽を殴り、蹴り続けた。やがて頑丈なはずの樽は、少しずつひび割れて、崩れていく。ザゼリは唖然とした。とても14歳の腕力とは思えない。そもそも、これだけの攻撃を自分がうけるかもしれなかったことにも呆然とする。そして、軽い気持ちで言ってしまった自分の言葉にも喚きたくなった。船長になんと言えばいいのか。
全てが粉々にただの板の破片と化した頃、ようやくキオは肩で息をしながら腰を上げる。片足で残骸を足蹴にしたまま。
まるで未来の暴君を見ているようで、ザゼリは苦笑するしかなかった。
「あーあーもう・・・何をそんなに怒ってんだか知んねえが・・・あーあもう・・・どうすっかな・・・怒られるのおれなんだけど」
「あー、ごめんね?」
「ちっとも悪いと思ってねえな」
「や、そんなことはないよ、4割程度には悪いとは思ってる。というか感謝っぽいものくらいはしてる」
「そうかそうか4割か。こないだより一割増しだな、ってそういうことじゃねえええええ」
ザゼリは頭を抱えた。
「あーあ・・・なんでおれこんな奴に懐かれちまってんだか」
「は?馬鹿言うなよ。懐いてないし。ただちょうどいい捌け口だよ」
「うわほんと、マジでひでえ・・・」
キオはふう、と息を整えて腰に手を当てる。空は薄く広がって、綺麗だ。
「ねえ、今日この辺をレミオとかが通らなかった?」
「あ?ああ・・・なんか下町に行くっつってたけど」
それを聞いた瞬間、キオが再び鬼のような顔になる。
「いや、おれに怒られてもさ・・・」
「別にお前に怒ってるんじゃないよ。僕が本気で苛つくとすればそれはレミオ以外にありえないからね。あのクソアマ・・・ッ」
それは憎々しげにキオは声を絞り出す。ザゼリは苦笑した。
「なーに怒ってんだぁ」
「あいつの不始末のせいでいつも不愉快な時間を過ごさせられるのは俺なんだよ・・・っ。あの脳味噌ふやけ女」
キオはそのままポケットに手を突っ込み、眉間に皺を寄せたまま大股で石段の道へと消えていく。そうはしながらも器用に人ごみをかき分けて一度もぶつからずに歩く辺はさすがとしか言いようがない。ザゼリはくすり、と笑って、しゃがんで板の残骸をつまみながら頬杖を付いた。
「だからあの皺・・・あいつ大丈夫かな、こんなガキの頃からあんなんで」
ザゼリはのんびりと呟いた。
それに同意するかのように、かもめが一声鳴く。
二、
キオは舌打ちをしながら黙々と人込みを潜り抜ける。
街は活気にあふれていた。道端でテントを張って行商をする者、店の展示窓に張り付いて、お菓子やおもちゃを物欲しそうに見つめる子供たち。美味しそうなパンの匂い。色とりどりに盛られた野菜の市場。
がやがやとうるさい人のおしゃべりは、しかし楽しげに空気を彩る。
路地を回って足場の狭い階段を駆け降りる。少しだけ埃っぽい。
下町までやってくると、空気は一気に煙草臭くなる。珈琲豆の香りも漂う。キオは正直この匂いは好きでなかったが、レミオはなぜかここが落ち着くといつも言っていた。レミオの父親が煙管をふかす癖があるからかもしれない。
キオはそのまま、裏通りにこぢんまりとたたずむ焦げ茶色の看板の店先に移動した。相変わらずぼろぼろの店だ。しかし店主には店を改築する金はない。キオは嘆息した。扉を開くと、ベルの音が耳に心地よく響く。この音だけは嫌いじゃないと認めてやってもいい。同時に、甘く濃い香りも鼻腔をくすぐった。これはチョコラトルの匂いだ。
キオが入ってきたことに気付くと、レミオが能天気な笑顔で手を大きく振った。
「キオ!!あなたも飲んだら??冷たいチョコラトルも美味しいわよ!」
キオはこめかみをひくつかせた。どうもこの女を見ると鳥肌が立って苛々する。
「キオは甘いもの苦手だもの」
涼しい声でエンデが言う。エンデは優雅に紫色の茶を飲んでいた。
キオは嘆息する。
「何飲んでるの、エンデ」
「桑茶じゃよ」
ティーカップを布巾で拭きながら、店主のローゼンが答える。
キオは肩をすくめた。
「え、それ旨いの」
「わたしは好き」
エンデはこともなげに言った。そして、小さく嘆息する。
「そろそろ構ってあげたら?泣きそうよ」
キオはエンデの顎の先を見てげんなりとした。レミオがふくれっ面でキオを睨んでいる。
(くそうっとうしいこのアマ・・・!!)
キオは小さく舌打ちした。顔を思いっきりしかめる。
「あのさあ、お前、俺になんか言うこたないわけ?」
レミオはきょとん、とした。青緑の大きな瞳がまんまるに見開かれる。
「へ?」
その間抜けな声に、頭の血管がぶち切れる音がした。キオは顔をゆがめつつも極めて笑顔を装う。
「だーかーらーぁ、卯の月櫨の日赤の刻。忘れたとは言わせねえ」
「ええと・・・うーん・・・何があった日?日付言われてもわからないわ。あっ、もしかして、ラゼルタさんとこの雌山羊に赤ちゃん生まれた時?」
「確かに惜しいがお前はそういうことしか印象に残ってねえわけ!!!」
キオはついに怒鳴った。
「へ?で、でも、他に何か・・・あ、わかった、サコルさんとこで新作パンを試食させてもらえたんだったわね?」
「日にちが遠くなった!!ちげえよ!!」
「え?ええ??」
エンデが嘆息する。
「王様がお通りになった日よ」
「え?あ、あっ、そっか!!そんなこともあったわね!!」
「レミオ。ここにいるのはわたし達だけだからいいけど、そんなこと大声で言ったら処罰されかねないわよ」
「まあまあ。子供にはあまり興味の惹かれないことじゃろうて」
「・・・ローゼンさんはレミオに甘すぎるわ」
「こんっのクソアマぁああああ!!!!」
キオは切れた。レミオの肩をぐらぐらと揺さぶる。
「ま、ちょ、ま、待って、キ―痛っ!!舌噛んだぁ・・・っ」
「るせええ!!そのまま舌噛み切ってくたばれや!!!」
「な、なにそんなに怒ってるのぉ!?」
エンデが眉間に手の甲を当てる。
「レミオ・・・あなたのしでかしたこともう忘れたわけ・・・」
「え?ええ??」
キオは肩で息をしながらぐいっ、とエンデの飲んでいた桑茶の残りを飲み干した。息を整える。
「はぁ・・・はぁ・・・とにかく。一回外出るぞ。くそっ。ごちそうさん!!」
「ごちそうさまでした」
「え?ちょ、ちょっと、髪引っ張らないで!!痛い痛いご、ごちそうさまでしたぁああ」
三人は慌ただしく外へ消える。
「若者はいいねえ、賑やかなことだよ」
残されたローゼン翁はにこにこと笑った。カウンターに乗っていたぶち猫がニー、とあくびをする。
柵の隙間から鉄道と海が見渡せる、時計台のある丘までレミオを引きずり、ようやくキオはレミオを解放した。レミオは涙目で薄紅の髪をくしゃりと握りしめる。
「いいか」
キオはどす黒い笑みを浮かべた。
「言ったよなあ、俺。何度も何度も再三言ってきたよなあ、俺!?な ん で お前はいつもいつもそう約束忘れやがる!!後始末するのはいつも俺だぞ!!!!」
「たまにわたしも、だけど」
エンデが小さくぼやく。
「え、えっと・・・」
「人前で【力】使うなって何度言えばわかるわけ?しかもなにさあれ!!何のつもりであんなことした!!ごまかすのにも限度があるんだけど!!」
「え?ええと・・・あ!」
ようやくレミオは事態を理解したようだった。申し訳なさそうに俯く。
「ご、ごめんなさい・・・べ、別に使うつもりはなかったのよ。ただ・・・わからないの。暴走してしまって」
「暴走じゃ済まないっつうの・・・!」
キオは腕を組み口の端をひくつかせながら苛々と片足で地面を叩く。
「だ、だって・・・!!」
「だってじゃない!!」
「まあ・・・レミオの言い分も聞いてあげてよ」
エンデが肩をすくめた。
「あ?言うならさっさと言いやがれ!!」
「そ、その・・・だって、キオがみんなから責められてるの見たら、胸が痛くて、そしたら体が熱くなって、いつの間にか、風車が動いちゃってたんだもの・・・!」
「はぁ?」
キオは呆れたように呟いた。
「なんだそれ。ほんっとに意味不明だな。どのあたり責められてたんだよ。普通の会話してただけじゃん」
「い、いじめられてたよ!?みんな、寄ってたかって・・・まだキオは子供なのに、すごく厳しいこと言ってた・・・怖かったの、なのにキオ、平気そうな顔してるんだもの!」
「俺にとっては普通だよ。むしろお前の感覚がわかんない。平気そうも何も、実際平気なんだよ」
キオは頭を掻いた。
「でも、キオ、たしかにヘラクレイトスの人たちはわたしやレミオのお家の人たちよりもずっと、あなたを子供扱いしなさすぎると思うわ」
「子供扱いなんざされたくないね。気色悪い」
「あなたはそれで平気かもしれないけど、わたしも確かに、見ててちょっと怖かったわ。大人扱いどころの話じゃないもの。まるであなたがヘラクレイトス家の全てを背負っているみたい」
「実際似たようななものだけど?」
キオはきょとん、として言った。
「むしろ早く年齢ともに大人になりたいね。そうしたら、全ての人間を黙らせてやる。うっとうしい小蝿なんかさっさと掃ってしまいたいし」
レミオがぎゅっ、と服を掴む。
「キオったら・・・!!わたしたちまだ14歳よ!」
「もう14歳だよ!!馬鹿だろお前?いいか、数年前まではみんな俺達を大目に見てくれてたかもしんない。だけど、もうあのころとは違う。何度も言ったろ?元々俺達は、この印を持って生まれてきてしまった時点で、【家】の道具なんだ」
キオは左の目じりにある、二つ並んだ黒子を指差した。
「しかもそいつらが全て、尋常でない力を持ってるだなんて知られてみろよ、俺達は絶対に利用される。確かに俺は大人びてるかもしれない、だけど、大人のこずるい知恵にはどうしたって敵わないよ。だから身を守りたいんだ。特にお前!お前みたいなのろまは絶対に家の思うつぼだ」
「うちの人たちはそんなことないもん」
「お前さ、自分で言ったこと忘れたか?俺は忘れてない。ガキの頃だったけど、俺に泣きついたじゃないか、『わたしは不出来な子なの。だからみんなわたしを見限ってるの』って」
レミオは唇を噛んだ。
「あれで俺が『本物の馬鹿のふりをしろ』って言ったから、まあ、お前がこんな抜けた性格になっちゃったんだろうけどさ・・・そう考えるとお前のすっとぼけも俺のせいでもあるんだけど・・・」
キオは力が抜けたように嘆息した。そうしてレミオの頭にぽん、と手を載せた。
「まあ、一応ごまかしたけどさ。俺は風の力使えないし。やつらはみんな、あれは俺がしたことだと勘違いしてたから、一応切り抜けたけどさ。でも、俺がいないところでお前がもし力暴発させたらさすがの俺にもごまかしてやることできない。だから、頼むから気をつけてくれよ・・・俺のことなんかどうでもいいよ・・・何が責められてたから、だよ、ったく」
キオは深々と息を吐く。レミオは俯いたままだった。
「その点、エンデはへまやらかしたこと一度もないよな。ほんと」
エンデはほほ笑んだ。
「私が自分の力に気付いたのは、あなた達二人から話を聞いた後だったもの。どうとでも出来たわ。レミオがあちこちで騒動起こしてくれるから、なるほど、こういう風にしちゃいけないのか、って先に勉強になってるし」
「ひ、ひどぉい!!そうなる前に止めてよ!?」
レミオが叫ぶと、エンデはくすくすと笑った。キオは小さく嘆息する。
「でもまあ・・・気をつけろよ?エンデの場合、下手すると人命巻き込みかねないし」
エンデはにっこりと笑った。
「大丈夫よ。それに、お互い様でしょ?」
キオは肩をすくめた。
キオは舌打ちをしながら黙々と人込みを潜り抜ける。
街は活気にあふれていた。道端でテントを張って行商をする者、店の展示窓に張り付いて、お菓子やおもちゃを物欲しそうに見つめる子供たち。美味しそうなパンの匂い。色とりどりに盛られた野菜の市場。
がやがやとうるさい人のおしゃべりは、しかし楽しげに空気を彩る。
路地を回って足場の狭い階段を駆け降りる。少しだけ埃っぽい。
下町までやってくると、空気は一気に煙草臭くなる。珈琲豆の香りも漂う。キオは正直この匂いは好きでなかったが、レミオはなぜかここが落ち着くといつも言っていた。レミオの父親が煙管をふかす癖があるからかもしれない。
キオはそのまま、裏通りにこぢんまりとたたずむ焦げ茶色の看板の店先に移動した。相変わらずぼろぼろの店だ。しかし店主には店を改築する金はない。キオは嘆息した。扉を開くと、ベルの音が耳に心地よく響く。この音だけは嫌いじゃないと認めてやってもいい。同時に、甘く濃い香りも鼻腔をくすぐった。これはチョコラトルの匂いだ。
キオが入ってきたことに気付くと、レミオが能天気な笑顔で手を大きく振った。
「キオ!!あなたも飲んだら??冷たいチョコラトルも美味しいわよ!」
キオはこめかみをひくつかせた。どうもこの女を見ると鳥肌が立って苛々する。
「キオは甘いもの苦手だもの」
涼しい声でエンデが言う。エンデは優雅に紫色の茶を飲んでいた。
キオは嘆息する。
「何飲んでるの、エンデ」
「桑茶じゃよ」
ティーカップを布巾で拭きながら、店主のローゼンが答える。
キオは肩をすくめた。
「え、それ旨いの」
「わたしは好き」
エンデはこともなげに言った。そして、小さく嘆息する。
「そろそろ構ってあげたら?泣きそうよ」
キオはエンデの顎の先を見てげんなりとした。レミオがふくれっ面でキオを睨んでいる。
(くそうっとうしいこのアマ・・・!!)
キオは小さく舌打ちした。顔を思いっきりしかめる。
「あのさあ、お前、俺になんか言うこたないわけ?」
レミオはきょとん、とした。青緑の大きな瞳がまんまるに見開かれる。
「へ?」
その間抜けな声に、頭の血管がぶち切れる音がした。キオは顔をゆがめつつも極めて笑顔を装う。
「だーかーらーぁ、卯の月櫨の日赤の刻。忘れたとは言わせねえ」
「ええと・・・うーん・・・何があった日?日付言われてもわからないわ。あっ、もしかして、ラゼルタさんとこの雌山羊に赤ちゃん生まれた時?」
「確かに惜しいがお前はそういうことしか印象に残ってねえわけ!!!」
キオはついに怒鳴った。
「へ?で、でも、他に何か・・・あ、わかった、サコルさんとこで新作パンを試食させてもらえたんだったわね?」
「日にちが遠くなった!!ちげえよ!!」
「え?ええ??」
エンデが嘆息する。
「王様がお通りになった日よ」
「え?あ、あっ、そっか!!そんなこともあったわね!!」
「レミオ。ここにいるのはわたし達だけだからいいけど、そんなこと大声で言ったら処罰されかねないわよ」
「まあまあ。子供にはあまり興味の惹かれないことじゃろうて」
「・・・ローゼンさんはレミオに甘すぎるわ」
「こんっのクソアマぁああああ!!!!」
キオは切れた。レミオの肩をぐらぐらと揺さぶる。
「ま、ちょ、ま、待って、キ―痛っ!!舌噛んだぁ・・・っ」
「るせええ!!そのまま舌噛み切ってくたばれや!!!」
「な、なにそんなに怒ってるのぉ!?」
エンデが眉間に手の甲を当てる。
「レミオ・・・あなたのしでかしたこともう忘れたわけ・・・」
「え?ええ??」
キオは肩で息をしながらぐいっ、とエンデの飲んでいた桑茶の残りを飲み干した。息を整える。
「はぁ・・・はぁ・・・とにかく。一回外出るぞ。くそっ。ごちそうさん!!」
「ごちそうさまでした」
「え?ちょ、ちょっと、髪引っ張らないで!!痛い痛いご、ごちそうさまでしたぁああ」
三人は慌ただしく外へ消える。
「若者はいいねえ、賑やかなことだよ」
残されたローゼン翁はにこにこと笑った。カウンターに乗っていたぶち猫がニー、とあくびをする。
柵の隙間から鉄道と海が見渡せる、時計台のある丘までレミオを引きずり、ようやくキオはレミオを解放した。レミオは涙目で薄紅の髪をくしゃりと握りしめる。
「いいか」
キオはどす黒い笑みを浮かべた。
「言ったよなあ、俺。何度も何度も再三言ってきたよなあ、俺!?な ん で お前はいつもいつもそう約束忘れやがる!!後始末するのはいつも俺だぞ!!!!」
「たまにわたしも、だけど」
エンデが小さくぼやく。
「え、えっと・・・」
「人前で【力】使うなって何度言えばわかるわけ?しかもなにさあれ!!何のつもりであんなことした!!ごまかすのにも限度があるんだけど!!」
「え?ええと・・・あ!」
ようやくレミオは事態を理解したようだった。申し訳なさそうに俯く。
「ご、ごめんなさい・・・べ、別に使うつもりはなかったのよ。ただ・・・わからないの。暴走してしまって」
「暴走じゃ済まないっつうの・・・!」
キオは腕を組み口の端をひくつかせながら苛々と片足で地面を叩く。
「だ、だって・・・!!」
「だってじゃない!!」
「まあ・・・レミオの言い分も聞いてあげてよ」
エンデが肩をすくめた。
「あ?言うならさっさと言いやがれ!!」
「そ、その・・・だって、キオがみんなから責められてるの見たら、胸が痛くて、そしたら体が熱くなって、いつの間にか、風車が動いちゃってたんだもの・・・!」
「はぁ?」
キオは呆れたように呟いた。
「なんだそれ。ほんっとに意味不明だな。どのあたり責められてたんだよ。普通の会話してただけじゃん」
「い、いじめられてたよ!?みんな、寄ってたかって・・・まだキオは子供なのに、すごく厳しいこと言ってた・・・怖かったの、なのにキオ、平気そうな顔してるんだもの!」
「俺にとっては普通だよ。むしろお前の感覚がわかんない。平気そうも何も、実際平気なんだよ」
キオは頭を掻いた。
「でも、キオ、たしかにヘラクレイトスの人たちはわたしやレミオのお家の人たちよりもずっと、あなたを子供扱いしなさすぎると思うわ」
「子供扱いなんざされたくないね。気色悪い」
「あなたはそれで平気かもしれないけど、わたしも確かに、見ててちょっと怖かったわ。大人扱いどころの話じゃないもの。まるであなたがヘラクレイトス家の全てを背負っているみたい」
「実際似たようななものだけど?」
キオはきょとん、として言った。
「むしろ早く年齢ともに大人になりたいね。そうしたら、全ての人間を黙らせてやる。うっとうしい小蝿なんかさっさと掃ってしまいたいし」
レミオがぎゅっ、と服を掴む。
「キオったら・・・!!わたしたちまだ14歳よ!」
「もう14歳だよ!!馬鹿だろお前?いいか、数年前まではみんな俺達を大目に見てくれてたかもしんない。だけど、もうあのころとは違う。何度も言ったろ?元々俺達は、この印を持って生まれてきてしまった時点で、【家】の道具なんだ」
キオは左の目じりにある、二つ並んだ黒子を指差した。
「しかもそいつらが全て、尋常でない力を持ってるだなんて知られてみろよ、俺達は絶対に利用される。確かに俺は大人びてるかもしれない、だけど、大人のこずるい知恵にはどうしたって敵わないよ。だから身を守りたいんだ。特にお前!お前みたいなのろまは絶対に家の思うつぼだ」
「うちの人たちはそんなことないもん」
「お前さ、自分で言ったこと忘れたか?俺は忘れてない。ガキの頃だったけど、俺に泣きついたじゃないか、『わたしは不出来な子なの。だからみんなわたしを見限ってるの』って」
レミオは唇を噛んだ。
「あれで俺が『本物の馬鹿のふりをしろ』って言ったから、まあ、お前がこんな抜けた性格になっちゃったんだろうけどさ・・・そう考えるとお前のすっとぼけも俺のせいでもあるんだけど・・・」
キオは力が抜けたように嘆息した。そうしてレミオの頭にぽん、と手を載せた。
「まあ、一応ごまかしたけどさ。俺は風の力使えないし。やつらはみんな、あれは俺がしたことだと勘違いしてたから、一応切り抜けたけどさ。でも、俺がいないところでお前がもし力暴発させたらさすがの俺にもごまかしてやることできない。だから、頼むから気をつけてくれよ・・・俺のことなんかどうでもいいよ・・・何が責められてたから、だよ、ったく」
キオは深々と息を吐く。レミオは俯いたままだった。
「その点、エンデはへまやらかしたこと一度もないよな。ほんと」
エンデはほほ笑んだ。
「私が自分の力に気付いたのは、あなた達二人から話を聞いた後だったもの。どうとでも出来たわ。レミオがあちこちで騒動起こしてくれるから、なるほど、こういう風にしちゃいけないのか、って先に勉強になってるし」
「ひ、ひどぉい!!そうなる前に止めてよ!?」
レミオが叫ぶと、エンデはくすくすと笑った。キオは小さく嘆息する。
「でもまあ・・・気をつけろよ?エンデの場合、下手すると人命巻き込みかねないし」
エンデはにっこりと笑った。
「大丈夫よ。それに、お互い様でしょ?」
キオは肩をすくめた。
三、
かつてこの国の空には、決してその位置を変えない二つの星があった。
人々は、赤く輝く一つを、ルフェラ、橙の光を放つ一つを、サフィアと讃えていた。
神話がある。
彼ら神々はかつてこの大地に住まい、緑を、青を、生き物を、人を、作りたもうた。
やがて彼らは人の勤勉さに感じ入り、住み慣れた大地を人の住む家として与えたもうた。
彼らは全て黒き空へと渡り、人々を見守っている。
彼らが空へと住まったがために、空には星というものが現われた。
それは夜空を彩り、闇に脅える命を導いた。
人々は、この光る星は全て、神そのものの姿だと知った。
神は時折、寵愛なさった生き物をも、傍に召される。
彼らもまた、星となる。
星となることは、人々の誇りであった。尊く生きれば、星になれる【かもしれない】。
星にまつわる神話が数多く生まれた。
時に、空から星が消えてしまうこともあった。
人々は理解した。星となった賢者、神々が、この地に再び降臨なさるのだと。
数々の英雄の伝説が生まれた。
空と大地をつなぐその物語こそ、人々を魅了してやまない。
大地が生まれ幾千の時を経てなお、人々が流行り病や度重なる戦、覆せぬ貧富の差に耐え生きることができるのは、神々のための物語が、今も人々の心に根付いているからだった。
ルフェラとサフィアは、かつての戦乱、混沌の三千年を終結させた双子の英雄である。
世界は二人によってようやく統一され、戦は終わりを告げた。
以後、小さな紛争は各地で起こるも、【暗黒戦争】のような戦乱は二度と起こってはいない。
彼らは非常に美しい存在であったとも伝えられている。
神に愛された二人は、世界を平定してのち、その行く末を見守ることなきままに、天に召され、二つの星となった。
ルフェラと同じ髪の色の星、サフィアと同じ髪の色の星。
彼らの死とともに空に現れ、以来不動のままそこに在り続ける双つ星こそ、英雄神そのものであるのだと、人々は知った。
旅をする者、海に出るもの、彼らは凡て、【ルフェラ】と【サフィア】を目印に歩む。
双子神は人々を見守り続けている。
その双つ星が空から消えて、まだ十数年にも満たなかった。
人々は、まさにかつての英雄が再び降臨されるのだと知った。
折しも、絶対神クルトェラを奉る中央教会の下位修道女が、第三等神ダジエルダからの詔を賜る事態が起こる。
神は言われた。
『其の赤子
生まれ落つ時しより
彼の者である
此れ須らく
空に還るべき末なり』
かつてこの国の空には、決してその位置を変えない二つの星があった。
人々は、赤く輝く一つを、ルフェラ、橙の光を放つ一つを、サフィアと讃えていた。
神話がある。
彼ら神々はかつてこの大地に住まい、緑を、青を、生き物を、人を、作りたもうた。
やがて彼らは人の勤勉さに感じ入り、住み慣れた大地を人の住む家として与えたもうた。
彼らは全て黒き空へと渡り、人々を見守っている。
彼らが空へと住まったがために、空には星というものが現われた。
それは夜空を彩り、闇に脅える命を導いた。
人々は、この光る星は全て、神そのものの姿だと知った。
神は時折、寵愛なさった生き物をも、傍に召される。
彼らもまた、星となる。
星となることは、人々の誇りであった。尊く生きれば、星になれる【かもしれない】。
星にまつわる神話が数多く生まれた。
時に、空から星が消えてしまうこともあった。
人々は理解した。星となった賢者、神々が、この地に再び降臨なさるのだと。
数々の英雄の伝説が生まれた。
空と大地をつなぐその物語こそ、人々を魅了してやまない。
大地が生まれ幾千の時を経てなお、人々が流行り病や度重なる戦、覆せぬ貧富の差に耐え生きることができるのは、神々のための物語が、今も人々の心に根付いているからだった。
ルフェラとサフィアは、かつての戦乱、混沌の三千年を終結させた双子の英雄である。
世界は二人によってようやく統一され、戦は終わりを告げた。
以後、小さな紛争は各地で起こるも、【暗黒戦争】のような戦乱は二度と起こってはいない。
彼らは非常に美しい存在であったとも伝えられている。
神に愛された二人は、世界を平定してのち、その行く末を見守ることなきままに、天に召され、二つの星となった。
ルフェラと同じ髪の色の星、サフィアと同じ髪の色の星。
彼らの死とともに空に現れ、以来不動のままそこに在り続ける双つ星こそ、英雄神そのものであるのだと、人々は知った。
旅をする者、海に出るもの、彼らは凡て、【ルフェラ】と【サフィア】を目印に歩む。
双子神は人々を見守り続けている。
その双つ星が空から消えて、まだ十数年にも満たなかった。
人々は、まさにかつての英雄が再び降臨されるのだと知った。
折しも、絶対神クルトェラを奉る中央教会の下位修道女が、第三等神ダジエルダからの詔を賜る事態が起こる。
神は言われた。
『其の赤子
生まれ落つ時しより
彼の者である
此れ須らく
空に還るべき末なり』
********************
鏡に手を当てる。
映る萌黄色の瞳は、微動だにしない。
エンデは左の目元を指でそっと撫でた。
(これさえ無かったら)
そう、思わずにはいられない。けれど、言っても詮無きことだ。
ただの二つの黒子は、まるで警告の証のようだった。
「こんなもの、救いなんかじゃないわ」
エンデは冷えた声で、鏡の向こうの人形に呟く。
エンデは三人の中では一番最後に生まれた。
【予言の子】、それが現実になったのは、キオ=ヘラクレイトスが生まれた時だ。
キオには、生まれながらにして、左の目尻に二つ並ぶ黒子があった。
新興貴族ヘラクレイトス家は、予言と照らし合わせ、彼こそがその予言だとお祭り騒ぎだったという。
その後、数刻も満たないうち、エリュイトスという名の古参の貴族の家で、全く同じ黒子を有した女児が生まれた。
エリュイトス家は、王宮に古くから仕える家系で、何人もの側室を出していることでも有名な身分の高い家柄だった。
ヘラクレイトス家とエリュイトス家は反りが合わない。
しかし、二人が予言の子であれば、手を組むことは悪い話ではなかった。
その日のうちに、内密に当主は会合を開いたという。
二人は許嫁となり、名も、かのルフェラとサフィアの故国であると伝わるサビラの地の言葉で、【兄】と【弟】を表す言葉を与えられた。
エンデが生まれたのは、翌日の明け方だった。
エンデが生まれたその日、母屋で小火が起こった。
母は産後まもなく動きが取れず、その煙で喉を潰した。
それまでは、とても美しい声の持ち主だったという。エンデには年の離れた兄が二人いるが、幼い頃にはたくさんの童謡を歌って聞かせてくれていたと聞いた。兄達はそのせいか、たくさんの歌を、物語を知っていた。けれど、エンデはほとんど知らない。
母の声は、しわがれた声しか知らなかった。幼い頃、どうして自分の母の声はおばあさんみたいなのか、他所の母はあんなに綺麗な声をしているのに、とぐずったことがある。
ぞっとする。
けれど、母は決して、怒らなかった。
大きくなって、そのことを知って、思い出して、恐ろしくなった。
赤子の頃、エンデが泣く度、あちこちで小火が起こったという。
それまで古きを愛し、蝋燭を用いた灯篭を屋敷に拵えていた父が、全て発明されたばかりの電球に切り替えたのも、その頃だった。当時電球は高価で、元々没落貴族であったマジュ家は、財産をほとんど使ってしまったらしい。
【エンデが泣くと、火事になる】
【エンデが怒ると、火事になる】
【エンデに恨まれたら最後、僕らみんな丸焼きだ】
兄達も、少年時代の遊びたい盛りに、貧乏のために苦労してきたのだと思う。
そんな歌を聞かされて、育った。両親の知らないところで。
兄達は優しかった。声のほとんど出なくなった母に代って、エンデに本を読み聞かせしてくれたし、めずらしい絵画や玩具もたくさん見せてくれた。与えてくれた。
けれど同時に心に重くたまっていく不満を、歌で爆発させることが多かった。
それを歌っていた兄達の表情が、今もまぶたの裏に焼きついて離れない。
可愛がってくれていたのは、それでもの肉親の愛情ゆえなのか、それともエンデが恐ろしかったからなのか。
そんなこと、怖くて聞けるはずもない。
キオとレミオの誕生は、国中に知らせられた。国民の喜びは相当なものだった。
彼らの誕生を祝って、盛大な祭りが開かれたほどだ。
数日して、エンデの父は、自分の娘がその【予言の子であるかもしれない】ということを、母にも告げたという。
二人は、エンデの存在を隠すことにした。ヘラクレイトス家とエリュイトス家ほど、敵に回すと恐ろしい家はなかった。
【勢力争いに巻き込みたくなかった】と、父は言う。
『大きくなれば、その黒子も偶然だと言い張れるだろう。お前はお前なのだから、予言の子でなくともよい。誰かを愛し愛され、年老いる、そんな平凡な幸せが、女の子には一番似合っている』
怖かった。
大きくなればなるほど、自分の周りの環境を理解した。自分のせいで奪われたかもしれない幸せを、知った。
それなのに愛情を向けられることが、怖かった。
そんな資格はないと思った。
それでいて、敵意を時折向けてくる兄達のまなざしも、怖いと思った。
結局、全て信じられなかったのだ。
エンデの正体は、あっけなく露見した。
詰めの甘い父のせいだったかもしれない。
貴族の集まる華やかな茶会を、娘にも見せてあげたいという親心だった。
あの頃、どれだけレミオを恨んだか知れない。
レミオのたった一言で、全てが台無しになった。
あの指差しを、今でも忘れられない。
『見て!!あの子、わたしと同じ黒子があるわ!!』
あの時真っ先にエンデの前に現れたのが、キオだった。
キオはエンデを見ると、エンデにとっては【恐ろしい】顔をした。
まるで憎まれているような。
けれどあれは、自分の、自分達の運命を呪っての子供じみた怒りだったのだと、今ならわかる。
彼は一瞬で表情を柔らかく【人前用】に戻すと、エンデをかっさらった。
レミオというおまけつきで。
『端的に聞く。お前、人と違う何かがあるか』
最初、何を聞かれているのか分からなかった。キオは小声でエンデにたたみかける。
『お前のその黒子がただの黒子か、それとも僕達と同じ類のものか、それを知りたい。返答によっては僕達の、いや、僕の対応が変わってくるから。悪いようにはしない。絶対に、君に悪いようにはしない!』
その目は酷く真剣だった。エンデは、掴まれた手首が痛いとようやく感じた。少しだけ体が震える。
『ど、どういうこと?違うって・・・何が』
目に涙が滲んだ。【歌】を聞かされるようになってから、一度も人前で泣いたことなどなかった。エンデは唇をかみしめて堪えた。キオは、ほう、と息をつくと、エンデの手を解放した。諦めきったような表情で、薄く笑った。
『十分だ』
その言葉に胸が締め付けられる。
『ごめんなさい・・・!!ごめんなさい!!』
思わず頭を抱えしゃがみこんだ。体がかたかたと震えていた。けれど、レミオがその背中をそっとさすってくれた。
『もう!!キオが怖い顔してるから泣いちゃったじゃないの!!』
『あぁ!?もとはと言えば誰のせいだよ!!お前がすっとぼけたこと大声で言うからだろが・・・!!』
キオはくわっとして怒鳴った後、もう一度深呼吸した。
『これを見て』
キオは花壇に咲いていた一輪の蕾を摘み取り、エンデの目の前にかざした。
キオの手元が鈍く光った。瞬間、蕾は生き生きと花開く。やがてそれはまたたく間に枯れていった。もう一度キオの手が光る。一瞬のうちに葉や茎は燃え灰になって、キオの手には綿毛だけが残った。
エンデは目を丸くした。まるで魔法を見ているようだ。
『たぶんお前にも、こういうことができるんだと思う。予言の子なら、ね。僕は光を操ることができる。こうして、植物の成長を早めたり、灰にしたり、暗がりで明かりをともすこともできる。レミオは風を操ることができる。風の力を借りてどんな高い所にだって登れる』
『空は飛べないけどね』
レミオが舌を出す。
『それはお前の体重が重いからじゃないの』
『ひ、ひどい!!そ、そんなことないわよ!!』
レミオはむっとして、ぱしぱし、とキオの背中を叩いた。
『あ、あとね、私水浴びた後でもすぐに髪を乾かすことができるの!おかげで寝冷えで風邪ひいたことは全くないのよ、結構便利でしょ』
レミオはにこにこと笑った。
エンデはまだ震えていた。頭がついていかなかった。キオはぽん、とエンデの頭に手を載せた。
『言いたくないなら今は言わなくてもいい。だけど、僕達君の敵じゃないから。むしろ敵は大人だから』
キオの目に再び鋭い怒りが宿った。それはエンデに向けてのものではないと、エンデにも理解できた。
『何かあったら、港にいる金髪頭ののっぽに伝えて。ザゼリ、っていうんだけど。あいつは信用できるから』
キオはそのまま姿を茂みの中へと消した。
レミオはそのままエンデの傍にいた。にっこりと無邪気に笑う。
『ね、おままごとしよっか!!』
そう言って、花壇の草花を摘んで、編み始めた。
エンデは複雑な気持ちになる。
***
それが自分の【力】だと知るまでに、時間がかかった。
確かめたくて、けれど、怖かった。
母に港に行きたいと言ったら、目を丸くした後、『じゃあ林檎も買ってきてくれる?』と言われた。
母はほほ笑んでいた。何も聞かないでいてくれた。
泣きたくなった。
エンデは庶民の服に着替え、フードで顔を隠して港へ向かった。
かもめがたくさん飛んでいる。
船着き場は、たくさんの男達で賑わっていた。
恰幅のいい男が樽を抱えて、通り過ぎる。
荷台を押して、木箱を運んでいた男が、エンデを見て首をかしげた。
『よう、嬢ちゃん、なんか用か?』
エンデは答えられなかった。普段話すことに慣れていないから、こういう時にとっさに声が出ない。
男は髭の生えた顎を掻く。
『ふーん・・・こういうのはあいつ専門かねえ。嬢ちゃん、ちょいと待ってな。ここに子供がやたら好きな馬鹿連れてくるからよ』
男が通り過ぎて、どれくらい経っただろう。
その場にしゃがみこみ震えながら待っていたエンデの頭上から、掠れたような少年の声が聞こえた。
『なんだぁ?待ってるのって、あんた?』
エンデがはっ、として顔を上げると、そばかすだらけの顔が目に入る。綺麗な青い大きな目に、エンデの顔が映っている。
少年はまじまじとエンデを見詰めた後、ふにゃり、と笑った。その笑顔になぜだかとても安堵して、胸が苦しくなった。少年はくしゃくしゃとエンデの頭を撫でまわす。
『おれ、ザゼリ。あんたは?』
エンデは泣いた。とてつもなく、気が抜けたのだ。ザゼリは驚いたようだったが、にこにことほほ笑みながら、エンデが泣き止むまで待っていてくれた。
『ここなら、万が一のことがあっても、大丈夫だと思うの』
『万が一?』
ザゼリは首をかしげる。エンデは首を振った。
『あのね、ごみでいいから、なくなっても困らないもの、くれない?』
『ごみ!?ごみねえ・・・あ、そうだ』
ザゼリはポケットからくしゃくしゃになった紙切れを取りだす。
『これ、どうせ捨てようと思ってたもんだし、いいよ』
『・・・手紙?』
『まあ・・・あっ!!でも読むなよ!!何があっても読むなよ!?ぜってえ読むなよ!!?』
エンデは呆気にとられる。ザゼリは耳まで真っ赤になって、頭を掻いた。
『いや・・・その、さ、それ、バルクローレって港町でお花売ってるお嬢さんがさ、すっげえ可愛くて、おしとやかで、もうほんとに、可愛いのさ』
『は、はあ』
『それで・・・その・・・ああああもういいや!!と、とにかく!!それ失敗作だから!!』
エンデは手元のくしゃくしゃになった紙を見つめる。
『でもこれ・・・匂い付きの紙だもの。結構上等だわ。大事な気持ちが書いてあるんでしょう?』
ザゼリは顔を真っ赤にした。
『い、いいの!!やっぱ男はさ、こんなちまちま手紙書くよか当たって砕けるべきだと思うわけ!!だからそれはどうせ使わないの。というか、俺が持ってるとぜってえ捨てらんないからさ、捨てといてよ』
エンデはくすりと笑った。
『砕けないでね』
ザゼリは目を丸くすると、照れたように頬を掻く。
『ちょっと、後ろ向いていて』
『あ?』
『ちょっとだけ、お願い』
『は?ま、まあいいけど』
ザゼリは大人しく背を向けた。エンデはそっと、しゃがみこむ。眼下には、海の面が揺らめいている。エンデは深呼吸した。目を閉じて、キオのやっていたように、手をそっと、紙の端に当てる。意識を集中させる。
手のひらが、ちりちりと痛んだ。煙の匂いがしたような気がして、目を開ける。線香のように角の所が燃えて、墨になっていた。エンデはその部分を海の水に浸す。
立ちあがって、小さく嘆息した。
『もういいわ、ザゼリさん』
『お?おう』
ザゼリはきょとん、として振り返る。歳も背もエンデよりも大きい彼は、それでいて自分よりもずっと無邪気で可愛い子供のように思えた。
エンデは微笑した。いつから、こんなに、【当たり障りのない】笑顔ができるようになったのだろう。自然に笑えた。口の端の筋肉がひきつることもない。
『もしここに・・・キオ、って子とか、レミオ、って子が来たら・・・伝えておいて。待ってる、って。探しに来て、って。いつまでも、待ってる、って』
ザゼリはお日様のように笑った。
『おー。やっぱあいつらのダチか!伝えとく。あんたもまた遊びに来な、エンデ』
『少しは進展してるといいわね』
エンデが柔らかくほほ笑むと、ザゼリは一瞬きょとん、として、すぐに顔を音が出そうなほどに赤らめた。
『お、お、おおう・・・!!ま、まかしとけ!!』
それが自分の【力】だと知るまでに、時間がかかった。
確かめたくて、けれど、怖かった。
母に港に行きたいと言ったら、目を丸くした後、『じゃあ林檎も買ってきてくれる?』と言われた。
母はほほ笑んでいた。何も聞かないでいてくれた。
泣きたくなった。
エンデは庶民の服に着替え、フードで顔を隠して港へ向かった。
かもめがたくさん飛んでいる。
船着き場は、たくさんの男達で賑わっていた。
恰幅のいい男が樽を抱えて、通り過ぎる。
荷台を押して、木箱を運んでいた男が、エンデを見て首をかしげた。
『よう、嬢ちゃん、なんか用か?』
エンデは答えられなかった。普段話すことに慣れていないから、こういう時にとっさに声が出ない。
男は髭の生えた顎を掻く。
『ふーん・・・こういうのはあいつ専門かねえ。嬢ちゃん、ちょいと待ってな。ここに子供がやたら好きな馬鹿連れてくるからよ』
男が通り過ぎて、どれくらい経っただろう。
その場にしゃがみこみ震えながら待っていたエンデの頭上から、掠れたような少年の声が聞こえた。
『なんだぁ?待ってるのって、あんた?』
エンデがはっ、として顔を上げると、そばかすだらけの顔が目に入る。綺麗な青い大きな目に、エンデの顔が映っている。
少年はまじまじとエンデを見詰めた後、ふにゃり、と笑った。その笑顔になぜだかとても安堵して、胸が苦しくなった。少年はくしゃくしゃとエンデの頭を撫でまわす。
『おれ、ザゼリ。あんたは?』
エンデは泣いた。とてつもなく、気が抜けたのだ。ザゼリは驚いたようだったが、にこにことほほ笑みながら、エンデが泣き止むまで待っていてくれた。
『ここなら、万が一のことがあっても、大丈夫だと思うの』
『万が一?』
ザゼリは首をかしげる。エンデは首を振った。
『あのね、ごみでいいから、なくなっても困らないもの、くれない?』
『ごみ!?ごみねえ・・・あ、そうだ』
ザゼリはポケットからくしゃくしゃになった紙切れを取りだす。
『これ、どうせ捨てようと思ってたもんだし、いいよ』
『・・・手紙?』
『まあ・・・あっ!!でも読むなよ!!何があっても読むなよ!?ぜってえ読むなよ!!?』
エンデは呆気にとられる。ザゼリは耳まで真っ赤になって、頭を掻いた。
『いや・・・その、さ、それ、バルクローレって港町でお花売ってるお嬢さんがさ、すっげえ可愛くて、おしとやかで、もうほんとに、可愛いのさ』
『は、はあ』
『それで・・・その・・・ああああもういいや!!と、とにかく!!それ失敗作だから!!』
エンデは手元のくしゃくしゃになった紙を見つめる。
『でもこれ・・・匂い付きの紙だもの。結構上等だわ。大事な気持ちが書いてあるんでしょう?』
ザゼリは顔を真っ赤にした。
『い、いいの!!やっぱ男はさ、こんなちまちま手紙書くよか当たって砕けるべきだと思うわけ!!だからそれはどうせ使わないの。というか、俺が持ってるとぜってえ捨てらんないからさ、捨てといてよ』
エンデはくすりと笑った。
『砕けないでね』
ザゼリは目を丸くすると、照れたように頬を掻く。
『ちょっと、後ろ向いていて』
『あ?』
『ちょっとだけ、お願い』
『は?ま、まあいいけど』
ザゼリは大人しく背を向けた。エンデはそっと、しゃがみこむ。眼下には、海の面が揺らめいている。エンデは深呼吸した。目を閉じて、キオのやっていたように、手をそっと、紙の端に当てる。意識を集中させる。
手のひらが、ちりちりと痛んだ。煙の匂いがしたような気がして、目を開ける。線香のように角の所が燃えて、墨になっていた。エンデはその部分を海の水に浸す。
立ちあがって、小さく嘆息した。
『もういいわ、ザゼリさん』
『お?おう』
ザゼリはきょとん、として振り返る。歳も背もエンデよりも大きい彼は、それでいて自分よりもずっと無邪気で可愛い子供のように思えた。
エンデは微笑した。いつから、こんなに、【当たり障りのない】笑顔ができるようになったのだろう。自然に笑えた。口の端の筋肉がひきつることもない。
『もしここに・・・キオ、って子とか、レミオ、って子が来たら・・・伝えておいて。待ってる、って。探しに来て、って。いつまでも、待ってる、って』
ザゼリはお日様のように笑った。
『おー。やっぱあいつらのダチか!伝えとく。あんたもまた遊びに来な、エンデ』
『少しは進展してるといいわね』
エンデが柔らかくほほ笑むと、ザゼリは一瞬きょとん、として、すぐに顔を音が出そうなほどに赤らめた。
『お、お、おおう・・・!!ま、まかしとけ!!』
四、
庭の薔薇は綺麗だ。
レミオには手入れの仕方はよくわからない。これは爺やが趣味で育てている小さな薔薇たちだ。
淡い桃色の、まるでレースのような、紙細工のような薔薇たちがレミオは大好きだった。
刺には気を付けなければいけない。一度思い切り詰まんだら予想以上に痛くて半泣きになった。
自分の家の庭に咲く薔薇は、お店で売ってあるどの薔薇よりも美しいと思う。
レミオは、こんなに可愛らしくて繊細な薔薇を作れる爺やが大好きだった。
我が子を育てているようなものですから、と爺やは笑う。
爺やには子供はいなかったけれど、妻を深く愛しているようだった。
婆やはいつも、レミオに美味しいお菓子を作ってくれる。
レミオはこの老夫婦が大好きだった。
二人がお互いに向けている愛情が羨ましかった。
薔薇は、まるで自分のように思えた。大切に大切に育てられた薔薇はきっと、本当はいつの日にか誰かに、
自分の花婿に摘み取られるのを静かに待っているに違いない。
折って欲しい。
私を静かに手折って欲しい。
「エーンデっ」
ふわり、とエンデの部屋の、小さな窓の縁に腰掛ける。
エンデは何かを熱心に書いていたようだったが、レミオの声に顔を上げた。
「どうかした?」
「うん、なんとなく」
レミオはにこにこする。エンデの表情は変わらない。「ふーん」、と言って、また机の物に姿勢を戻す。
「何を書いているの?いつも」
「お話」
エンデは静かな声で答えた。
まるで水のような声だとレミオは思う。レミオはエンデの声が大好きだ。水のように冷たくて、小さく震えて、澄み切っている。
けれどレミオには、もっともっと、苦しいくらい好きな声があった。
「お話?どんな感じ?」
「笑わない?」
「笑わないわよ」
レミオはくすりと笑った。エンデがむっとする。
「今笑った」
「今のはエンデが可愛かったからだもん」
むう、とものすごくエンデは顔をしかめている。ふと、ザゼリがエンデの眉間の皺を心配していたのを思い出した。エンデにはまだ皺が刻まれてはいないけれど、既にキオには結構深く刻まれている。女の子にあの皺はあまりよろしくない。レミオは柔らかく微笑んだ。
「馬鹿になんかしないわよ」
今度はエンデは困ったような顔をした。レミオには自覚がない。レミオは時偶、普段の惚けた彼女からは想像のつかないような大人びた空気を身に纏うことがある。
「地獄のようなところで、苦しんで、けれど抜け出せなくて、絶望していた男の子がいたの」
エンデは静かに言った。
「何度死にたいかと考えて、けれど神様は決して少年を許してはくださらないの。少年は重い罪を犯してしまったから。神様の物を欲しいと願ってしまったから。そんな絶望の淵にいた彼に、あるとき天窓から白い手が伸びてくるの。その手はひらひらと少年の目の前で手を振った。少年が見上げると、そこにはとても綺麗な、怖いほどに綺麗な妖精がいたの。妖精は少年をその地獄から出してくれた。一緒に逃げてくれるの。ただの気まぐれだった。当然、神様は二人を追いかける。二人は地の果てまで追い詰められていくの」
エンデはふう、とそこで息を継いだ。
「だけどわたし、妖精の気持ちがよくわからないの」
「どうして?妖精が優しい妖精で、その男の子が可哀相だったから、助けてあげようと思ったんじゃないの?素敵なお話だと思うけど」
レミオはにっこりと笑った。エンデは首を振る。
「そんなの在り来たり。妖精ってそんなに純粋じゃないと思うわ。内在的な怖さがあると思うの。気まぐれで始めたことなの。なのにどこまでも一緒に逃げてくれる妖精の気持ちは、少年には理解が不可能なの。だって少年はただの人間だから」
「ふうん・・・」
レミオはエンデを新鮮な気持ちで見つめていた。正直なところ、そういう深い心情表現はレミオには難しすぎてよくわからない。けれど、エンデがレミオにはわからない世界をその中に秘めている、そのことがとても意外で、それでいてしっくりと心に収まる気もして、不思議だった。
「エンデって、すごいのねえ」
「それは褒め言葉?」
「もちろんよ」
レミオは柔らかく笑う。
「だって私には全然理解できないんだもの。だけどエンデには分かっていて、頭の中に広がってるんでしょ?すごいと思うわ」
「ザゼリと似たようなこと言うのね」
エンデは肩をすくめた。
「キオの言ったとおりね、ザゼリとレミオって根本的に似てるんだわ」
エンデは小さく嘆息する。小さな声で付け加えた。
「まあ、そういうとこ嫌いじゃないんだけど」
「根本的に、似てる、かなあ・・・」
レミオも小さく呟いた。きっとエンデには聞き取れなかったに違いない。
「似てないと思うけどなあ」
レミオは両膝を抱え、頬を膝頭に乗せた。
エンデの屋敷が、レミオは好きだ。橙色の煉瓦に緑色の三角屋根。なんだかとても落ち着く気がした。
少なくとも、キオの家の様にレミオの心をかき乱したりはしない。
キオには緑が似合うと思う。本当はとても暖かい人だ。そして、本当は一番物語が似合う人だ。
なのに、ヘラクレイトスの屋敷はごてごてと、金と赤に塗れている。
キオがいつも神経を張っているのではないかと、嫌な気持ちになった。
「それ、誰か模写体がいるの?」
レミオの素朴な疑問に、エンデも静かに答える。
「ただ、思いついただけよ」
どうせ書くのなら、キオの物語を書いてくれればいいのに、とレミオは思った。
胸が痛い。
レミオが生まれたことは、エリュイトス家にとっての誇りだった。
エリュイトスは貴族の中でも高位の家柄だった。昔から何人も、王宮に娘を后として差し出している。
レミオの母は、元々后になるために育てられたグレダリシャ家の子女で、政治的な理由からエリュイトス家に嫁ぐことになったのだと聞いた。母はそのことに内心不満を抱いていたようだった。けれど、レミオを産んだことが母にとっての誉れ、自尊心の保護につながった。
古参の貴族からは風当たりの強いヘラクレイトス家と手を結ぶことを決めたのは父だ。母はそれを酷く嫌がったという。ヘラクレイトス家にとってのもう一つの宝、レミオの片割れと名の由来を揃えたことも、母は嫌った。未だに母はレミオをレミオと呼ばない。代わりに、母の好きな花、百合という意味のピリア、と呼ぶ。それはそれで母からの愛情なのかもしれない、とも思う。そもそもレミオの名は、グレダリシャ家の先祖が住んでいたとされるロルカナの地の伝承からとって付けられた。母からしてみればとても残酷な仕打ちだったろう。しかも提案者はヘラクレイトス家当主ベリエルザの提案だったというから、余計に恨めしかったに違いない。
ロルカナは、現在経典としてまとめられている星神話の、殆どの物語の元が生まれた地だと言われている。今は無きロルカナの民に語り継がれてきたその物語は、双子の英雄神の話の祖であった。ただ、最近の研究で双子神ルフェラとサフィア、英雄レミオとキオは、別人であったとされている。ルフェラとサフィアは帝都アルカイヤを奪還し、世界を統べた。レミオとキオはロルカナを邪神デリエルから解放し、人の世界の礎を作ったとされている。その功績を大神オストロイアに認められ、二人は星となった。今もその二つの星―銀色と緑に輝く二つ星は空で輝いている。
兄レミオの名を与えられたレミオ=エリュイトスは、まだ赤子のうちに、弟の名を与えられたキオ=ヘラクレイトスと婚約させられた。レミオが英雄の兄の名を与えられたのは、エリュイトス家を立ててのことであったかもしれないし、別の地キヲリアの建国者であるキオラの名を意識して、ヘラクレイトス家に暗に先を越された結果かもしれなかった。
母も父も、ヘラクレイトス家のことを本気で信用してはいない。
ベリエルザ=ヘラクレイトスが、先代当主に比べるとうつけもので常識が無いことが、余計にかの家の心証を悪くしていた。その息子キオが妙に理知的で優秀なことも、エリュイトス家だけでなく他の貴族からの反感を買った。
ベリエルザは他人の評価を気にするような男ではなかった。多少小汚い手を使っても伸し上がろうとする男だ。ある意味大物とも言えるのかもしれない。
けれど、その皺寄せが全て息子のキオを縛り付けていたことをレミオは知っている。子供だからこそ見える世界があった。なまじっか何でも卒なくこなせるキオは、その小さな体に見る見るうちに、錆びた枷を増やしていった。
レミオはキオが好きだった。
最初は、ただの一目惚れだったと思う。
物心ついて初めて邂逅したのは、まだたったの7歳の時だ。
それでもひどく惹かれた。
まるで、童話の中に佇む憂いをたたえた少年のように思えた。
自分は、自分だけは、キオを理解できると思った。支えになれると思えた。
けれど、キオは決してレミオがキオの深くに踏み入ることを許さない。
悲しかった。
どうしようもないから、笑うしかない。
エンデと友達になれたことは、レミオにとっても救いだった。
二人だと弾まない話も、
どこか肌寒く感じる時間も、
エンデ一人が加わっただけで、緩やかに流れていく気がした。
今のレミオはエンデがいるから、
エンデがキオを連れて来てくれるから、
笑っていられる。
エンデが好きだ。どうしようもなく好きだ。
キオが、好きだ。
エンデは、せかせかと羽ペンを動かしていた。真っ白な紙は、見る見るうちに黒い文字でびっしりと埋めつくされていく。
まるで、レミオの心のようだ。
私には何もない。
何も誇れるものがない。
キオはエンデばかりを心配する。
あの子は炎に愛されてしまった可哀想な子だから。
炎は誰かを焼き尽くしてしまうから。
とても、危険、な、もの。
私には何もない。
こんな風の力、何の役にも立たない。
誰かを癒すこともできない。
誰かを恐怖させることもできない。
私は出来損ない。
いつも失敗して、キオに怒られる。
けれどキオが怒ってくれるから、それだけで嬉しい。
それが悔しい。
とても、悲しい。
レミオはキオの声が好きだ。
キオの喉が震わせる振動が好きだ。
胸が震える。
体が心地よいと鳴く。
レミオは花火が嫌いだ。
キオがエンデばかり気にかけるから、嫌いだ。
炎を操るからと、全てを諦めたように笑ったエンデが悲しく思えた。
レミオは人を傷つけたことがないからわからない。
どうしてエンデがあんな目をして俯くのかわからなかった。
けれどキオはあの日、あの祭りの日。
花火の上がる建国祭。
エンデを連れ出して、花火を見上げて。
あの時もう、何を信じたらいいかわからなくなった。
レミオは心の奥深くで眠っている。
今でも誰かに、誰かレミオが待ち望む【ただ一人に】、
手折られるのを、待っている。
「あ、そうだ」
エンデがふと、手を止めて振り返った。
「来週だね」
エンデはとても柔らかく笑った。この子がこんな風にちゃんと笑うのは珍しい。普段はほとんど表情がない。
だから、エンデがそれで笑顔になるのなら、それだけのためならレミオだって、好きになれた。
「そうね、今年の花火は三千発だって。気合入ってるわね」
レミオも微笑む。
胸のざわつきは、とうの昔に消えている。
エンデの笑顔が大好きだ。
エンデがいてくれるからきっと、レミオも笑っていられる。
飲み込まれないでいられる。
エンデが好きだから。
それでもキオが、好きだから。
ふと、去年の花火の日を思い出す。
人ごみに流され、二人とはぐれた自分を、見たことのない、ごてごての衣装を着た女の子が助けてくれた。
あの時は、この手がキオだったらどんなに良かっただろうと思ったけれど。
『ああ、花火、終わっちゃったね』
『・・・どうした?』
『いいの。どうせ、嫌いだし』
『嫌い?あんなに綺麗なのに?』
『だから嫌いなの』
『そう?』
『うん。だって、火と光だけであんな綺麗だなんて、反則だもの。まるでもう他のものは必要ないみたいで怖くなるんだもの』
『ふうん』
『でもさ、火って、空気がないと燃えないんだよ』
『そして、みんなその空気すって、花火を見て、綺麗だねって言って、生きてるでしょ』
『綺麗だっていう人が誰もいなかったら、花火なんて何の意味もない』
『要らないものなんてきっとないよ』
「空気」
「え?」
レミオの呟きに、エンデが眉をひそめる。
「どうしたの?」
レミオは肩を小さくすくめる。
「ううん、なんでもない。ただちょっと」
「ちょっと、何?」
「去年の花火の時、通りすがりに会った観光客の子思い出して」
レミオはにっこりと笑った。
「また会えるといいなあ」
「まあ、観光客なら、今年も来るかどうかは五分五分だろうけどね」
エンデはさらりと言った。
庭の薔薇は綺麗だ。
レミオには手入れの仕方はよくわからない。これは爺やが趣味で育てている小さな薔薇たちだ。
淡い桃色の、まるでレースのような、紙細工のような薔薇たちがレミオは大好きだった。
刺には気を付けなければいけない。一度思い切り詰まんだら予想以上に痛くて半泣きになった。
自分の家の庭に咲く薔薇は、お店で売ってあるどの薔薇よりも美しいと思う。
レミオは、こんなに可愛らしくて繊細な薔薇を作れる爺やが大好きだった。
我が子を育てているようなものですから、と爺やは笑う。
爺やには子供はいなかったけれど、妻を深く愛しているようだった。
婆やはいつも、レミオに美味しいお菓子を作ってくれる。
レミオはこの老夫婦が大好きだった。
二人がお互いに向けている愛情が羨ましかった。
薔薇は、まるで自分のように思えた。大切に大切に育てられた薔薇はきっと、本当はいつの日にか誰かに、
自分の花婿に摘み取られるのを静かに待っているに違いない。
折って欲しい。
私を静かに手折って欲しい。
「エーンデっ」
ふわり、とエンデの部屋の、小さな窓の縁に腰掛ける。
エンデは何かを熱心に書いていたようだったが、レミオの声に顔を上げた。
「どうかした?」
「うん、なんとなく」
レミオはにこにこする。エンデの表情は変わらない。「ふーん」、と言って、また机の物に姿勢を戻す。
「何を書いているの?いつも」
「お話」
エンデは静かな声で答えた。
まるで水のような声だとレミオは思う。レミオはエンデの声が大好きだ。水のように冷たくて、小さく震えて、澄み切っている。
けれどレミオには、もっともっと、苦しいくらい好きな声があった。
「お話?どんな感じ?」
「笑わない?」
「笑わないわよ」
レミオはくすりと笑った。エンデがむっとする。
「今笑った」
「今のはエンデが可愛かったからだもん」
むう、とものすごくエンデは顔をしかめている。ふと、ザゼリがエンデの眉間の皺を心配していたのを思い出した。エンデにはまだ皺が刻まれてはいないけれど、既にキオには結構深く刻まれている。女の子にあの皺はあまりよろしくない。レミオは柔らかく微笑んだ。
「馬鹿になんかしないわよ」
今度はエンデは困ったような顔をした。レミオには自覚がない。レミオは時偶、普段の惚けた彼女からは想像のつかないような大人びた空気を身に纏うことがある。
「地獄のようなところで、苦しんで、けれど抜け出せなくて、絶望していた男の子がいたの」
エンデは静かに言った。
「何度死にたいかと考えて、けれど神様は決して少年を許してはくださらないの。少年は重い罪を犯してしまったから。神様の物を欲しいと願ってしまったから。そんな絶望の淵にいた彼に、あるとき天窓から白い手が伸びてくるの。その手はひらひらと少年の目の前で手を振った。少年が見上げると、そこにはとても綺麗な、怖いほどに綺麗な妖精がいたの。妖精は少年をその地獄から出してくれた。一緒に逃げてくれるの。ただの気まぐれだった。当然、神様は二人を追いかける。二人は地の果てまで追い詰められていくの」
エンデはふう、とそこで息を継いだ。
「だけどわたし、妖精の気持ちがよくわからないの」
「どうして?妖精が優しい妖精で、その男の子が可哀相だったから、助けてあげようと思ったんじゃないの?素敵なお話だと思うけど」
レミオはにっこりと笑った。エンデは首を振る。
「そんなの在り来たり。妖精ってそんなに純粋じゃないと思うわ。内在的な怖さがあると思うの。気まぐれで始めたことなの。なのにどこまでも一緒に逃げてくれる妖精の気持ちは、少年には理解が不可能なの。だって少年はただの人間だから」
「ふうん・・・」
レミオはエンデを新鮮な気持ちで見つめていた。正直なところ、そういう深い心情表現はレミオには難しすぎてよくわからない。けれど、エンデがレミオにはわからない世界をその中に秘めている、そのことがとても意外で、それでいてしっくりと心に収まる気もして、不思議だった。
「エンデって、すごいのねえ」
「それは褒め言葉?」
「もちろんよ」
レミオは柔らかく笑う。
「だって私には全然理解できないんだもの。だけどエンデには分かっていて、頭の中に広がってるんでしょ?すごいと思うわ」
「ザゼリと似たようなこと言うのね」
エンデは肩をすくめた。
「キオの言ったとおりね、ザゼリとレミオって根本的に似てるんだわ」
エンデは小さく嘆息する。小さな声で付け加えた。
「まあ、そういうとこ嫌いじゃないんだけど」
「根本的に、似てる、かなあ・・・」
レミオも小さく呟いた。きっとエンデには聞き取れなかったに違いない。
「似てないと思うけどなあ」
レミオは両膝を抱え、頬を膝頭に乗せた。
エンデの屋敷が、レミオは好きだ。橙色の煉瓦に緑色の三角屋根。なんだかとても落ち着く気がした。
少なくとも、キオの家の様にレミオの心をかき乱したりはしない。
キオには緑が似合うと思う。本当はとても暖かい人だ。そして、本当は一番物語が似合う人だ。
なのに、ヘラクレイトスの屋敷はごてごてと、金と赤に塗れている。
キオがいつも神経を張っているのではないかと、嫌な気持ちになった。
「それ、誰か模写体がいるの?」
レミオの素朴な疑問に、エンデも静かに答える。
「ただ、思いついただけよ」
どうせ書くのなら、キオの物語を書いてくれればいいのに、とレミオは思った。
胸が痛い。
レミオが生まれたことは、エリュイトス家にとっての誇りだった。
エリュイトスは貴族の中でも高位の家柄だった。昔から何人も、王宮に娘を后として差し出している。
レミオの母は、元々后になるために育てられたグレダリシャ家の子女で、政治的な理由からエリュイトス家に嫁ぐことになったのだと聞いた。母はそのことに内心不満を抱いていたようだった。けれど、レミオを産んだことが母にとっての誉れ、自尊心の保護につながった。
古参の貴族からは風当たりの強いヘラクレイトス家と手を結ぶことを決めたのは父だ。母はそれを酷く嫌がったという。ヘラクレイトス家にとってのもう一つの宝、レミオの片割れと名の由来を揃えたことも、母は嫌った。未だに母はレミオをレミオと呼ばない。代わりに、母の好きな花、百合という意味のピリア、と呼ぶ。それはそれで母からの愛情なのかもしれない、とも思う。そもそもレミオの名は、グレダリシャ家の先祖が住んでいたとされるロルカナの地の伝承からとって付けられた。母からしてみればとても残酷な仕打ちだったろう。しかも提案者はヘラクレイトス家当主ベリエルザの提案だったというから、余計に恨めしかったに違いない。
ロルカナは、現在経典としてまとめられている星神話の、殆どの物語の元が生まれた地だと言われている。今は無きロルカナの民に語り継がれてきたその物語は、双子の英雄神の話の祖であった。ただ、最近の研究で双子神ルフェラとサフィア、英雄レミオとキオは、別人であったとされている。ルフェラとサフィアは帝都アルカイヤを奪還し、世界を統べた。レミオとキオはロルカナを邪神デリエルから解放し、人の世界の礎を作ったとされている。その功績を大神オストロイアに認められ、二人は星となった。今もその二つの星―銀色と緑に輝く二つ星は空で輝いている。
兄レミオの名を与えられたレミオ=エリュイトスは、まだ赤子のうちに、弟の名を与えられたキオ=ヘラクレイトスと婚約させられた。レミオが英雄の兄の名を与えられたのは、エリュイトス家を立ててのことであったかもしれないし、別の地キヲリアの建国者であるキオラの名を意識して、ヘラクレイトス家に暗に先を越された結果かもしれなかった。
母も父も、ヘラクレイトス家のことを本気で信用してはいない。
ベリエルザ=ヘラクレイトスが、先代当主に比べるとうつけもので常識が無いことが、余計にかの家の心証を悪くしていた。その息子キオが妙に理知的で優秀なことも、エリュイトス家だけでなく他の貴族からの反感を買った。
ベリエルザは他人の評価を気にするような男ではなかった。多少小汚い手を使っても伸し上がろうとする男だ。ある意味大物とも言えるのかもしれない。
けれど、その皺寄せが全て息子のキオを縛り付けていたことをレミオは知っている。子供だからこそ見える世界があった。なまじっか何でも卒なくこなせるキオは、その小さな体に見る見るうちに、錆びた枷を増やしていった。
レミオはキオが好きだった。
最初は、ただの一目惚れだったと思う。
物心ついて初めて邂逅したのは、まだたったの7歳の時だ。
それでもひどく惹かれた。
まるで、童話の中に佇む憂いをたたえた少年のように思えた。
自分は、自分だけは、キオを理解できると思った。支えになれると思えた。
けれど、キオは決してレミオがキオの深くに踏み入ることを許さない。
悲しかった。
どうしようもないから、笑うしかない。
エンデと友達になれたことは、レミオにとっても救いだった。
二人だと弾まない話も、
どこか肌寒く感じる時間も、
エンデ一人が加わっただけで、緩やかに流れていく気がした。
今のレミオはエンデがいるから、
エンデがキオを連れて来てくれるから、
笑っていられる。
エンデが好きだ。どうしようもなく好きだ。
キオが、好きだ。
エンデは、せかせかと羽ペンを動かしていた。真っ白な紙は、見る見るうちに黒い文字でびっしりと埋めつくされていく。
まるで、レミオの心のようだ。
私には何もない。
何も誇れるものがない。
キオはエンデばかりを心配する。
あの子は炎に愛されてしまった可哀想な子だから。
炎は誰かを焼き尽くしてしまうから。
とても、危険、な、もの。
私には何もない。
こんな風の力、何の役にも立たない。
誰かを癒すこともできない。
誰かを恐怖させることもできない。
私は出来損ない。
いつも失敗して、キオに怒られる。
けれどキオが怒ってくれるから、それだけで嬉しい。
それが悔しい。
とても、悲しい。
レミオはキオの声が好きだ。
キオの喉が震わせる振動が好きだ。
胸が震える。
体が心地よいと鳴く。
レミオは花火が嫌いだ。
キオがエンデばかり気にかけるから、嫌いだ。
炎を操るからと、全てを諦めたように笑ったエンデが悲しく思えた。
レミオは人を傷つけたことがないからわからない。
どうしてエンデがあんな目をして俯くのかわからなかった。
けれどキオはあの日、あの祭りの日。
花火の上がる建国祭。
エンデを連れ出して、花火を見上げて。
あの時もう、何を信じたらいいかわからなくなった。
レミオは心の奥深くで眠っている。
今でも誰かに、誰かレミオが待ち望む【ただ一人に】、
手折られるのを、待っている。
「あ、そうだ」
エンデがふと、手を止めて振り返った。
「来週だね」
エンデはとても柔らかく笑った。この子がこんな風にちゃんと笑うのは珍しい。普段はほとんど表情がない。
だから、エンデがそれで笑顔になるのなら、それだけのためならレミオだって、好きになれた。
「そうね、今年の花火は三千発だって。気合入ってるわね」
レミオも微笑む。
胸のざわつきは、とうの昔に消えている。
エンデの笑顔が大好きだ。
エンデがいてくれるからきっと、レミオも笑っていられる。
飲み込まれないでいられる。
エンデが好きだから。
それでもキオが、好きだから。
ふと、去年の花火の日を思い出す。
人ごみに流され、二人とはぐれた自分を、見たことのない、ごてごての衣装を着た女の子が助けてくれた。
あの時は、この手がキオだったらどんなに良かっただろうと思ったけれど。
『ああ、花火、終わっちゃったね』
『・・・どうした?』
『いいの。どうせ、嫌いだし』
『嫌い?あんなに綺麗なのに?』
『だから嫌いなの』
『そう?』
『うん。だって、火と光だけであんな綺麗だなんて、反則だもの。まるでもう他のものは必要ないみたいで怖くなるんだもの』
『ふうん』
『でもさ、火って、空気がないと燃えないんだよ』
『そして、みんなその空気すって、花火を見て、綺麗だねって言って、生きてるでしょ』
『綺麗だっていう人が誰もいなかったら、花火なんて何の意味もない』
『要らないものなんてきっとないよ』
「空気」
「え?」
レミオの呟きに、エンデが眉をひそめる。
「どうしたの?」
レミオは肩を小さくすくめる。
「ううん、なんでもない。ただちょっと」
「ちょっと、何?」
「去年の花火の時、通りすがりに会った観光客の子思い出して」
レミオはにっこりと笑った。
「また会えるといいなあ」
「まあ、観光客なら、今年も来るかどうかは五分五分だろうけどね」
エンデはさらりと言った。
五、
城下に広がる町には、新鮮な空気があふれている。
焼けた甘いパンの匂い、水で無造作に洗われた野菜の匂い、少しだけ血の味を連想させる、生臭い魚の匂い。
男の匂い、女の匂い。母親の匂い、子供の匂い、年寄りの匂い。
綺麗に磨かれた清潔な香り。垂れ流したままの汚物の匂い。
それら全てがキオの鼻をつき、生きていると知らせてくれる。
大げさかもしれない。そんなことは分かっている。
けれど、閉ざされた窓の奥で、人工的に灯された明かりの下で、既製品として作られたペンを握って文字を書く日常よりもずっと、日のあたる場所で餓鬼のように土に木の棒で絵ともいえない代物を描いたり、他にないからと果汁の余りや魚の血でとりあえず文字を書く、そういう街の庶民の動作が好きだった。綺麗なようで汚い。汚いようで磨かれている。
こういう暮らしがあるのだと、見せてくれたのはレミオだった。正しく言うなら、ふらふらと庶民の街に迷い込んだ彼女の捜索隊にちゃっかり自分も紛れ込んだだけだったが。
けれど、新しい発見だった。あの造られた邸から抜け出すこと、自分の足で歩くこと、思いもつかなかった。言われるままに背中を押され、差し出された手をとり、ただ馬車に乗るだけ。特に景色にも興味はなかった。どうせ自分とは無縁の世界だ。キオの関心を引いたのはただ、馬車の天井の角、つなぎ目部分にあるちょっとした錆だった。どうせここからは出ていいと言われなければ出られない。出たいとも思わない。なぜなら、いきなり一人で外に放り出されても何処へ行けばいいのか分からないのだし。
レミオを探しに行ったのは単なる気まぐれだった。レミオは正真正銘の阿呆だと思う。どうせぼけっとしていて邸から出て戻ってこれなくなったんだろう、と思った。途方に暮れてべそをかいているなら、その面を思い切り小馬鹿にした目で笑いくだしてやりたいと思った。もし泣きもせずぼけっとしているならそれはそれで面白い。退屈しのぎにはなる。なんだかんだでキオは別にレミオを嫌っているわけじゃなかった。だから別に、怒るのも本気なわけではない。けれど、レミオのへまやぼけに少しずつ怒鳴っていくうちに、気づいた。自分にはこんなにも揺らぐ気持ちがあったのだと。本当は苛々したかったのだということ。けれどただの怒りは自分の内に溜まるだけだ。やがて自分を蝕むだけだ。だから怒らなかった。いつも静かに、ただ静かな気持ちで生きていれば苦しいことも悲しいこともない。抑えろ。抑えるんだ。動じることなどみっともない。ほら見てみろ、僕の父親は怒る時唾を飛ばす。なんて醜い。あんな風にはなりたくない。汚い。
けれど、本当はただ分からなくなっていただけなのかもしれない。今でも父親の癖は好きじゃない。不快感しか起こらない。それでも何か情はあって、たまに哀れになり、たまに可愛いなとも思う。不思議だと思う。気を使っていたことだけは確かだと思う。無意識にそれを覚えたのか、それとも言うことを聞けと以前怒られたことがあったのか、もう覚えていない。けれど不思議だった。どうしてレミオは笑うのだろう。泣くのだろう。あんなにぼんやりしているのだろう。危ないのに。ほら、また躓いた。危ない。危ない?
どうして危ないと思うのだろう。
不思議だった。いつの間にか、自分とはまるっきり違う奇妙な少女を目で追うようになっていた。そしていつしか、情までわくなんて。危ない、だなんて、心配にまでなるなんて。
怒鳴るのは体力が要る。苛つくのも体力を奪っていく。けれど、感情を爆発させ、ぶつけられるのはレミオだけだった。レミオになら何をしたっていい気がする。いいはけ口だ。そしてそういう自分が好きだ。いつの間にか好きになっていた。
たまに、やりすぎたかなとか、言い過ぎたかな、と思う時もある。けれどレミオは必ずふにゃりと笑った。どうでもいい。どうしたらいいのか分からないから、どうでもいい。
もう少し大人になったら、対処の仕方も、後始末の仕方もわかるんだろうか、とぼんやりと考えている。
ザゼリと会ったのも、レミオのおかげだったかもしれない。
馬鹿のレミオは港に散乱していた箱にもたれかかって、出っ張っていた釘で手を刺した。ものすごく泣いた。慌てて駆け寄って来たのがザゼリだ。鉄錆が体に入ったらどうするんだと思った。呆れてものもいえない。ザゼリはものすごくあたふたして、途中何度も荷物にけつまづいて、包帯の巻き方もがたがただった。自分のことじゃないのに、痛いよね、痛いよね、とぽろぽろ涙を流して消毒液をぼたぼた腕の方に垂れるくらい塗りたくった。
変な奴だな、と思った。どうしてレミオはいつも、僕に新鮮なものを運んでくるんだろう。こんななよなよした男、見たことがない。
興味が出たのは、ザゼリがレミオにどこか似ていて、しかも男だったからかもしれない。ザゼリは自分の知っていた男どものどれとも違っていた。ひょろひょろともやしのように頼りない。そばかすだらけのしまりのない顔と表情。どこどこのお嬢さんが可愛いだの、惚れた腫れただの、常に嬉しそうに話しては振られたと落ち込む。花束を渡そうとして、安い花を握り締めながら電柱の陰から相手を見つめているのを見た時にはさすがに引いた。酷い猫背だ。老婆のように腰が曲がった背中で、おどおどと相手を見つめている。そして嬉しそうに幸せそうにへらへらと笑っている。
「キオ、最近姿勢悪いよ?」
ザゼリは船から下ろした荷物をどさり、と床に置いて腰をそらした。
「あー、腰いてえ・・・」
「お前のが移ったんだよ。責任とれよこの野郎」
「は?え、でも、ええ?おれのせいぃ?」
ザゼリは頭を掻いた。キオと背中あわせに樽の上に座っていたエンデがこん、と後頭部をキオにぶつけてくる。背中に重みが加わった。
「疲れた」
「んだよ、もう根あげてんの?」
「編み方が難しい」
「絡ませたのはあんたらだろ。手伝ってやってんだからありがたく思えよ」
「わたしよりもキオの方が目数少ないじゃない。わたしはこれだけやったのよ?」
エンデは編み終わった綱を広げる。
「自業自得だろ」
キオが言うと、少し気分を害したらしいエンデは黙り込んで、また作業にとりかかった。ザゼリは目をこする。
「それにしても、レミオならわかるけど、エンデがへまをするって珍しいね?」
「半分はわたしのせいだもの、つまづいたから・・・」
床に座り込んでほつれた網目を直していたレミオが申し訳なさそうに言う。キオはつっこまずにはいられなかった。
「いや、お前、半分って。謙虚さ少しは学べ」
つっこんでしまってから、どうして自分は声を出すという面倒な動作をしてしまったのだろうとぼんやり考える。
ザゼリが思い出し笑いで噴き出した。肩が小刻みに揺れる。エンデが真っ赤になったのが首越しに伝わった。熱い。
「あんま笑ってやんなよ」
小さな声でキオは言う。
「だってさ、思わないじゃない、綱の網目の中にすっぽり、狙ったみたいに挟まるとかありえないだろ?いやああれは可愛かった。そして面白かった」
元々緩くなっていた網目の間に挟まったのはエンデだ。こけそうになったレミオの服を掴み、傍にあった綱をとっさに掴んだ。きちんと巻かれていた綱が一気にたるんで、二人してよろめいた。しかもレミオも綱を引っ張った。多分穴を広げたのはレミオの腕だったと思う。そこから慌てて手を抜こうとして、その手はエンデにしたたかにぶつかり、エンデはよろけて肩からその穴に突っ込んだ。そのあとたくさんの綱が落ちてきて、レミオの体に巻き付いた。もがくから余計に辺に結び目ができて、二人をそこから助け出すのも一苦労だった。周りは大爆笑だ。顔が火照りそうになって、キオは何とかこらえた。ここはきっと、呆れかえった方が二人のためだ。二人の皮膚が硬い綱に擦られてあちこち擦り向けていたのに少し胸が痛んだ気もしたが、ザゼリが自分の代わりに顔を真っ赤にして焦っていたので自分はもう気にしないことにした。
「しかもレミオはレミオでまるで蓑虫みたいな恰好なんだもんな。まったくほんとに。あんなのもう二度と見れない気がする」
ザゼリはまだ笑っている。そしてふと気がついた。
「エンデ、指の皮剥けてる。無理すんなよ」
「いいの。終わらないんだもの」
「血でてるじゃん。とりあえず消毒しろって。ここの物大して綺麗じゃないんだぜ」
「いいんだってば」
エンデの声は普段通りだ。淡々と静かで、抑揚すらない。けれど、言葉遣いがなんとなく違う気がした。どこがどう違うだなんて、キオには説明できない。ただ、声を出すことがためらわれる。不思議だ。
ザゼリは肩をすくめた。ただでさえ狭い樽の上に自分も腰かける。キオは意地でも場所を譲らなかった。なんとなく負けな気がしたからだ。結局少しずれたのはエンデだ。エンデが振り返って少し睨んできた気がした。ほんの少し心が跳ねた。びっくりしたのだ。エンデが感情を高ぶらせるなんて、めったにないことだ。いや、ほぼないことだ。
ザゼリはそのままただエンデの手元を眺めていた。何をするでもない。エンデも黙々と、先刻教えられた通りにほどけた五本の細い糸を固く編んでいく。
とても穏やかだ。肩に触れるザゼリの体温。背中に触れているエンデ。なんとなくキオの心は穏やかだった。こういう時間はなぜか嫌いじゃなかった。なんとなく、むずかゆくなってくる。けれど絶対に意地でもどいてなんかやらない。このままの風が好きだ。
ふと、キオは一人だけじべたにしゃがみこんで綱を編んでいるレミオを見やった。いつもならうんうん唸りながら作業をしているのに、先刻までそうだったのに、レミオは全く声を発しない。首が酷く曲がっている。流れた髪で顔は見えなかった。レミオにしては珍しく、空気を読んでいるんだろうかと思った。けれど、それにしても不自然に静かすぎる気がした。見なければ気づかないほどに空気に溶け込んでいる違和感。とはいえキオには関係ない。どうでもいいのだ。どうせレミオは何も考えちゃいないし、どうせすぐに忘れる。自分と違って、心に浮かんだことは染みだすように空気に溶けて消えていくのだ。構ってやろうとは思わない。構うと楽しいのはザゼリの方だからだ。それにエンデが付け加えられるとなお面白い。
顔にザゼリのおくれ毛がかぶさって来た。なんとなくキオはそれを指に巻き付けいじる。ザゼリがキオの方に顔を向けてきょとん、とした。とても可愛い表情だと思う。年上だけど。
「どうした?」
「別に?」
ザゼリはくすり、と笑った。今度はキオの手元を眺める。やがて目を閉じて顎を空に向けた。気持ち良さそうに風の匂いを嗅いでいる。
「お前さぁ、髪だけは綺麗だよな、いっちょ前に」
キオが言うと、ザゼリはのんびりした声で笑った。
「なんだよいっちょまえって。ひでえなあ」
綺麗だな、と思う。キオはエンデの背中にもたれかかった。エンデは何も言わない。そのまま支えてくれている。
キオはザゼリの金髪の束を空に向かってすかした。明るい。とても薄くて明るいそれは、心をなんとなく晴らしてくれる。キオは髪を手から離すと、ふう、と息をついて空を仰ぎ、自分も目を閉じた。
明るい。
自分を包む日の光も、この世の光も、自分を照らしてくれる。頬がぽかぽかと暖かくなる。いつか心臓が光の熱で焼かれればいいと思った。焼け焦げればいい。この日々が続くなら、きっと耐えられる。いつかもし、ヘラクレイトスの掟が自分達を阻みそうになるなら、この心臓ごと、あいつらを焼き焦がしてやる。
キオはとても満足していた。レミオに感謝してやってもいい。けれど絶対に、意地でも口には出してやらない。
城下に広がる町には、新鮮な空気があふれている。
焼けた甘いパンの匂い、水で無造作に洗われた野菜の匂い、少しだけ血の味を連想させる、生臭い魚の匂い。
男の匂い、女の匂い。母親の匂い、子供の匂い、年寄りの匂い。
綺麗に磨かれた清潔な香り。垂れ流したままの汚物の匂い。
それら全てがキオの鼻をつき、生きていると知らせてくれる。
大げさかもしれない。そんなことは分かっている。
けれど、閉ざされた窓の奥で、人工的に灯された明かりの下で、既製品として作られたペンを握って文字を書く日常よりもずっと、日のあたる場所で餓鬼のように土に木の棒で絵ともいえない代物を描いたり、他にないからと果汁の余りや魚の血でとりあえず文字を書く、そういう街の庶民の動作が好きだった。綺麗なようで汚い。汚いようで磨かれている。
こういう暮らしがあるのだと、見せてくれたのはレミオだった。正しく言うなら、ふらふらと庶民の街に迷い込んだ彼女の捜索隊にちゃっかり自分も紛れ込んだだけだったが。
けれど、新しい発見だった。あの造られた邸から抜け出すこと、自分の足で歩くこと、思いもつかなかった。言われるままに背中を押され、差し出された手をとり、ただ馬車に乗るだけ。特に景色にも興味はなかった。どうせ自分とは無縁の世界だ。キオの関心を引いたのはただ、馬車の天井の角、つなぎ目部分にあるちょっとした錆だった。どうせここからは出ていいと言われなければ出られない。出たいとも思わない。なぜなら、いきなり一人で外に放り出されても何処へ行けばいいのか分からないのだし。
レミオを探しに行ったのは単なる気まぐれだった。レミオは正真正銘の阿呆だと思う。どうせぼけっとしていて邸から出て戻ってこれなくなったんだろう、と思った。途方に暮れてべそをかいているなら、その面を思い切り小馬鹿にした目で笑いくだしてやりたいと思った。もし泣きもせずぼけっとしているならそれはそれで面白い。退屈しのぎにはなる。なんだかんだでキオは別にレミオを嫌っているわけじゃなかった。だから別に、怒るのも本気なわけではない。けれど、レミオのへまやぼけに少しずつ怒鳴っていくうちに、気づいた。自分にはこんなにも揺らぐ気持ちがあったのだと。本当は苛々したかったのだということ。けれどただの怒りは自分の内に溜まるだけだ。やがて自分を蝕むだけだ。だから怒らなかった。いつも静かに、ただ静かな気持ちで生きていれば苦しいことも悲しいこともない。抑えろ。抑えるんだ。動じることなどみっともない。ほら見てみろ、僕の父親は怒る時唾を飛ばす。なんて醜い。あんな風にはなりたくない。汚い。
けれど、本当はただ分からなくなっていただけなのかもしれない。今でも父親の癖は好きじゃない。不快感しか起こらない。それでも何か情はあって、たまに哀れになり、たまに可愛いなとも思う。不思議だと思う。気を使っていたことだけは確かだと思う。無意識にそれを覚えたのか、それとも言うことを聞けと以前怒られたことがあったのか、もう覚えていない。けれど不思議だった。どうしてレミオは笑うのだろう。泣くのだろう。あんなにぼんやりしているのだろう。危ないのに。ほら、また躓いた。危ない。危ない?
どうして危ないと思うのだろう。
不思議だった。いつの間にか、自分とはまるっきり違う奇妙な少女を目で追うようになっていた。そしていつしか、情までわくなんて。危ない、だなんて、心配にまでなるなんて。
怒鳴るのは体力が要る。苛つくのも体力を奪っていく。けれど、感情を爆発させ、ぶつけられるのはレミオだけだった。レミオになら何をしたっていい気がする。いいはけ口だ。そしてそういう自分が好きだ。いつの間にか好きになっていた。
たまに、やりすぎたかなとか、言い過ぎたかな、と思う時もある。けれどレミオは必ずふにゃりと笑った。どうでもいい。どうしたらいいのか分からないから、どうでもいい。
もう少し大人になったら、対処の仕方も、後始末の仕方もわかるんだろうか、とぼんやりと考えている。
ザゼリと会ったのも、レミオのおかげだったかもしれない。
馬鹿のレミオは港に散乱していた箱にもたれかかって、出っ張っていた釘で手を刺した。ものすごく泣いた。慌てて駆け寄って来たのがザゼリだ。鉄錆が体に入ったらどうするんだと思った。呆れてものもいえない。ザゼリはものすごくあたふたして、途中何度も荷物にけつまづいて、包帯の巻き方もがたがただった。自分のことじゃないのに、痛いよね、痛いよね、とぽろぽろ涙を流して消毒液をぼたぼた腕の方に垂れるくらい塗りたくった。
変な奴だな、と思った。どうしてレミオはいつも、僕に新鮮なものを運んでくるんだろう。こんななよなよした男、見たことがない。
興味が出たのは、ザゼリがレミオにどこか似ていて、しかも男だったからかもしれない。ザゼリは自分の知っていた男どものどれとも違っていた。ひょろひょろともやしのように頼りない。そばかすだらけのしまりのない顔と表情。どこどこのお嬢さんが可愛いだの、惚れた腫れただの、常に嬉しそうに話しては振られたと落ち込む。花束を渡そうとして、安い花を握り締めながら電柱の陰から相手を見つめているのを見た時にはさすがに引いた。酷い猫背だ。老婆のように腰が曲がった背中で、おどおどと相手を見つめている。そして嬉しそうに幸せそうにへらへらと笑っている。
「キオ、最近姿勢悪いよ?」
ザゼリは船から下ろした荷物をどさり、と床に置いて腰をそらした。
「あー、腰いてえ・・・」
「お前のが移ったんだよ。責任とれよこの野郎」
「は?え、でも、ええ?おれのせいぃ?」
ザゼリは頭を掻いた。キオと背中あわせに樽の上に座っていたエンデがこん、と後頭部をキオにぶつけてくる。背中に重みが加わった。
「疲れた」
「んだよ、もう根あげてんの?」
「編み方が難しい」
「絡ませたのはあんたらだろ。手伝ってやってんだからありがたく思えよ」
「わたしよりもキオの方が目数少ないじゃない。わたしはこれだけやったのよ?」
エンデは編み終わった綱を広げる。
「自業自得だろ」
キオが言うと、少し気分を害したらしいエンデは黙り込んで、また作業にとりかかった。ザゼリは目をこする。
「それにしても、レミオならわかるけど、エンデがへまをするって珍しいね?」
「半分はわたしのせいだもの、つまづいたから・・・」
床に座り込んでほつれた網目を直していたレミオが申し訳なさそうに言う。キオはつっこまずにはいられなかった。
「いや、お前、半分って。謙虚さ少しは学べ」
つっこんでしまってから、どうして自分は声を出すという面倒な動作をしてしまったのだろうとぼんやり考える。
ザゼリが思い出し笑いで噴き出した。肩が小刻みに揺れる。エンデが真っ赤になったのが首越しに伝わった。熱い。
「あんま笑ってやんなよ」
小さな声でキオは言う。
「だってさ、思わないじゃない、綱の網目の中にすっぽり、狙ったみたいに挟まるとかありえないだろ?いやああれは可愛かった。そして面白かった」
元々緩くなっていた網目の間に挟まったのはエンデだ。こけそうになったレミオの服を掴み、傍にあった綱をとっさに掴んだ。きちんと巻かれていた綱が一気にたるんで、二人してよろめいた。しかもレミオも綱を引っ張った。多分穴を広げたのはレミオの腕だったと思う。そこから慌てて手を抜こうとして、その手はエンデにしたたかにぶつかり、エンデはよろけて肩からその穴に突っ込んだ。そのあとたくさんの綱が落ちてきて、レミオの体に巻き付いた。もがくから余計に辺に結び目ができて、二人をそこから助け出すのも一苦労だった。周りは大爆笑だ。顔が火照りそうになって、キオは何とかこらえた。ここはきっと、呆れかえった方が二人のためだ。二人の皮膚が硬い綱に擦られてあちこち擦り向けていたのに少し胸が痛んだ気もしたが、ザゼリが自分の代わりに顔を真っ赤にして焦っていたので自分はもう気にしないことにした。
「しかもレミオはレミオでまるで蓑虫みたいな恰好なんだもんな。まったくほんとに。あんなのもう二度と見れない気がする」
ザゼリはまだ笑っている。そしてふと気がついた。
「エンデ、指の皮剥けてる。無理すんなよ」
「いいの。終わらないんだもの」
「血でてるじゃん。とりあえず消毒しろって。ここの物大して綺麗じゃないんだぜ」
「いいんだってば」
エンデの声は普段通りだ。淡々と静かで、抑揚すらない。けれど、言葉遣いがなんとなく違う気がした。どこがどう違うだなんて、キオには説明できない。ただ、声を出すことがためらわれる。不思議だ。
ザゼリは肩をすくめた。ただでさえ狭い樽の上に自分も腰かける。キオは意地でも場所を譲らなかった。なんとなく負けな気がしたからだ。結局少しずれたのはエンデだ。エンデが振り返って少し睨んできた気がした。ほんの少し心が跳ねた。びっくりしたのだ。エンデが感情を高ぶらせるなんて、めったにないことだ。いや、ほぼないことだ。
ザゼリはそのままただエンデの手元を眺めていた。何をするでもない。エンデも黙々と、先刻教えられた通りにほどけた五本の細い糸を固く編んでいく。
とても穏やかだ。肩に触れるザゼリの体温。背中に触れているエンデ。なんとなくキオの心は穏やかだった。こういう時間はなぜか嫌いじゃなかった。なんとなく、むずかゆくなってくる。けれど絶対に意地でもどいてなんかやらない。このままの風が好きだ。
ふと、キオは一人だけじべたにしゃがみこんで綱を編んでいるレミオを見やった。いつもならうんうん唸りながら作業をしているのに、先刻までそうだったのに、レミオは全く声を発しない。首が酷く曲がっている。流れた髪で顔は見えなかった。レミオにしては珍しく、空気を読んでいるんだろうかと思った。けれど、それにしても不自然に静かすぎる気がした。見なければ気づかないほどに空気に溶け込んでいる違和感。とはいえキオには関係ない。どうでもいいのだ。どうせレミオは何も考えちゃいないし、どうせすぐに忘れる。自分と違って、心に浮かんだことは染みだすように空気に溶けて消えていくのだ。構ってやろうとは思わない。構うと楽しいのはザゼリの方だからだ。それにエンデが付け加えられるとなお面白い。
顔にザゼリのおくれ毛がかぶさって来た。なんとなくキオはそれを指に巻き付けいじる。ザゼリがキオの方に顔を向けてきょとん、とした。とても可愛い表情だと思う。年上だけど。
「どうした?」
「別に?」
ザゼリはくすり、と笑った。今度はキオの手元を眺める。やがて目を閉じて顎を空に向けた。気持ち良さそうに風の匂いを嗅いでいる。
「お前さぁ、髪だけは綺麗だよな、いっちょ前に」
キオが言うと、ザゼリはのんびりした声で笑った。
「なんだよいっちょまえって。ひでえなあ」
綺麗だな、と思う。キオはエンデの背中にもたれかかった。エンデは何も言わない。そのまま支えてくれている。
キオはザゼリの金髪の束を空に向かってすかした。明るい。とても薄くて明るいそれは、心をなんとなく晴らしてくれる。キオは髪を手から離すと、ふう、と息をついて空を仰ぎ、自分も目を閉じた。
明るい。
自分を包む日の光も、この世の光も、自分を照らしてくれる。頬がぽかぽかと暖かくなる。いつか心臓が光の熱で焼かれればいいと思った。焼け焦げればいい。この日々が続くなら、きっと耐えられる。いつかもし、ヘラクレイトスの掟が自分達を阻みそうになるなら、この心臓ごと、あいつらを焼き焦がしてやる。
キオはとても満足していた。レミオに感謝してやってもいい。けれど絶対に、意地でも口には出してやらない。
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(10/08)
(10/07)
(09/24)
(09/24)
(09/10)
(08/11)
(08/11)
(08/11)
(08/10)
(07/27)
最新トラックバック
ブログ内検索
最古記事
(07/19)
(07/20)
(07/20)
(07/27)
(08/10)
(08/11)
(08/11)
(08/11)
(09/10)
(09/24)
P R