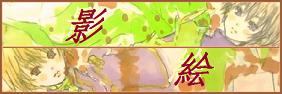自作小説「水の車輪」の原稿置き場です。 ※未熟ではありますが著作権を放棄しておりません。著作権に関わる行為は固くお断り致します。どうぞよろしくお願い致します。
[1]
[2]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
六、
蔦の絡んだ石壁の穴を潜り抜ける。途中でレミオがまた躓いて、エンデの背中に顔をしたたかにぶつけた。
「いたぁい・・・」
鼻を抑える。それは痛いだろう、とエンデも思う。せっかく可愛らしい顔をしているのに、しょっちゅうレミオは鼻や顎をどこかにぶつけている。たまに、この子の鼻が折れたらどうしよう、と心配になる、顔面骨折でもしたら大変だ。エンデはその鼻を撫でてやった。そしてうなずくと、もう一度気を取り直して進む。レミオは鼻をすんすんと鳴らしていた。ぐすっ、とまるで泣いているかのような音だ。
二人はようやく広い所に出た。空を仰ぐ。邸の三階に、小さな窓が一つある。裏口の窓だ。
「キオー」
エンデはものすごく小さな声で窓に向かって呼ぶ。さすがにレミオは肩をすくめた。たまにエンデもぼけている。
「さすがにその声じゃ聞こえないわよ?」
「そうね。じゃ、レミオ、あとはよろしく」
「はぁい」
レミオはふわり、と風に舞った。スカートが花の形にふわりと広がる。とても可愛いとエンデも思った。レミオは服にも割とこだわりがある。
ぱたぱた、と、泳ぐ時のようにつま先までぴんと伸ばして足を小さくばたつかせながら、レミオは上へと昇っていく。とても綺麗だ。妖精みたいだ。いいなあ、とエンデは思う。レミオのふわりとした髪も、華奢ですらりとしたまるで踊り子のような容姿も、とても羨ましかった。彼女には風がよく似合う。神様は本当に、与えるものを間違わない。
エンデは自分のごわごわとした髪に触れた。エンデの髪質はとても固かった。レミオのように、風でふわり、と可愛らしくなびくこともない。癖がつくと治りにくくて、寝ぐせや鳥の巣状に絡まった髪の毛がそのままどんなに櫛ですかしてもなかなか綺麗にならなかった。けれどレミオは真っすぐなエンデの髪が綺麗でうらやましいという。不思議だった。ふと、同じことをザゼリに言われたことを思い出す。髪に触れた手。触れる時頬を撫でた小さな風。急に顔がほかほかと温まっていた。手櫛で髪を縛ってもらったことまで思い出す。自分の髪を縛るシュシュを外して、ザゼリは寝ぐせの酷かったエンデの髪を綺麗に縛ってくれた。可愛いと言ってくれる。けれどエンデは、ザゼリの方がずっと可愛いと思った。髪を下ろしたザゼリに、どきりとした。
「キオー、そろそろ行こー?」
のろのろとしたしまりのない声が耳に届く。キオは椅子を回転させた。レミオが窓の向こう側で、頬杖をついてこちらを見ている。普通の人間がこんなのを見たらぎょっとするだろうな、とキオは思った。嘆息する。
「お前さ、目立つから、とりあえず中入れ」
「はーい」
レミオは大人しく淵に足をかけ、部屋の中に飛び降りた。さすが風に愛された娘だ。全てのしぐさがふわりとしていて、まるで妖精のようだ。
「俺さ、まだ勉強終わってないんだけど」
「キオにしては珍しいわね?」
「阿呆。これは5日後の講義の予習だ。お前と一緒にすんな」
レミオはしゅん、とした。レミオはあまり勉強は得意ではない。けれど、別にそれでもいいだろ、とキオは思う。どうせ自分の妻になる女だ。とりあえず生きていればいい。勉強ができようができなかろうが、少々どころかかなりみっともないボケをかます女だろうが、自分がきちんとするつもりだから万事大丈夫だろうと思う。
「いいじゃない、明日すれば・・・お祭りは今日しかないのよ?エンデだって楽しみにしてるのに」
エンデ、という単語にキオは思わずぴくり、と反応した。
「エンデに花火見せてあげるんでしょ?いつものことでしょ?」
レミオは柔らかく笑っていた。そしてとても静かな穏やかな声だ。こいつ、こんなに大人びてただろうか、とふとキオは考える。たまにレミオは、まるで包み込むような空気を滲ませる。まるで母親とか姉と接しているような感覚になる。実際の母も姉も、キオに対して温かいわけではないけれど。
「まだ明るいじゃん」
キオはとりあえず、机に向かった。けれど、どうしてだろう。なぜか筆が進まない。なんとなく居心地が悪い。キオは嘆息した。視線がうっとうしい。どうせレミオがごねているのだろう。
「いいよ、わかったよ。行けばいいんだろ?」
「もちろん!お祭りは明るいうちから楽しむものよ!」
レミオの声が明るくなる。
いつもどおりだ、問題ない。キオは少しだけほっとした。レミオにいつも通りの緩い笑顔が戻っている。よほど祭りが好きなんだなあと今更感心する。正直、いつもの遊びの延長のような気がして、キオ自身は花火以外祭りには興味がない。女と言うのは不可解だな、と思った。エンデも楽しみにしているんだろうか。彼女はあまり表情に出さないから分かりにくい。嬉しそうに意味もなくくるくると回るレミオを見ながら少々呆れた。本当にレミオの行動は不可解だ。スカートが花のようにふわふわと広がって揺れている。洒落てきたな、とキオは思った。庶民の服としてはよそいき着だと思う。淡い水色のスカートに淡い赤のライン。レミオの桃色の髪によく似合っていた。一人でにやにやしながら口元を両手で覆っている。そわそわと落ち着きやしない。もう一度キオは嘆息してノートを閉じた。たまには焼き菓子でもおごってやろうかな、とふと思った。エンデは何をしたら喜ぶだろう。とりあえず、ザゼリを引きずってでも連れて行こうと思った。そこでふと気がつく。どうせあいつはぼろぼろの汗臭い服しか持っていない。キオはこめかみに手を当てた。先に風呂に入れよう。いくらなんでも祭りの人だかりであの恰好は浮くに決まっている。
キオが着替え終わって窓枠に足をかけると、なぜかレミオに服を引っ張られた。とても小さな力だ。それでもなんとなくキオは振り返る。
「何」
レミオは一度口を開けて、また閉じた。毎年この一連の動作を見ているような気がする。とりあえず一応いつも待ってはやるのだ。けれどレミオはもじもじするばかりなので、いつもだんだん苛ついてくる。結局今も、キオはレミオに何かおごってやるのをやめようかという気持ちになって来た。
けれどレミオは服を握った手に力を入れてもう一度顔をあげた。精いっぱいの笑顔を浮かべる。それがキオにすら分かった。まったくもって不可解極まりない。
「あのね」
「んだよ。だから早く言えっつってんだよ」
「あの、たまにはわたしに抱っこされてみない?」
「は?」
しばらく言われた意味が分からなかった。時計の針が何度か音を立てる。
「は?」
もう一度声を出してしまった。レミオは吹っ切れたのか、今度は自然な笑顔でにこにことして言う。
「一度やってみたかったの。ね、キオ、抱っこさせて!」
「はぁ?逆だろ普通」
「逆ぅ~?」
レミオが気持ち悪い声を出す。キオは顔をしかめた。
「ええ~?じゃあやってくれるの?キオ」
「誰がやるか、気色悪ぃ」
「うん、わかってる」
レミオはほほ笑んだ。
「風に舞うってとっても気持ちがいいのよ、キオも体験しようよ、たまには」
「なんで」
「なんでも!」
「そうじゃない。なんで、今。てか今更。いきなり何」
レミオは黙り込んだ。えへへ、と力なく笑いながら頬を掻く。
けれど目はとても真剣だった。意味が分からない、と思った。
「くだんね」
キオは首を振って、ためらいなく窓から飛び降りた。
こういう時どうしたらいいのか分からない。とりあえず考えるのをやめた。夕焼けが目に染みる。昼の太陽よりも日差しは結構強いものなんだな、と思った。一応待ってやったのだ。聞いてやったのだ。進歩だ。精いっぱいだ。
来年以降また考えてやってもいい、とキオはぼんやり考えていた。自分がいっぱいいっぱいだったことに、蔦に包まれながらようやく気付く。心臓が痛いくらいに拍動していた。いつから痛みに鈍感になったのだろう。キオは舌打ちした。レミオのせいだ。レミオのボケが自分にも移ってしまったじゃないか。
ふわり、とキオは着地する。少し焦っていたのかもしれない。伸びた蔦を焼き焦がすのを早まった。少し体が傾く。その肩を下で待機していたエンデがとっさに支えた。なんとか体勢を立て直す。
「わり」
「いいえ」
エンデはにこりともせずに言った。キオは上を見上げた。
レミオはまだ降りてこない。
「おい!早くしろよって」
キオが怒鳴ると、ようやくレミオの頭が小さく見えた。またふにゃりと笑っている。
窓枠に立つ。頭をぶつけた。キオは嘆息した。本当にいつも通りでどうしようもない。
レミオはへらへらと笑いながら降りてきた。スカートが広がっている。キオは反射的に目をそらした。フリルだらけのペチコートで、別に何かが見えるわけでもなかったのだけれど。
レミオが降りてくると、ようやくエンデは少しだけ笑った。やっぱり女の子なんだなあ、とキオは少し感心する。自分もレミオではなくザゼリでなければ満たされない楽しさがあるように、きっとエンデもそうなのだろうと思った。レミオももう少しエンデに目を向ければいいのに、と思う。二人はもちろん仲がいい。自分とよりも一緒にいる時間だっておそらくは長いだろう。けれどなんとなく、うまく言葉では言い表せないが、レミオは無理して自分に甘えようとしているような気が最近してきていた。なぜかは分からない。ただそう思ってしまっただけだ。
(なんだ?)
ふと、違和感を感じる。
「さ、行きましょエンデ。こんな早くからお祭りに行けるとか初めてだわ!!すっごく楽しみ」
「わたしも少し」
「ふふ」
エンデがレミオの手を握り、それをレミオが握り返す。仲良く腕を振って前を歩く。その後をキオはついていく。
キオはものすごく考え込んでいた。何かが分からない。何かが変わった気がする。いつもと違う気がする。
ようやくそれに気がついたのは、二人のおしゃべりを聞きながらザゼリのいる港に着いた頃だった。
「おー、なんだぁ?えらくめかしてんなぁ」
ザゼリはにっこり笑いながら二人を見た。
「そう、可愛いでしょ?」
レミオはくるん、と一回転する。ザゼリはうなずいた。
「おぅ、可愛い可愛い。これ手作り?」
「似たようなものよ」
レミオはにこにこと笑っている。
ザゼリは首を小さくかしげた。
「エンデも、やっぱりすこしめかしてんな、いつもと似てるけど、服」
エンデが苦笑する。まったくもって気の利いた言葉の言えない男だ。キオは嘆息した。ようやく追いつくと、ザゼリがものすごく笑顔になった。
「おお!キオも来てたか!こんな時間からいるって珍しいな、めんどくさがりのくせに」
「うっせえ」
エンデも少しだけ振り返って苦笑した。ザゼリはキオの頭をくしゃくしゃにする。
「ちょっと、やめろよ。一応櫛でとかしたんだから」
「おれの手櫛で直してやるから問題ねぇ」
「いや問題大ありだよ阿呆」
なぜかエンデがそわそわしている。キオは首をかしげた。そうしてふと、ようやく、気づいた。
レミオがこっちを見ない。
一度も見ない。
話しかけもしない。
話にすら入ってこなかった。
キオにはレミオの背中しか見えない。どんな表情なのかもわからない。
分かるのは、背中に表情なんかないということだけだった。まるでレミオは本当に空気のように、そこに溶け込んでいた。
(なんだよ)
キオは少しだけむっとして、やめた。
よく考えたらどうでもいいことだった。どうせ少し拗ねているのだろう。こういう反抗の仕方は少し珍しいけれど、今までもなかったわけじゃない。放っておこうと思った。
「ねえザゼリ」
「ん?」
レミオに服の裾をひかれ、ザゼリは立ち止まった。キオとエンデは露店を覗きこんで何事か話している。
「わたしね、人を、探してるの。だから」
「ん、ん?」
ザゼリはきょとんとした。レミオはこくり、と少しだけ唾を飲み込んだ。
「ちょっとはぐれるけど、また追いかけるから、心配しないでね。って伝えてね」
服を掴む手が震えていた。震えないように力を込める。けれど腕が痛い。
ザゼリはいつもの穏やかなきょとんとした眼でレミオを見つめていた。そうして、優しく笑って、レミオの頭を撫でた。
とても温かな手だ。大きな手だ。三年後、自分の手も、これくらい大きくなれるだろうか。二人の手も、骨も、こういう風に大きくなるのだろうか、とレミオは唇をかみしめて思った。ふと、いつの間に唇をかむなんて癖ができていたのだろうと思う。きっとキオのせいだ。キオがいつも考え事をしている時唇を噛むから。ザゼリは何も言わなかった。それがありがたい。ザゼリは何も言わないでくれる。聞かないでくれる。だから好きだった。だからきっと、エンデもキオもザゼリが好きなのだろうと思う。レミオはくるりと背を向けて、人込みの中へ消えた。とにかく離れられればなんでもよかった。家に帰ろうと思った。でも帰りたくない気持ちもあった。
せっかく来たのに。せっかく来たのに。
花火、やっぱり見たくない。
わたしの場所はきっと、ザゼリが埋めてくれる。だからきっと、今少しわたしが抜けたところで大丈夫。
せっかく来たけど。
レミオは唇を噛んだ。人とぶつかる。その反動で、思い切り下唇に傷ができた。痛い。血の味がする。立ち止まると、別の大きな背中が肩にぶつかって体が揺れた。レミオは服の裾を持ち上げて、広げて見た。
こんなもの意味がない。どうして女の子は可愛い恰好をしたくなるのだろう。
可愛くなって何か意味があるだろうか。
可愛いってどういうことだろう。レミオはふとザゼリの笑顔を思い出した。
可愛いってきっと、ああいう人のことだ、と思った。
だとしたら自分には可愛くなんてなる意味がない。なる価値もない。
第一章 終
蔦の絡んだ石壁の穴を潜り抜ける。途中でレミオがまた躓いて、エンデの背中に顔をしたたかにぶつけた。
「いたぁい・・・」
鼻を抑える。それは痛いだろう、とエンデも思う。せっかく可愛らしい顔をしているのに、しょっちゅうレミオは鼻や顎をどこかにぶつけている。たまに、この子の鼻が折れたらどうしよう、と心配になる、顔面骨折でもしたら大変だ。エンデはその鼻を撫でてやった。そしてうなずくと、もう一度気を取り直して進む。レミオは鼻をすんすんと鳴らしていた。ぐすっ、とまるで泣いているかのような音だ。
二人はようやく広い所に出た。空を仰ぐ。邸の三階に、小さな窓が一つある。裏口の窓だ。
「キオー」
エンデはものすごく小さな声で窓に向かって呼ぶ。さすがにレミオは肩をすくめた。たまにエンデもぼけている。
「さすがにその声じゃ聞こえないわよ?」
「そうね。じゃ、レミオ、あとはよろしく」
「はぁい」
レミオはふわり、と風に舞った。スカートが花の形にふわりと広がる。とても可愛いとエンデも思った。レミオは服にも割とこだわりがある。
ぱたぱた、と、泳ぐ時のようにつま先までぴんと伸ばして足を小さくばたつかせながら、レミオは上へと昇っていく。とても綺麗だ。妖精みたいだ。いいなあ、とエンデは思う。レミオのふわりとした髪も、華奢ですらりとしたまるで踊り子のような容姿も、とても羨ましかった。彼女には風がよく似合う。神様は本当に、与えるものを間違わない。
エンデは自分のごわごわとした髪に触れた。エンデの髪質はとても固かった。レミオのように、風でふわり、と可愛らしくなびくこともない。癖がつくと治りにくくて、寝ぐせや鳥の巣状に絡まった髪の毛がそのままどんなに櫛ですかしてもなかなか綺麗にならなかった。けれどレミオは真っすぐなエンデの髪が綺麗でうらやましいという。不思議だった。ふと、同じことをザゼリに言われたことを思い出す。髪に触れた手。触れる時頬を撫でた小さな風。急に顔がほかほかと温まっていた。手櫛で髪を縛ってもらったことまで思い出す。自分の髪を縛るシュシュを外して、ザゼリは寝ぐせの酷かったエンデの髪を綺麗に縛ってくれた。可愛いと言ってくれる。けれどエンデは、ザゼリの方がずっと可愛いと思った。髪を下ろしたザゼリに、どきりとした。
「キオー、そろそろ行こー?」
のろのろとしたしまりのない声が耳に届く。キオは椅子を回転させた。レミオが窓の向こう側で、頬杖をついてこちらを見ている。普通の人間がこんなのを見たらぎょっとするだろうな、とキオは思った。嘆息する。
「お前さ、目立つから、とりあえず中入れ」
「はーい」
レミオは大人しく淵に足をかけ、部屋の中に飛び降りた。さすが風に愛された娘だ。全てのしぐさがふわりとしていて、まるで妖精のようだ。
「俺さ、まだ勉強終わってないんだけど」
「キオにしては珍しいわね?」
「阿呆。これは5日後の講義の予習だ。お前と一緒にすんな」
レミオはしゅん、とした。レミオはあまり勉強は得意ではない。けれど、別にそれでもいいだろ、とキオは思う。どうせ自分の妻になる女だ。とりあえず生きていればいい。勉強ができようができなかろうが、少々どころかかなりみっともないボケをかます女だろうが、自分がきちんとするつもりだから万事大丈夫だろうと思う。
「いいじゃない、明日すれば・・・お祭りは今日しかないのよ?エンデだって楽しみにしてるのに」
エンデ、という単語にキオは思わずぴくり、と反応した。
「エンデに花火見せてあげるんでしょ?いつものことでしょ?」
レミオは柔らかく笑っていた。そしてとても静かな穏やかな声だ。こいつ、こんなに大人びてただろうか、とふとキオは考える。たまにレミオは、まるで包み込むような空気を滲ませる。まるで母親とか姉と接しているような感覚になる。実際の母も姉も、キオに対して温かいわけではないけれど。
「まだ明るいじゃん」
キオはとりあえず、机に向かった。けれど、どうしてだろう。なぜか筆が進まない。なんとなく居心地が悪い。キオは嘆息した。視線がうっとうしい。どうせレミオがごねているのだろう。
「いいよ、わかったよ。行けばいいんだろ?」
「もちろん!お祭りは明るいうちから楽しむものよ!」
レミオの声が明るくなる。
いつもどおりだ、問題ない。キオは少しだけほっとした。レミオにいつも通りの緩い笑顔が戻っている。よほど祭りが好きなんだなあと今更感心する。正直、いつもの遊びの延長のような気がして、キオ自身は花火以外祭りには興味がない。女と言うのは不可解だな、と思った。エンデも楽しみにしているんだろうか。彼女はあまり表情に出さないから分かりにくい。嬉しそうに意味もなくくるくると回るレミオを見ながら少々呆れた。本当にレミオの行動は不可解だ。スカートが花のようにふわふわと広がって揺れている。洒落てきたな、とキオは思った。庶民の服としてはよそいき着だと思う。淡い水色のスカートに淡い赤のライン。レミオの桃色の髪によく似合っていた。一人でにやにやしながら口元を両手で覆っている。そわそわと落ち着きやしない。もう一度キオは嘆息してノートを閉じた。たまには焼き菓子でもおごってやろうかな、とふと思った。エンデは何をしたら喜ぶだろう。とりあえず、ザゼリを引きずってでも連れて行こうと思った。そこでふと気がつく。どうせあいつはぼろぼろの汗臭い服しか持っていない。キオはこめかみに手を当てた。先に風呂に入れよう。いくらなんでも祭りの人だかりであの恰好は浮くに決まっている。
キオが着替え終わって窓枠に足をかけると、なぜかレミオに服を引っ張られた。とても小さな力だ。それでもなんとなくキオは振り返る。
「何」
レミオは一度口を開けて、また閉じた。毎年この一連の動作を見ているような気がする。とりあえず一応いつも待ってはやるのだ。けれどレミオはもじもじするばかりなので、いつもだんだん苛ついてくる。結局今も、キオはレミオに何かおごってやるのをやめようかという気持ちになって来た。
けれどレミオは服を握った手に力を入れてもう一度顔をあげた。精いっぱいの笑顔を浮かべる。それがキオにすら分かった。まったくもって不可解極まりない。
「あのね」
「んだよ。だから早く言えっつってんだよ」
「あの、たまにはわたしに抱っこされてみない?」
「は?」
しばらく言われた意味が分からなかった。時計の針が何度か音を立てる。
「は?」
もう一度声を出してしまった。レミオは吹っ切れたのか、今度は自然な笑顔でにこにことして言う。
「一度やってみたかったの。ね、キオ、抱っこさせて!」
「はぁ?逆だろ普通」
「逆ぅ~?」
レミオが気持ち悪い声を出す。キオは顔をしかめた。
「ええ~?じゃあやってくれるの?キオ」
「誰がやるか、気色悪ぃ」
「うん、わかってる」
レミオはほほ笑んだ。
「風に舞うってとっても気持ちがいいのよ、キオも体験しようよ、たまには」
「なんで」
「なんでも!」
「そうじゃない。なんで、今。てか今更。いきなり何」
レミオは黙り込んだ。えへへ、と力なく笑いながら頬を掻く。
けれど目はとても真剣だった。意味が分からない、と思った。
「くだんね」
キオは首を振って、ためらいなく窓から飛び降りた。
こういう時どうしたらいいのか分からない。とりあえず考えるのをやめた。夕焼けが目に染みる。昼の太陽よりも日差しは結構強いものなんだな、と思った。一応待ってやったのだ。聞いてやったのだ。進歩だ。精いっぱいだ。
来年以降また考えてやってもいい、とキオはぼんやり考えていた。自分がいっぱいいっぱいだったことに、蔦に包まれながらようやく気付く。心臓が痛いくらいに拍動していた。いつから痛みに鈍感になったのだろう。キオは舌打ちした。レミオのせいだ。レミオのボケが自分にも移ってしまったじゃないか。
ふわり、とキオは着地する。少し焦っていたのかもしれない。伸びた蔦を焼き焦がすのを早まった。少し体が傾く。その肩を下で待機していたエンデがとっさに支えた。なんとか体勢を立て直す。
「わり」
「いいえ」
エンデはにこりともせずに言った。キオは上を見上げた。
レミオはまだ降りてこない。
「おい!早くしろよって」
キオが怒鳴ると、ようやくレミオの頭が小さく見えた。またふにゃりと笑っている。
窓枠に立つ。頭をぶつけた。キオは嘆息した。本当にいつも通りでどうしようもない。
レミオはへらへらと笑いながら降りてきた。スカートが広がっている。キオは反射的に目をそらした。フリルだらけのペチコートで、別に何かが見えるわけでもなかったのだけれど。
レミオが降りてくると、ようやくエンデは少しだけ笑った。やっぱり女の子なんだなあ、とキオは少し感心する。自分もレミオではなくザゼリでなければ満たされない楽しさがあるように、きっとエンデもそうなのだろうと思った。レミオももう少しエンデに目を向ければいいのに、と思う。二人はもちろん仲がいい。自分とよりも一緒にいる時間だっておそらくは長いだろう。けれどなんとなく、うまく言葉では言い表せないが、レミオは無理して自分に甘えようとしているような気が最近してきていた。なぜかは分からない。ただそう思ってしまっただけだ。
(なんだ?)
ふと、違和感を感じる。
「さ、行きましょエンデ。こんな早くからお祭りに行けるとか初めてだわ!!すっごく楽しみ」
「わたしも少し」
「ふふ」
エンデがレミオの手を握り、それをレミオが握り返す。仲良く腕を振って前を歩く。その後をキオはついていく。
キオはものすごく考え込んでいた。何かが分からない。何かが変わった気がする。いつもと違う気がする。
ようやくそれに気がついたのは、二人のおしゃべりを聞きながらザゼリのいる港に着いた頃だった。
「おー、なんだぁ?えらくめかしてんなぁ」
ザゼリはにっこり笑いながら二人を見た。
「そう、可愛いでしょ?」
レミオはくるん、と一回転する。ザゼリはうなずいた。
「おぅ、可愛い可愛い。これ手作り?」
「似たようなものよ」
レミオはにこにこと笑っている。
ザゼリは首を小さくかしげた。
「エンデも、やっぱりすこしめかしてんな、いつもと似てるけど、服」
エンデが苦笑する。まったくもって気の利いた言葉の言えない男だ。キオは嘆息した。ようやく追いつくと、ザゼリがものすごく笑顔になった。
「おお!キオも来てたか!こんな時間からいるって珍しいな、めんどくさがりのくせに」
「うっせえ」
エンデも少しだけ振り返って苦笑した。ザゼリはキオの頭をくしゃくしゃにする。
「ちょっと、やめろよ。一応櫛でとかしたんだから」
「おれの手櫛で直してやるから問題ねぇ」
「いや問題大ありだよ阿呆」
なぜかエンデがそわそわしている。キオは首をかしげた。そうしてふと、ようやく、気づいた。
レミオがこっちを見ない。
一度も見ない。
話しかけもしない。
話にすら入ってこなかった。
キオにはレミオの背中しか見えない。どんな表情なのかもわからない。
分かるのは、背中に表情なんかないということだけだった。まるでレミオは本当に空気のように、そこに溶け込んでいた。
(なんだよ)
キオは少しだけむっとして、やめた。
よく考えたらどうでもいいことだった。どうせ少し拗ねているのだろう。こういう反抗の仕方は少し珍しいけれど、今までもなかったわけじゃない。放っておこうと思った。
「ねえザゼリ」
「ん?」
レミオに服の裾をひかれ、ザゼリは立ち止まった。キオとエンデは露店を覗きこんで何事か話している。
「わたしね、人を、探してるの。だから」
「ん、ん?」
ザゼリはきょとんとした。レミオはこくり、と少しだけ唾を飲み込んだ。
「ちょっとはぐれるけど、また追いかけるから、心配しないでね。って伝えてね」
服を掴む手が震えていた。震えないように力を込める。けれど腕が痛い。
ザゼリはいつもの穏やかなきょとんとした眼でレミオを見つめていた。そうして、優しく笑って、レミオの頭を撫でた。
とても温かな手だ。大きな手だ。三年後、自分の手も、これくらい大きくなれるだろうか。二人の手も、骨も、こういう風に大きくなるのだろうか、とレミオは唇をかみしめて思った。ふと、いつの間に唇をかむなんて癖ができていたのだろうと思う。きっとキオのせいだ。キオがいつも考え事をしている時唇を噛むから。ザゼリは何も言わなかった。それがありがたい。ザゼリは何も言わないでくれる。聞かないでくれる。だから好きだった。だからきっと、エンデもキオもザゼリが好きなのだろうと思う。レミオはくるりと背を向けて、人込みの中へ消えた。とにかく離れられればなんでもよかった。家に帰ろうと思った。でも帰りたくない気持ちもあった。
せっかく来たのに。せっかく来たのに。
花火、やっぱり見たくない。
わたしの場所はきっと、ザゼリが埋めてくれる。だからきっと、今少しわたしが抜けたところで大丈夫。
せっかく来たけど。
レミオは唇を噛んだ。人とぶつかる。その反動で、思い切り下唇に傷ができた。痛い。血の味がする。立ち止まると、別の大きな背中が肩にぶつかって体が揺れた。レミオは服の裾を持ち上げて、広げて見た。
こんなもの意味がない。どうして女の子は可愛い恰好をしたくなるのだろう。
可愛くなって何か意味があるだろうか。
可愛いってどういうことだろう。レミオはふとザゼリの笑顔を思い出した。
可愛いってきっと、ああいう人のことだ、と思った。
だとしたら自分には可愛くなんてなる意味がない。なる価値もない。
第一章 終
PR
第二章
愛しい人
俺はあなたに告げることができなかった
なぜならそれは許されていなかったから
あなたはそれを理不尽だという
それでも俺にはなす術がないのです
あなたは術などいくらでもあるという
けれど本当は
それらはすべて
侵してはいけない領域なのです
愛しかった人
俺はあなたに言えなかったことがあった
どうしても隠さずにはいられなかった
きっとこうなることがわかってたんだ
だって俺は知っていた
あなたがいつか
『彼』になるのだと
知っていた
愛していたのはあなただった
けれど焦がれていたのは
ほんとうは
あなたは知らなかった
知れるはずがない
どうしてあの日俺と出会ったのか
あなたはそれを運命だというけれど
ほんとうはきっと
ただの逃避だったんだ
あなたを止めなかった
強く止めなかった
頭では分かっていたのに
止められなかった
ただ一つの短い夢に
もう一度巡り逢いたかった
だから
止められなかった
ああオケアノスよ
我らに備うはずもない
衝動というものを
欲というものを
きっと俺だけが
なぜか持ってしまっていたんだ
きっとそれが
いけないことだったのに
一、
海の中にいる。
耳に、脳髄に、深く染み入ってくる声、音、言葉。
僕を呼ぶ声が上からも下からも降ってくる、昇ってくる。僕を包み込む。
壁がどこにあるのかは、僕にはわからないけれど、
けれどそれらの声はすべてまた反射して、僕にどんどん絡みついてきた。
『オストロン』
『ドュマ』
『オストロン』
『オストロン』
『ドュマ』
途切れることなく僕の耳をずっとずっと撫でていく。僕は不安になった。
僕は一体誰だろう。
いろんな声が、音が僕を呼ぶ。
けれど耳を澄ますと、一つの音が特に僕を縛って放さないような気がした。
「誰・・・?」
ようやく僕は瞼を上げる。そうして初めて、自分が目を開けていなかったことに気付いた。
透明な水色の世界が僕を取り囲んでいた。
とてもひんやりとして気持ちがいい。四方八方から泡が十色に光りながら舞い集まってくる。
まるで、妖精が喜び踊っているようだ。僕は緩やかに沈んでいたけれど、透明に揺れる天井からそそぐ金色の明かりの筋は、まるで誰かがやさしく微笑みかけてくれているようで、見守られているような心地になる。
光を感じるだけで、こんなにも世界が美しいことを知れるのかと、僕は嬉しくなった。
僕を呼ぶ声たちは途切れることなくこだましている。けれど、僕を包み込み、それでいてどこか締め付けるような不安を呼び起こしたそれらの音は、視界が開けたことであまり気にならなくなっていた。ただ僕を浸してくれるだけだった。心が満たされていく。僕は愛されている。包まれている。この世界に。世界のすべてに。
愛されることがこんなにも嬉しい。
満たされる気持ちは僕を内側からも包み込んだ。つい、また瞼を閉じてしまいそうなほどに心地よい。
僕は浸っていた。
僕を締め付ける欲からも、強い願いからも、ここは解放してくれる。
僕の中にある水は、僕を潤してくれる水は、僕をすべてから濾し出してくれる。
だから僕は、もう少しでその声を聞き逃すところだった。
『あなたの・・・名前は?』
その声は低いようで高いようで、かすれているようでよく通るようで。
不思議な声だ。あまりにも微かな響きだった。だから、もしも聞き逃していたならと、急にぞっとした。それなのに心のどこかで、やっぱりきっと聞き逃さなかっただろうとも思えた。
心臓がはねて、ずきずきと鼓動していた。自分には心臓があったとようやく思い出す。
「君は誰?」
僕は、声の響いてきた暗く何ものがあるか見えない水底に向かって手を伸ばす。
そしてふと、どこかでこの感覚を覚えている、と気付いた。
どこで、この会話をしただろう。どこで、初めてこの声を聞いただろう。
思い出せない。
思い、出せない。
『オストロン』
僕の周りの声がひときわ大きく合唱する。僕ははっ、と我に返った。
「違うよ、それは、僕の名前じゃない」
『オストロン』
『オストロン』
『オストロン』
それでも、声たちは慈しむように僕を呼んだ。
「僕じゃない。僕じゃ、ないんだ」
僕はいつの間にか、胸の痛みをこらえるように目を閉じていた。それでも瞼をすかして鈍い水の色が僕の瞳を撫でていく。
青い色をとてもきれいだと思った。それなのに、今は息苦しい。
僕は、僕を大切だと、消えないでほしいという声が辛くてたまらない。
【消えるわけじゃないよ】
僕の中にいるもう一人の僕が言った。くすり、と笑っている。
【消えるわけじゃない。消えるとすればそれは君の方だろう?僕がオストロンなのは変えようのない事実。摂理だよ】
「そうだね」
僕は素直に答えた。とても穏やかな気分だ。
それは、僕には失うものも何もなくて、大事なものも何もないからかもしれない。
「僕は君が君の願いをかなえるための、ただの通過点でしかないね」
僕は揺らめく天井を見上げた。光はくすくすと笑い揺れる。
【その通り】
【君には大事なものなんか必要ない】
【だから、楽しめばいいよ】
【夢は楽しむためのものでしょう?】
僕は静かに首を横に振った。
「それは違うよ、オストロン。夢を見て癒されることもある。けれど同じだけ、不安になったり、怖くなったりすることもあるんだ。僕らにとって、一夜の夢なんて、癒しなんかじゃないんだよ」
【そう】
光は静かに答えた。
【それでも君は僕で、僕は君だから。好きに生きればいいよ】
【君がいつか、勝手に疲れてしまって】
【その姿を僕に返すことになったら】
【二度と君はいなくなるんだから】
「そうだね」
僕は素直にうなずいた。
摂理も、仕組みも、よくわからない。けれど一つだけわかっているのは、水の子は消えることがなくて、僕は朽ちるものであるということ。それは変えられない、慈悲も何もない、事実だということ。
僕はふわりふわりと浮いている体をねじり、もう一度水底を見つめた。
「ひとつ、聞いてもいいかな」
誰も答えない。耳に届くのは、ずっと鳴り響いてやまない、僕を『オストロン』とも『ドュマ』とも呼びしきる声たちのみ。
「オストロン、君はいつ彼と出会ったの?僕はどうしてもそれが思い出せないんだ。なのにどうして、君はずっと彼と一緒にいたの?彼を、好きになったの」
光は揺れていた。僕は気づいた。水のゆれも、光の揺れも、すべてオストロンの心そのものだった。彼の心は留まれない。ずっと、揺れていく。止まりたいと願っているのに、止まれない。
【僕は覚えていないよ】
悲しげに、光は言った。
【彼が僕に隠していることもなんとなくだけど】
【知っていた】
【けれど、それでも良かったんだ。だって彼は、僕を唯一濁してくれる人だから】
【僕を、せき止めてくれるたった一人の子だから】
【僕が立ち止まれるように、後ろにいてくれる人だからね】
「嘘だ」
僕は少しずつ意識がはっきりしてくるのを感じていた。鈍かった水の肌に触れる感触を、今ははっきりと感じている。なんて冷たいのだろう。
「僕は覚えている。僕は、彼の背中だけをよく覚えているんだ。後ろにいたのはいつも君の方だ。君ばかり、彼を追いかけてたんだ」
【知ってる】
光はこともなげに言った。
【結局、僕の心に触れてくれるのは】
光はそこでしばらく言葉を切った。
【揺れる者だけ】
とても悲しげな声だった。
【だから君に託したいんだ】
【だから、彼らと一緒にいてみようと思ったんだ】
【留まる体を得て、今の気分はどう?】
とても面白そうに光は言った。
僕は言った。
「最悪だ」
僕は名前を思い出す。
僕の名前。
そして僕は、強くなっていく光とともに、彼の名前を忘れた。
彼と、彼の愛していたもう一人の彼の名前も。
愛しい人
俺はあなたに告げることができなかった
なぜならそれは許されていなかったから
あなたはそれを理不尽だという
それでも俺にはなす術がないのです
あなたは術などいくらでもあるという
けれど本当は
それらはすべて
侵してはいけない領域なのです
愛しかった人
俺はあなたに言えなかったことがあった
どうしても隠さずにはいられなかった
きっとこうなることがわかってたんだ
だって俺は知っていた
あなたがいつか
『彼』になるのだと
知っていた
愛していたのはあなただった
けれど焦がれていたのは
ほんとうは
あなたは知らなかった
知れるはずがない
どうしてあの日俺と出会ったのか
あなたはそれを運命だというけれど
ほんとうはきっと
ただの逃避だったんだ
あなたを止めなかった
強く止めなかった
頭では分かっていたのに
止められなかった
ただ一つの短い夢に
もう一度巡り逢いたかった
だから
止められなかった
ああオケアノスよ
我らに備うはずもない
衝動というものを
欲というものを
きっと俺だけが
なぜか持ってしまっていたんだ
きっとそれが
いけないことだったのに
一、
海の中にいる。
耳に、脳髄に、深く染み入ってくる声、音、言葉。
僕を呼ぶ声が上からも下からも降ってくる、昇ってくる。僕を包み込む。
壁がどこにあるのかは、僕にはわからないけれど、
けれどそれらの声はすべてまた反射して、僕にどんどん絡みついてきた。
『オストロン』
『ドュマ』
『オストロン』
『オストロン』
『ドュマ』
途切れることなく僕の耳をずっとずっと撫でていく。僕は不安になった。
僕は一体誰だろう。
いろんな声が、音が僕を呼ぶ。
けれど耳を澄ますと、一つの音が特に僕を縛って放さないような気がした。
「誰・・・?」
ようやく僕は瞼を上げる。そうして初めて、自分が目を開けていなかったことに気付いた。
透明な水色の世界が僕を取り囲んでいた。
とてもひんやりとして気持ちがいい。四方八方から泡が十色に光りながら舞い集まってくる。
まるで、妖精が喜び踊っているようだ。僕は緩やかに沈んでいたけれど、透明に揺れる天井からそそぐ金色の明かりの筋は、まるで誰かがやさしく微笑みかけてくれているようで、見守られているような心地になる。
光を感じるだけで、こんなにも世界が美しいことを知れるのかと、僕は嬉しくなった。
僕を呼ぶ声たちは途切れることなくこだましている。けれど、僕を包み込み、それでいてどこか締め付けるような不安を呼び起こしたそれらの音は、視界が開けたことであまり気にならなくなっていた。ただ僕を浸してくれるだけだった。心が満たされていく。僕は愛されている。包まれている。この世界に。世界のすべてに。
愛されることがこんなにも嬉しい。
満たされる気持ちは僕を内側からも包み込んだ。つい、また瞼を閉じてしまいそうなほどに心地よい。
僕は浸っていた。
僕を締め付ける欲からも、強い願いからも、ここは解放してくれる。
僕の中にある水は、僕を潤してくれる水は、僕をすべてから濾し出してくれる。
だから僕は、もう少しでその声を聞き逃すところだった。
『あなたの・・・名前は?』
その声は低いようで高いようで、かすれているようでよく通るようで。
不思議な声だ。あまりにも微かな響きだった。だから、もしも聞き逃していたならと、急にぞっとした。それなのに心のどこかで、やっぱりきっと聞き逃さなかっただろうとも思えた。
心臓がはねて、ずきずきと鼓動していた。自分には心臓があったとようやく思い出す。
「君は誰?」
僕は、声の響いてきた暗く何ものがあるか見えない水底に向かって手を伸ばす。
そしてふと、どこかでこの感覚を覚えている、と気付いた。
どこで、この会話をしただろう。どこで、初めてこの声を聞いただろう。
思い出せない。
思い、出せない。
『オストロン』
僕の周りの声がひときわ大きく合唱する。僕ははっ、と我に返った。
「違うよ、それは、僕の名前じゃない」
『オストロン』
『オストロン』
『オストロン』
それでも、声たちは慈しむように僕を呼んだ。
「僕じゃない。僕じゃ、ないんだ」
僕はいつの間にか、胸の痛みをこらえるように目を閉じていた。それでも瞼をすかして鈍い水の色が僕の瞳を撫でていく。
青い色をとてもきれいだと思った。それなのに、今は息苦しい。
僕は、僕を大切だと、消えないでほしいという声が辛くてたまらない。
【消えるわけじゃないよ】
僕の中にいるもう一人の僕が言った。くすり、と笑っている。
【消えるわけじゃない。消えるとすればそれは君の方だろう?僕がオストロンなのは変えようのない事実。摂理だよ】
「そうだね」
僕は素直に答えた。とても穏やかな気分だ。
それは、僕には失うものも何もなくて、大事なものも何もないからかもしれない。
「僕は君が君の願いをかなえるための、ただの通過点でしかないね」
僕は揺らめく天井を見上げた。光はくすくすと笑い揺れる。
【その通り】
【君には大事なものなんか必要ない】
【だから、楽しめばいいよ】
【夢は楽しむためのものでしょう?】
僕は静かに首を横に振った。
「それは違うよ、オストロン。夢を見て癒されることもある。けれど同じだけ、不安になったり、怖くなったりすることもあるんだ。僕らにとって、一夜の夢なんて、癒しなんかじゃないんだよ」
【そう】
光は静かに答えた。
【それでも君は僕で、僕は君だから。好きに生きればいいよ】
【君がいつか、勝手に疲れてしまって】
【その姿を僕に返すことになったら】
【二度と君はいなくなるんだから】
「そうだね」
僕は素直にうなずいた。
摂理も、仕組みも、よくわからない。けれど一つだけわかっているのは、水の子は消えることがなくて、僕は朽ちるものであるということ。それは変えられない、慈悲も何もない、事実だということ。
僕はふわりふわりと浮いている体をねじり、もう一度水底を見つめた。
「ひとつ、聞いてもいいかな」
誰も答えない。耳に届くのは、ずっと鳴り響いてやまない、僕を『オストロン』とも『ドュマ』とも呼びしきる声たちのみ。
「オストロン、君はいつ彼と出会ったの?僕はどうしてもそれが思い出せないんだ。なのにどうして、君はずっと彼と一緒にいたの?彼を、好きになったの」
光は揺れていた。僕は気づいた。水のゆれも、光の揺れも、すべてオストロンの心そのものだった。彼の心は留まれない。ずっと、揺れていく。止まりたいと願っているのに、止まれない。
【僕は覚えていないよ】
悲しげに、光は言った。
【彼が僕に隠していることもなんとなくだけど】
【知っていた】
【けれど、それでも良かったんだ。だって彼は、僕を唯一濁してくれる人だから】
【僕を、せき止めてくれるたった一人の子だから】
【僕が立ち止まれるように、後ろにいてくれる人だからね】
「嘘だ」
僕は少しずつ意識がはっきりしてくるのを感じていた。鈍かった水の肌に触れる感触を、今ははっきりと感じている。なんて冷たいのだろう。
「僕は覚えている。僕は、彼の背中だけをよく覚えているんだ。後ろにいたのはいつも君の方だ。君ばかり、彼を追いかけてたんだ」
【知ってる】
光はこともなげに言った。
【結局、僕の心に触れてくれるのは】
光はそこでしばらく言葉を切った。
【揺れる者だけ】
とても悲しげな声だった。
【だから君に託したいんだ】
【だから、彼らと一緒にいてみようと思ったんだ】
【留まる体を得て、今の気分はどう?】
とても面白そうに光は言った。
僕は言った。
「最悪だ」
僕は名前を思い出す。
僕の名前。
そして僕は、強くなっていく光とともに、彼の名前を忘れた。
彼と、彼の愛していたもう一人の彼の名前も。
二、
まるでどこかから浮遊してくるような感覚。
目が覚めると、梢越しの緑と金色の重なり合った光が目に染みた。
頬が痒い気がして、ドュマは少し爪の伸びた左の人差し指でそっと頬を掻いた。当たり前のことだが頬にくっきり草の痕が付いている。その場で胡坐をかいたまま、ドュマはぼんやりと目の前の草原を見つめる。腕の上を黒くて小さな虫がゆっくりと這っていく。ドュマはそいつを指で軽くはじいた。ブン、という不快な音を立てて、虫はしばらくドュマの周りをくるくる回ったのち、どこかへ飛んで行った。
寝起きに腹がこれ以上ないくらい空いているのはなぜだろう。きりきりと痛むくらいだ。ふらふらとしながらドュマはとりあえず食べるものを探すために腰を上げた。
「しまった。寝る前に傍に食うもの積んどきゃよかった」
のろのろと呟く。一人きりだと妙に大きい独り言が増えるのは仕様だから仕方がない。
木の枝の上では小鳥たちがせわしなく自分の身をついばんでいる。朝の手入れでもしているのだろうか。それを立ち止まってぼんやりと眺めながら、ドュマはのろのろと頭を掻いた。
「まさか虫を食うわけにもいかないしなあ」
くんくん、と匂いをかいでとりあえず道端に合った花を食む。
蜜が甘い。花弁も、木の皮を食べるのに比べたらずっと食感もうまい。
「村にいたら蜂蜜食い放題だったんだけどなあ。僕蜂の処理の仕方知らないしな」
おもしろくなさそうにドュマは口にくわえたまま茎を舌で動かす。ドュマは割と甘党だった。
ぼさぼさの頭はいつも適当に邪魔な部分を切っているため非常に不ぞろいだ。敢えて言うなら非常に個性的な髪形になっていた。それでもそれが似合って見えるのは、ドュマの顔立ちがどこか中性的で端正だからかもしれない。
「のど乾いた」
喉仏のあたりをこすりながらドュマは呟いた。そのまま口を空に向かって開ける。空から幾滴もの雨がドュマの口の中へと注いだ。とても冷たく綺麗な水だ。体の芯まで潤されていく。
ドュマが村を出て、すでに3カ月は過ぎていた。それでもまだ短い方だ。ここ数年のうちに、ドュマが村を開ける期間は少しずつ長くなっていた。ドュマはひとところに落ち着くのがどうも苦手だった。穏やかに立ち止まって生きていると、体の内側から熱い声がする。お前の居場所はここじゃない、お前の本質はそんなものじゃない、とドュマに語りかけてくる。
初めて村を出たのは7歳の頃だった。それまでも村の中をふらふらと歩きまわっては村の大人たちに捜索されるような子供だった。何度こっぴどく叱られたかわからない。それでもドュマのそういう癖は一向に治らなかった。どんなに怒っても叩いても諭しても、柳に風だ。ドュマはぼんやりと大人たちの顔を見上げるだけ、口先で謝るだけで、反省するそぶりを一切見せなかった。痛い思いをしても、その痛さに顔をしかめこそすれ泣きもしなかったし、やめて、と、同じ年ごろの子供なら誰でも泣いて振り絞る声さえ出しはしなかった。
次第に村の大人たちはドュマのことをあきらめた。勝手に森の中へ入って、それでもし命を落とすならばそれはドュマ自身の責任だと投げるようになった。ところが不思議なことに、一向にドュマは危ない目には合わなかった。いつでも、行方をくらましてはまたふらっと無事に村に戻ってくる。いつもののろのろとぼんやりした調子で、ただいますら言わずに当たり前のように食卓についている。村の大人たちはドュマを気味悪がった。
村人たちがドュマを気味悪がったのはドュマのそういった変わった性質だけではなかった。
ドュマは生まれ落ちた瞬間から、目じりのあたりに二つの点のような痣を持っていた。それはまるで黒子のようなものだったが、村人たちは気味悪いと思った。まるで汚い染みのように、その二つの点はドュマの目元にあり続け、一向に消えることはなかった。
ドュマは物心ついたころから、水と話をしていた。桶に入った水に笑いかけている彼を見た時は、ぞっとしたものだ。しかも、桶にためている水をドュマはことごとく地面にぶちまけたので、村人たちはほとほと困った。なぜこんなことをするのかと問うても、にっこりと笑ってのろのろと、「だって、水は留まってはいけないものだから」とばかり言うのだった。
それでも、村が水不足になったり、あるいは大雨による被害を受けることは、ドュマの生まれた14年前から嘘のようにぴたりと止んでいた。村は常に水の恵みを受けていた。14年前に生まれたのは、子供が生まれにくくなっているハケナの村ではドュマただ一人だったから、次第に大人たちは、ドュマはもしかしたら、水の神の化身なのではないか、と思うようになった。もしも神様の御姿であるというのなら、この奇妙なドュマのつかみどころのない性質も何となく納得できるような気もした。その憶測は、たまたま村に訪れた占いの手のある旅人が、「この子は水に守られている」と告げたことで核心に変わっていった。やがて親家族でさえも、ドュマを怖がるようになった。ぶってごめんなさい、と震えた。けれどドュマはいつものように首をかしげてにっこりと間の抜けた頬笑みを浮かべながら、「謝ることなんかないのに、どうして謝るの?」というのだ。その態度がどうにも村人たちには空恐ろしいものに思えた。
村を出て行ってはどうかとドュマに告げたのは祖父だった。ドュマは祖父が好きだったし、祖父もまた、ドュマを愛していた。けれど祖父はそう告げた。
『悪意や恐れを受けることはお前のためにならないよ』と祖父は言った。
『僕は気にならないよ』とドュマは言った。けれど祖父は頭を振った。
『たとえお前が自覚をしていなくても、人の心というものは、人を少しずつ蝕んでいくものなのだよ。そう思う彼らも、そしてお前自身をも。お前はこの村にいてはいけない。いつかほんとうに、大事な笑い方を忘れてしまうよ。わからなくなってしまうよ』祖父は真剣なまなざしで言った。その灰色の瞳には深い愛情と悲しみが潜んでいる。
『じゃあ僕はここを出て行こうかな』ドュマはあっさりと言った。
大好きな祖父、妹、両親と離れることは、今更やっと、少しだけ悲しいと思えた。それでもまあいいかとも思えた。ふわふわと心が浮遊する。ドュマは気づくことはなかった。自分の心も少しずつ傷はついているということがわからなかった。そのせいでどこか上の空で、心が体から離れてどこかを漂っている心地を味わっていたのに、よくわかれずにいた。
13歳のとき、村を出た。ただの一時的なものじゃなかった。ドュマは、村から縁を切られたのだ。けれどドュマはあくまで「これは僕の意思だから」と言った。
『僕の気持ちをくんでくれてありがとう。僕はここを出て行くよ。この村を出て行くよ』と、ドュマはにっこりと笑って言った。
それでも一度、ふらりとまた村に戻ってきてしまったことがある。なぜかはドュマにもわからなかった。心が初めて急いたのだ。けれど、どうしても門をくぐることはできなかった。古い木でできた大きな門を見上げて、ドュマは首を緩やかに振ると、また来た道を戻った。もう二度と戻れないのだと思った。初めて怖いと思った。戻ってどういう顔をしていいのかわからなかった。今までそういう努力を全くしてこなかったからだ。
ふらふらと歩くのは好きだったけれど、帰る場所も、行くための場所もないことは、なかなかに辛いものだった。
その日暮らしで生きていくことはできたし、水が自分を守ってくれるから、身の危険もなかったけれど、どういう風に生きていればいいのかわからなかった。
だからドュマは、一年前にふらりと行き着いたアルカイルの国で、祭りの夜に出会ったとき、どこか安堵できた。この火祭りは、この一帯ではとても有名なものであるらしかった。毎年この祭りの盛大な花火を見るために、各国から観光客が訪れるのだ。普段は世界中に散らばっている人という個が、この明るく暑い夜には群れをなして花火のもとに集まる。まるで帰ってこられたような気がした。
(ここが僕の帰られる場所だ)
ドュマは、十色に光る火の花を見ながら心が満たされていくのを感じた。周りにいる人々は誰もかれも知らない人たちばかりだ。どんな人生を送っているのか、どんな性格なのか、何も知らない。話もできない。それでもまるで、今だけは自分もその一部になれた気がした。
だから今日もまた、ドュマはあのアルカイルの国、シワナの港町の祭りに向けて、のんびりと歩いている。
帰れる場所、帰れる時間があるというのは幸せだった。これからは毎年これを自分の課としようと思っていた。祭りが終わったら、街を出てまたどこか知らない世界に歩いていく。そしてまたぐるりと回り道をして一年に一回帰ってくる。一晩だけを、人とともに温かな街で眠りたい。
「そろそろ着くかな?ちょっと早く来すぎたかな」
ドュマは立ち止まって首をかしげた。祭りが楽しみすぎて、戻ってくるのを少し早まったかもしれない。ドュマが関門の前に来た時、昨年は関門にも飾られていた赤い提灯はまだ取り付けられていなかった。
「いらっしゃい、シワナの街へ」
白髪と灰色の髪が混じった男は、ドュマの顔をろくに見ることもなく不愛想に言った。とても気難しそうな無骨な男だ。けれどドュマはこの男が嫌いではない。祖父と同じ匂いがする。
「こんにちは、おじさん。今年も会えたね」
「ここを通る人間の顔何ぞいちいち覚えとらん」
男はそっけない。ドュマは、門から見える大通りをきょろきょろと見渡した。
「おじさん、祭りはまだなの?」
「あと6日後だなあ」
「ありゃ。僕早く来すぎたみたいだなあ。おじさん、宿はここあるんだっけ?」
「仮にも観光街だ。あるに決まっているさ。だがわしは教えんぞ。自分で勝手に探すがいい」
「うん。そうだね、ありがとうおじさん」
ドュマはにっこりと笑った。淡い橙と白の薄煉瓦のタイルでできた道を踏みしめる。
祭りであろうとなかろうと、この街は常に電灯や店先の看板にたくさんの装飾が施してあった。色とりどりで、とても可愛らしい。ドュマはにっこりとした。なんだか楽しい。
後で思えば、やっぱり祭りより早くこの街に踏みいってしまったのは、軽率だったかもしれないともドュマは思う。
それでも、自分があの時あの場にいたからこそ、彼女の傷をあの程度で抑えられたのだとも思った。あの時自分がいてよかったと思った。水に愛されていてよかったと思った。
人との縁が少しずつ絡み合って、いつしか彼女にたどり着けたこと、たとえ一番残酷な形だったとしても、ドュマは感謝している。喜んでいる。たとえその気持ちが彼女にとっては救いにならなくても、それでもドュマにとっては大きなことだった。村人たちに忌み嫌われた目元の二つの痣・・・黒子も、このための道標だったのだと今ならわかるから。
まるでどこかから浮遊してくるような感覚。
目が覚めると、梢越しの緑と金色の重なり合った光が目に染みた。
頬が痒い気がして、ドュマは少し爪の伸びた左の人差し指でそっと頬を掻いた。当たり前のことだが頬にくっきり草の痕が付いている。その場で胡坐をかいたまま、ドュマはぼんやりと目の前の草原を見つめる。腕の上を黒くて小さな虫がゆっくりと這っていく。ドュマはそいつを指で軽くはじいた。ブン、という不快な音を立てて、虫はしばらくドュマの周りをくるくる回ったのち、どこかへ飛んで行った。
寝起きに腹がこれ以上ないくらい空いているのはなぜだろう。きりきりと痛むくらいだ。ふらふらとしながらドュマはとりあえず食べるものを探すために腰を上げた。
「しまった。寝る前に傍に食うもの積んどきゃよかった」
のろのろと呟く。一人きりだと妙に大きい独り言が増えるのは仕様だから仕方がない。
木の枝の上では小鳥たちがせわしなく自分の身をついばんでいる。朝の手入れでもしているのだろうか。それを立ち止まってぼんやりと眺めながら、ドュマはのろのろと頭を掻いた。
「まさか虫を食うわけにもいかないしなあ」
くんくん、と匂いをかいでとりあえず道端に合った花を食む。
蜜が甘い。花弁も、木の皮を食べるのに比べたらずっと食感もうまい。
「村にいたら蜂蜜食い放題だったんだけどなあ。僕蜂の処理の仕方知らないしな」
おもしろくなさそうにドュマは口にくわえたまま茎を舌で動かす。ドュマは割と甘党だった。
ぼさぼさの頭はいつも適当に邪魔な部分を切っているため非常に不ぞろいだ。敢えて言うなら非常に個性的な髪形になっていた。それでもそれが似合って見えるのは、ドュマの顔立ちがどこか中性的で端正だからかもしれない。
「のど乾いた」
喉仏のあたりをこすりながらドュマは呟いた。そのまま口を空に向かって開ける。空から幾滴もの雨がドュマの口の中へと注いだ。とても冷たく綺麗な水だ。体の芯まで潤されていく。
ドュマが村を出て、すでに3カ月は過ぎていた。それでもまだ短い方だ。ここ数年のうちに、ドュマが村を開ける期間は少しずつ長くなっていた。ドュマはひとところに落ち着くのがどうも苦手だった。穏やかに立ち止まって生きていると、体の内側から熱い声がする。お前の居場所はここじゃない、お前の本質はそんなものじゃない、とドュマに語りかけてくる。
初めて村を出たのは7歳の頃だった。それまでも村の中をふらふらと歩きまわっては村の大人たちに捜索されるような子供だった。何度こっぴどく叱られたかわからない。それでもドュマのそういう癖は一向に治らなかった。どんなに怒っても叩いても諭しても、柳に風だ。ドュマはぼんやりと大人たちの顔を見上げるだけ、口先で謝るだけで、反省するそぶりを一切見せなかった。痛い思いをしても、その痛さに顔をしかめこそすれ泣きもしなかったし、やめて、と、同じ年ごろの子供なら誰でも泣いて振り絞る声さえ出しはしなかった。
次第に村の大人たちはドュマのことをあきらめた。勝手に森の中へ入って、それでもし命を落とすならばそれはドュマ自身の責任だと投げるようになった。ところが不思議なことに、一向にドュマは危ない目には合わなかった。いつでも、行方をくらましてはまたふらっと無事に村に戻ってくる。いつもののろのろとぼんやりした調子で、ただいますら言わずに当たり前のように食卓についている。村の大人たちはドュマを気味悪がった。
村人たちがドュマを気味悪がったのはドュマのそういった変わった性質だけではなかった。
ドュマは生まれ落ちた瞬間から、目じりのあたりに二つの点のような痣を持っていた。それはまるで黒子のようなものだったが、村人たちは気味悪いと思った。まるで汚い染みのように、その二つの点はドュマの目元にあり続け、一向に消えることはなかった。
ドュマは物心ついたころから、水と話をしていた。桶に入った水に笑いかけている彼を見た時は、ぞっとしたものだ。しかも、桶にためている水をドュマはことごとく地面にぶちまけたので、村人たちはほとほと困った。なぜこんなことをするのかと問うても、にっこりと笑ってのろのろと、「だって、水は留まってはいけないものだから」とばかり言うのだった。
それでも、村が水不足になったり、あるいは大雨による被害を受けることは、ドュマの生まれた14年前から嘘のようにぴたりと止んでいた。村は常に水の恵みを受けていた。14年前に生まれたのは、子供が生まれにくくなっているハケナの村ではドュマただ一人だったから、次第に大人たちは、ドュマはもしかしたら、水の神の化身なのではないか、と思うようになった。もしも神様の御姿であるというのなら、この奇妙なドュマのつかみどころのない性質も何となく納得できるような気もした。その憶測は、たまたま村に訪れた占いの手のある旅人が、「この子は水に守られている」と告げたことで核心に変わっていった。やがて親家族でさえも、ドュマを怖がるようになった。ぶってごめんなさい、と震えた。けれどドュマはいつものように首をかしげてにっこりと間の抜けた頬笑みを浮かべながら、「謝ることなんかないのに、どうして謝るの?」というのだ。その態度がどうにも村人たちには空恐ろしいものに思えた。
村を出て行ってはどうかとドュマに告げたのは祖父だった。ドュマは祖父が好きだったし、祖父もまた、ドュマを愛していた。けれど祖父はそう告げた。
『悪意や恐れを受けることはお前のためにならないよ』と祖父は言った。
『僕は気にならないよ』とドュマは言った。けれど祖父は頭を振った。
『たとえお前が自覚をしていなくても、人の心というものは、人を少しずつ蝕んでいくものなのだよ。そう思う彼らも、そしてお前自身をも。お前はこの村にいてはいけない。いつかほんとうに、大事な笑い方を忘れてしまうよ。わからなくなってしまうよ』祖父は真剣なまなざしで言った。その灰色の瞳には深い愛情と悲しみが潜んでいる。
『じゃあ僕はここを出て行こうかな』ドュマはあっさりと言った。
大好きな祖父、妹、両親と離れることは、今更やっと、少しだけ悲しいと思えた。それでもまあいいかとも思えた。ふわふわと心が浮遊する。ドュマは気づくことはなかった。自分の心も少しずつ傷はついているということがわからなかった。そのせいでどこか上の空で、心が体から離れてどこかを漂っている心地を味わっていたのに、よくわかれずにいた。
13歳のとき、村を出た。ただの一時的なものじゃなかった。ドュマは、村から縁を切られたのだ。けれどドュマはあくまで「これは僕の意思だから」と言った。
『僕の気持ちをくんでくれてありがとう。僕はここを出て行くよ。この村を出て行くよ』と、ドュマはにっこりと笑って言った。
それでも一度、ふらりとまた村に戻ってきてしまったことがある。なぜかはドュマにもわからなかった。心が初めて急いたのだ。けれど、どうしても門をくぐることはできなかった。古い木でできた大きな門を見上げて、ドュマは首を緩やかに振ると、また来た道を戻った。もう二度と戻れないのだと思った。初めて怖いと思った。戻ってどういう顔をしていいのかわからなかった。今までそういう努力を全くしてこなかったからだ。
ふらふらと歩くのは好きだったけれど、帰る場所も、行くための場所もないことは、なかなかに辛いものだった。
その日暮らしで生きていくことはできたし、水が自分を守ってくれるから、身の危険もなかったけれど、どういう風に生きていればいいのかわからなかった。
だからドュマは、一年前にふらりと行き着いたアルカイルの国で、祭りの夜に出会ったとき、どこか安堵できた。この火祭りは、この一帯ではとても有名なものであるらしかった。毎年この祭りの盛大な花火を見るために、各国から観光客が訪れるのだ。普段は世界中に散らばっている人という個が、この明るく暑い夜には群れをなして花火のもとに集まる。まるで帰ってこられたような気がした。
(ここが僕の帰られる場所だ)
ドュマは、十色に光る火の花を見ながら心が満たされていくのを感じた。周りにいる人々は誰もかれも知らない人たちばかりだ。どんな人生を送っているのか、どんな性格なのか、何も知らない。話もできない。それでもまるで、今だけは自分もその一部になれた気がした。
だから今日もまた、ドュマはあのアルカイルの国、シワナの港町の祭りに向けて、のんびりと歩いている。
帰れる場所、帰れる時間があるというのは幸せだった。これからは毎年これを自分の課としようと思っていた。祭りが終わったら、街を出てまたどこか知らない世界に歩いていく。そしてまたぐるりと回り道をして一年に一回帰ってくる。一晩だけを、人とともに温かな街で眠りたい。
「そろそろ着くかな?ちょっと早く来すぎたかな」
ドュマは立ち止まって首をかしげた。祭りが楽しみすぎて、戻ってくるのを少し早まったかもしれない。ドュマが関門の前に来た時、昨年は関門にも飾られていた赤い提灯はまだ取り付けられていなかった。
「いらっしゃい、シワナの街へ」
白髪と灰色の髪が混じった男は、ドュマの顔をろくに見ることもなく不愛想に言った。とても気難しそうな無骨な男だ。けれどドュマはこの男が嫌いではない。祖父と同じ匂いがする。
「こんにちは、おじさん。今年も会えたね」
「ここを通る人間の顔何ぞいちいち覚えとらん」
男はそっけない。ドュマは、門から見える大通りをきょろきょろと見渡した。
「おじさん、祭りはまだなの?」
「あと6日後だなあ」
「ありゃ。僕早く来すぎたみたいだなあ。おじさん、宿はここあるんだっけ?」
「仮にも観光街だ。あるに決まっているさ。だがわしは教えんぞ。自分で勝手に探すがいい」
「うん。そうだね、ありがとうおじさん」
ドュマはにっこりと笑った。淡い橙と白の薄煉瓦のタイルでできた道を踏みしめる。
祭りであろうとなかろうと、この街は常に電灯や店先の看板にたくさんの装飾が施してあった。色とりどりで、とても可愛らしい。ドュマはにっこりとした。なんだか楽しい。
後で思えば、やっぱり祭りより早くこの街に踏みいってしまったのは、軽率だったかもしれないともドュマは思う。
それでも、自分があの時あの場にいたからこそ、彼女の傷をあの程度で抑えられたのだとも思った。あの時自分がいてよかったと思った。水に愛されていてよかったと思った。
人との縁が少しずつ絡み合って、いつしか彼女にたどり着けたこと、たとえ一番残酷な形だったとしても、ドュマは感謝している。喜んでいる。たとえその気持ちが彼女にとっては救いにならなくても、それでもドュマにとっては大きなことだった。村人たちに忌み嫌われた目元の二つの痣・・・黒子も、このための道標だったのだと今ならわかるから。
カレンダー
| 04 | 2024/05 | 06 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(10/08)
(10/07)
(09/24)
(09/24)
(09/10)
(08/11)
(08/11)
(08/11)
(08/10)
(07/27)
最新トラックバック
ブログ内検索
最古記事
(07/19)
(07/20)
(07/20)
(07/27)
(08/10)
(08/11)
(08/11)
(08/11)
(09/10)
(09/24)
P R